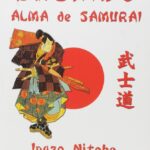、70代以上の日系ブラジル人2世は、既に人生の佳境を過ぎ、大半は穏やかな余生を送っている。そんな彼らが、普段は特に思い出すことはなくても、人に聞かれれば「残念に思う」ことがあるという。それは、戦中戦後に生まれた世代は、日本の在外公館がブラジルになく、両親が出生の届出をすることがなかったため、日本国籍を有していないということだ。
在外公館が引き揚げた時期に生まれた世代
「昔から残念に思ってきたのは、20年以上、年に2回はビザを取って日本に渡航してきたのに、日本国籍が取れないことです。二人の姉は、日本とブラジルの二重国籍を持っています。戦争で日本の在外公館が引き揚げていなければ、両親は私や弟妹の日本国籍も取得していたと思います」と話すのは、昨年末に廃刊したニッケイ新聞社の社長・高木ラウルさん(76、サンパウロ市在住)。まさに終戦直後の1946年に、熊本県・広島県出身の両親の元、サンパウロ市で生まれた。
米国政府に背中を押されたブラジル政府は1942年1月に連合国側につくことを決め、枢軸国側に外交断絶を宣言した。そのため、在伯の日本国在外公館は1942年7月に総引き揚げとなった。そこから1950年12月に在外公館が復活するまでの約8年間、ブラジルで生まれた日本人移民の子の出生届けは出せなかった。
在サンパウロ総領事館よると、51年8月から戸籍事務を正式に扱うことになり、その埋め合わせとして戦中戦後に生まれた子については、1952年まで届出期限を過ぎていても出生の届出を受け付ける特別な救済措置を取っていた。
高木さんは「1年の救済措置があったとはいえ、当時の子育て世代の親は仕事で忙しく、出生届けどころではなく諦めの境地だったと思います。情報がいきわたる時代でもなく、サンパウロ市内でも、奥地からの交通事情を考えても、手続きに行くのは大変なことでした」と続ける。
日本への渡航よりも目の前の生活
高木さんが子供時代を振り返ると、当時の日本人移民は、日本の敗戦もあって、ブラジルでの生活を維持するのが精いっぱいだったという。親自身も子どもたちも、日本はもちろん、外国へ旅行することなど想像もできず、日本国籍の重要性について考える余裕もなかった。
高木さんの姉で、1939年に生まれて二重国籍のある日系2世の聖子さん(83)は、「日本へは数年に一回行くくらいでしたが、日本国籍があるので渡航は簡単です。もちろん在外選挙もできます。弟は1年に2回以上、日本へ行く度に、ビザの手続きが大変そうでしたけどね」と話す。(取材=大浦智子、つづく)