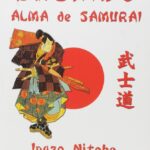上毛新聞社から3月に出版された『サンバの町それから 外国人と共に生きる群馬・大泉』を読み、ブラジル人日本就労開始33年目における「日本の共生の現実」を考えさせられた。
この本は、地元紙大泉支局の歴代記者の中でも、最も赴任期間が長かった和田吉浩さんが中心になってまとめたという。つまり日本人側の視点からブラジル人コミュニティの変遷を丁寧に記した、とても珍しい本だ。
あとがきによれば、和田さんは1989~91年、2017~2020年の計5年半を大泉支局で同コミュニティを定点観測した。その間、96年には上毛新聞で「サンバの町から」を40回連載し、翌年書籍として出版したという同案件のスペシャリストだ。
同書の帯には「町民の6人に1人が外国人、大泉町を知れば日本の近未来が見える!」「移民政策を考える上で必読の書」とあるが、まさにその通りだろう。
本書の流れを追うと、まず1990年代はコミュニティの「蜜月期」。バブル期の工場労働者不足を補うために、どんどん人数が増えてブラジリアンプラザなどの象徴的な施設が誕生。20万人を集客する全国的知名度を持つ巨大イベントに育った大泉カーニバルパレードが生まれるなど、コミュニティの量も質も拡大した。
2000年代は地元日本人住民とコミュニティの「軋轢期」。外国人犯罪や不良外国人生徒による事件などが目立つようになり、コミュニティに対する風当たりが強くなり、カーニバルは中止。08年のリーマンショック後に日本政府の日系人帰国政策に後押しされて、多くの日系人がブラジルに戻った。
2010年代は「停滞期」。東日本大震災が起きて帰伯者が増え、その後は微増する流れがあったが、パンデミックでそれも途絶えた。
そんなコミュニティの盛衰が、その時々の事件や出来事を通して記される。地元政治家や企業関係者、コミュニティに深く接している地元日本人の証言に加え、日系人の声も十分に織り込みながら立体的な実像を描き出している。
終章には、和田さん本人の《定年まで残り三年となった二〇一七年、二度目の大泉支局勤務を希望した。「サンバの町から」の続編を書き残すことが、私の使命と思えたからだ。この町に日系人が集住するようになった責任の一端は、報道した私にもあるだろう》(225頁)との辛そうな胸中が記されている。
一体何に対して責任を感じているのかと読み進むと、《大泉町に日系人コミュニティができて三十年、時間が経過すれば日系人も日本語を覚えて、日本社会の一員として働き、税を納め、次の世代を育んでいくものだと私は漠然と信じていた。しかし、そんな予定調和的な世界は来なかった。移民を受け入れるというコストについて、私は楽観的すぎて、見誤っていた。日本と南米の双方にルーツを持ち、日本人と比較的近い文化や考え方を持つ人たちであっても、同じ空間を共有し、お互いに譲り合い、理解し合うことは、容易なことではない》(230頁)と後悔の念を行間に滲ませている。
これを読んで、著者の誠実さに感銘を受けた。と同時に、「移民」に関する認識に違いを感じ、そんなに責任を感じる必要はないのではと思った。コラム子からすれば状況はどんどん変化するものであり、これから良い意味での成果が現れ始めると思えるからだ。
「長年住むと現地語が上達する」という誤解
認識の違いを具体的にいえば、「30年も時間が経過すれば、日系人も日本語を覚えて」とある点だ。留学生や駐在員が現地に居ついた場合には、1世でも現地語が達者になることが前提とされるが、いわゆる「移民」の場合それは難しい。
移民はエリートではなく一般大衆だ。語学の才能を持っている人は限られている。ブラジルに移住した日本人にもできなかったことを、日本は在日ブラジル人に求めている。
ブラジルに60年住んでいるから、ポルトガル語がペラペラになる訳ではない。長い年数をかけたから語学が上達するのではなく、早い年代から言葉の勉強を始めたほうが上達は早い。
大人になってから外国語の勉強を始めて、その国の人並みになれるのは語学に才能がある人だけだ。でも年数ではなく、幼年期から移住先の言語に接していれば、わずか数年で移住先国の人並みになる可能性が高い。
とはいえ、言葉がペラペラでなくともブラジル「社会の一員として働き、税を納め、次の世代を育んでいく」ことを、日本移民は成し遂げている。言葉の不自由さを補うのがコミュニティの役割であり、だからこそ2世の教育が大事だ。
ブラジルでは1世が踏ん張って2世に高等教育を受けさせ、大学進学を薦めた。だから子孫はブラジル社会への貢献ができた。日本では日系人の親が教育にあまり熱心ではない人が多く、日本側の教育制度としても、外国人児童生徒への教育が義務化されていない。学習内容を理解していなくても、トコロテン式に卒業させられてしまう。
在日2世が日本人と同じ待遇で教育を受け、日本人と同じような意識を持つようになれば、成人する頃には1世と日本社会の中間層になり軋轢は生まれづらくなる。2世の教育こそが社会適応の要のはずだが、そこが日本では重視されていない。「いかに幼い段階で日本の教育になじませるか」や「多文化人材として大事に育てる配慮」があれば、日本の将来を支える有益な人材になるだろう。
日本で活躍を始める「ステルス日系人」

例えば2020年2月、パンデミックが始まる1カ月前からニッケイ新聞で記者として働き始め、3月一杯でブラジル日報を退社した天野まゆみさんは、ブラジル生まれ、群馬県桐生市育ちの日系3世だ。京都の大学を卒業し“祖国”を知るために2年間、邦字紙編集部で働いてくれた。
今回ブラジルに来るための航空チケットは大泉町のブラジリアンプラザで購入したという。彼女は日本での教育に関して「親からはしっかりと勉強しろといつも言われていました。『日本の学校では落第はないが、ブラジルなら勉強ができないとすぐ落第だぞ』と脅されました」と笑う。彼女は4月末から日本での生活を再開する。
2月3日にオンライン開催されたJICAオンライン・セミナー「多文化共生・日本社会を考える」連続シリーズ第6回で、国外就労者情報援護センター(CIATE)理事長の二宮正人さんは、《笠戸丸移民から26年目の1934年にはサンパウロ大学(USP)で学ぶ日系人がすでに数人いた。だが、在日伯人コミュニティにおいては2016年時点の調査で約300人が大学在学中だった。その10年ほど前から日系人の大学入学が言われており、卒業生も含めれば1千人近くいるのでは》と比較した。
その一人が天野さんだ。すでに日本には、ブラジル日本移民が30年間で生み出した以上の大卒者がいる。
和田さんは《移民を受け入れるというコストについて、私は楽観的すぎて、見誤っていた》と書いている。だが、ブラジルでは移民開始38年が経った終戦直後の時点で、血なまぐさい勝ち負け抗争が起きて新憲法に「日本移民入国禁止」の条文が入れられそうになったことまである。
憲法制定議会の裁決でなんと賛否同数になり、議長権限でギリギリ否決された。まさに首の皮一枚で生き残った。ブラジル移民を創始した“移民の祖”水野龍ですら「移民は失敗だった」と思い込んだまま、1951年にこの世を去ったほどだ。日本の日系人はそこまでの事態になっていない。
ブラジルでは60年代以降の2世の活躍で現在まで続く日系人への信頼は醸成された。それは今の日本でいえば天野さんのような世代だと思う。
在日2、3世の大半は日本国籍を所有して「ステルス日系人」として活躍しているので、日系ブラジル人としては注目されていない可能性がある。でも、いつかそれも理解される。コラム子は「彼らの本格的な活躍はこれからだ」と楽観している。(深)