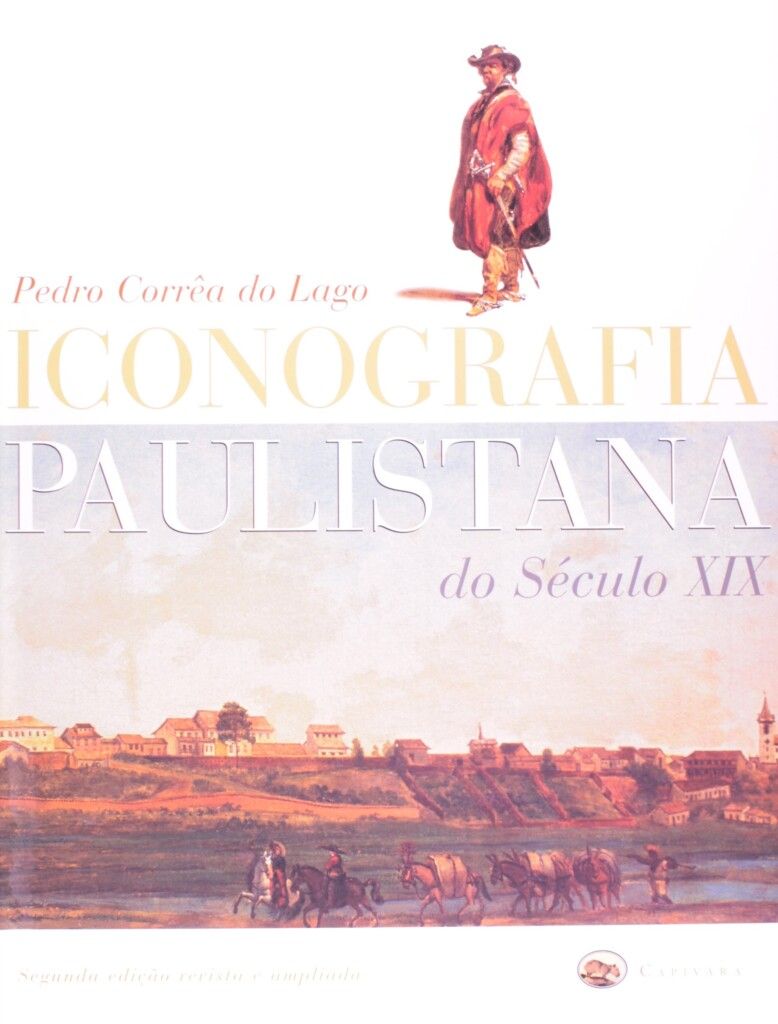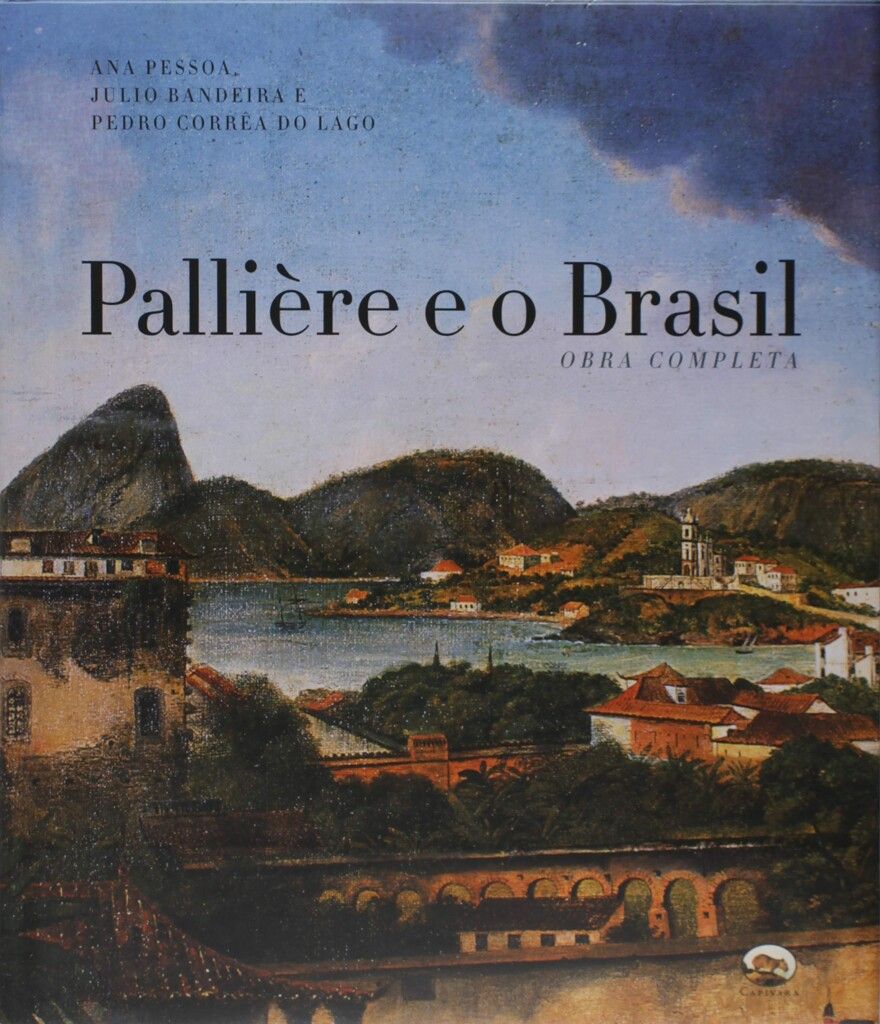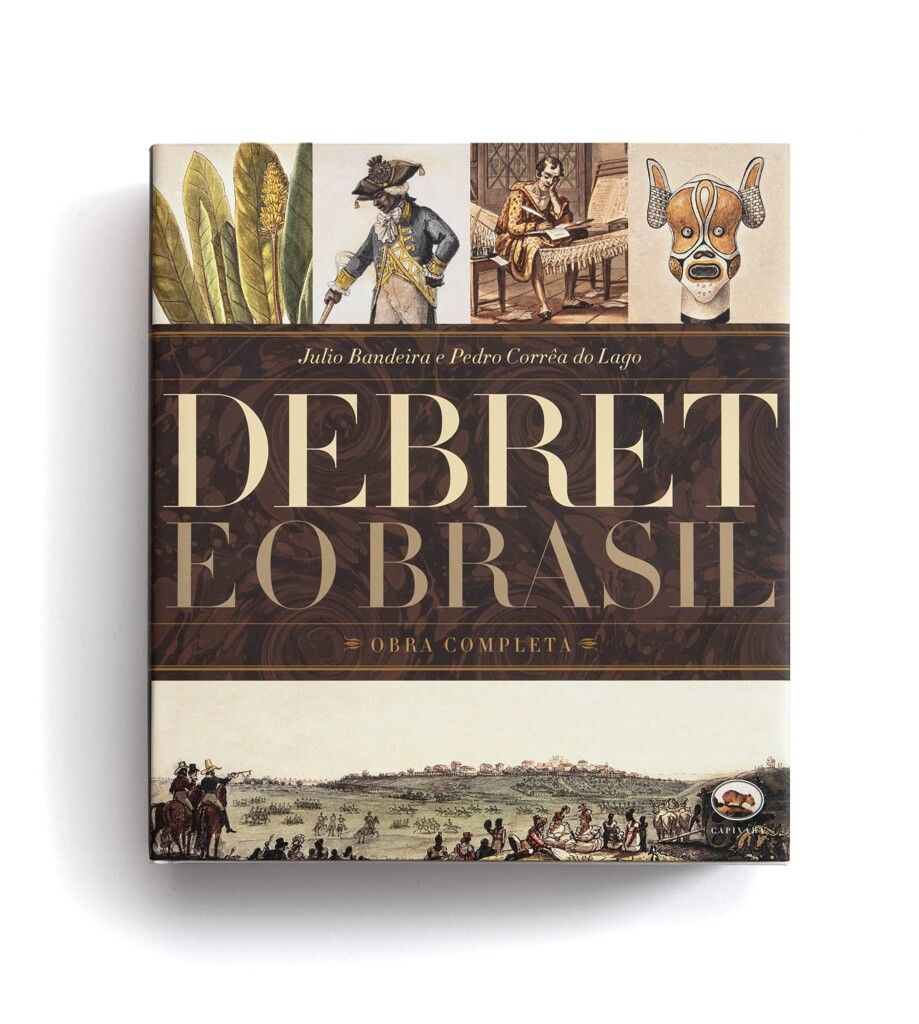ここ数年間で社会生活の形態がすっかり変わってしまい、家で過ごすことが多くなる中で、何かと再発見の面白さを楽しんでいる。その中でもギリェルメ・ゲンスリーの昔日のサンパウロの絵葉書や写真集と、ブラジル人コレクターで作家兼編集者ペドロ・コレア・ド・ラーゴ氏によって編集された『ICONOGRAFIA Paulistana do Século XIX. São Paulo. 2003』(19世紀のパウリスタの図像)という二冊の本は宝物を再発見したような嬉しさを味わっている。
ゲンスリーの写真は20世紀初頭までをサンパウロの記憶として残されたものであり、「19世紀のパウリスタの図像」はヨーロッパから訪れた画家の描いた絵画が著名な収集家によって出版された画集である。どちらも百年前の風雅なサンパウロに誘う古き町の残像である。
「顔のない写真家」ギリェルメ・ゲンスリー
サンパウロ市のアベニーダ・パウリスタはこれほど麗しい街並みを誇っていたのか…、その美しさを教えてくれるのがギリェルメ・ゲンスリー(Guilherme Gaensly 1843 – 1928)の絵葉書であり、写真集である。彼の絵葉書は数多く出回っているので、多くの人がきっとどこかで一度は目にしたことがあるかもしれない。
ゲンスリーは、スイス生まれだが、移住してサンパウロなどで活躍したブラジル人写真家である。彼は1928年にサンパウロで85歳のときに肺炎で亡くなり、妻イーダ(Ida Gaensly)との間に子供はなかった。1880年代半ばまではバイーアで活動し、その後サンパウロで政府の依頼を受けて本格的に市街の写真撮影に従事した。
彼の作品は、1895年から1925年までのサンパウロの町の近代化への移行期にある都市の風景と、新たに出現した大都市を記録した。その作品に登場するのは、コーヒー農園主の大邸宅、農場、公共の建物、教会、学校、病院、劇場に加えて、馬車から電気鉄道への交通手段の変遷を撮影。サンパウロが近代化するための技術的および構造的な斬新さを記録した。
写真の特徴は、黒人奴隷の写真はほとんどなく、通りから貧困や日常生活の喧騒、生活の営みから発生する汚れといったイメージを一切除外していること。建物の上層から町全体を展望するパノラマの風景、町の美しさと憧れを誘うことをイメージした構図を取り入れていること。
そのためヨーロッパ風の壮大で優雅な建造物、落ち着いた町の雰囲気の写真からは、現在と比較して、ここにこのような景観があったのかと、にわかに信じがたいほどヨーロッパ風の瀟洒な市街地の雰囲気が漂よっている。
ゲンスリーは、ブラジルの写真史における特別な地位を獲得した写真家であった。彼の作品は、サンパウロが近代都市として変遷する姿を写真という媒体によって、後世に残さんがために写真家としての任務を全うしたイメージアーティストの先駆者の一人といえよう。
しかし、当時は彼の業績が特定されることはめったになかったが、それは写真家の名前よりも出版社の名前を表示することが重要であったという理由がある。当時のブラジルを世界に知らせることが目的であり務めであるため、ゲンスリーは徹底して自分の肖像を残さなかったことから「顔のない写真家」と言われている。

写真は、国際的宣伝の絵葉書として広く売られた
絵葉書は、通信手段であるだけでなく、その地域を広く世界に知らせる宣伝の手段にもなる。ゲンスリーの写真は、サンパウロ州のイメージを国際的に宣伝するために最初のイラスト入りの出版物として使われ、広く出回った。
それらは、ブラジルの富を象徴するコーヒーと鉄道の重要性を強調し、サンパウロの発展の進捗状況を知らせるために、一連の物語風な説明を含んで作成された。物語には、大きな経済的および社会的影響を及ぼしたイタリア人コミュニティの日常風景、コーヒー農園の農民や労働者、コーヒー生産における技術的および構造的な斬新さが目新しかった。
さらに、イタリア移民のマタラッツォ家やクレスピ家など大富豪となった人々の邸宅なども町の印象を重厚にし、移民大国ブラジル・サンパウロの、1890年から1900年代の急速な発展を誇らしげに物語り、理想化されたサンパウロの都会のイメージをふんだんに取り入れ、高級で、近代的で、新古典主義のスタイルを醸し出す工夫がされていた。
哀愁のアべニーダ・パウリスタ
全長2.8キロのこの通りは1891年12月8日に正式開通された当時までは、コーヒー産業で成功した大富豪の邸宅が立ち並んでいた。それが、1930年代、サンパウロの発展を目指したジェトゥリオ・ヴァルガス大統領の指揮の下、シカゴの都市部発展プランに倣って、パウリスタ大通りを中心とした都市計画が進められた。
1950年代に入ると今度はジュセリーノ・クビチェック大統領が考案した都市計画が進められ、パウリスタ大通りは金融街となり、ブラジル経済において重要な役割を担う町になった。1972年、サンパウロ市長だったファリア・リマは「新たなパウリスタ(Novo Paulista)」プランを掲げ、街路樹を全て切り倒して車輌の交通量を2万台から10万台まで拡大し、今日のパウリスタ大通りの姿になった。
大通りにはかつて、モクレンとプラタナスの街路樹で飾られていた
1880年代まで、この地域はモーロ・ド・カグアスと呼ばれ、トゥピー語で「大きな森」を意味し、人里離れた土地であった。神父マヌエル・アントニオ・ビエイラが所有するシャカラであったという説もある。
通りは非常に広く、1909年にサンパウロにモクレンとプラタナスの街路樹が植えられ、舗装された最初の公道であった。1950年代までは、両側に大きな区画が配置された邸宅街の装飾の美しさはヨーロッパに劣らぬ、南米の別格の地の印象であった。同時に、フランスの景観建築家ポール・ヴィヨン、英国の建築家で都市計画家のバリー・パーカー等によって発足したトリアノン公園の建設も進んだ。
19世紀の終わりには、通りにはすでに約50の邸宅が立ち並んだが、それらは、裕福なコーヒー農園主、豪商人、銀行家、実業家たちで、彼らの住居や夏の別荘として使用するために新しい通りに面して、堂々とした邸宅を競って建てた。その中には、デンマークの実業家アダム・ディトリック・フォン・ブロー、イタリアの実業家フランチェスコ・マタラッツォがあり、その宮殿のような建物はイタリアの建築家ジュリオ・サルティーニとルイージによって設計された。
今現在のシダーデ・ショッピング・サンパウロは、かつてのマタラッツォの邸宅があった場所に建っている。個人的な好みに過ぎないが、せめて邸宅の外観だけでも残せなかったのか。内装は近代的にすれば、多くの利点を伴い効率的なことは言うまでもない。日本流の古民家再生に倣って、外観は、重厚荘厳な歴史的佇まいとして残したら、人気の観光地になったのではないか。残念に思う。
国内で最初のアールヌーボー様式の建物、ホラシオサビーノの邸宅は、大通りに面して、現在は見るも無残に立ち枯れた状態のままで放置されている。個人所有の事情の深刻さはともかく、南米を代表する国際都市サンパウロの大通りにはそぐわない。だからと言ってすぐに解体して今風近代建築の建物にするということではなく、市として歴史的建造物保存という観点から遺跡保存の範疇で考えられないのだろうか。
サンパウロ大学(USP)の建築学教授、パウロ・ガルセス(Paulo Garcez)は、「アベニーダ・パウリスタで起こったことは、国民の悲劇」と吐露しているように、それまでの市内の建物の多くは20世紀を通して取り壊され、20世紀初頭までの古き美しきこの町の姿は、「永遠に消された」。その面影を辿ろうと思えば当時の写真集を眺めるしかない。
現在のパウリスタ大通りには、1947年に開設したMASP、1990年代から銀行、その他の金融機関の本部が移転して以来、文化の中心地となった。病院、教会、報道機関、劇場、映画館、研究所、レストラン、ホテル、FIESPカルチュラルセンター、イタウカルチュラル・センター、そして最近ではジャパンハウスの開設などがある。だが、全体の印象といえば、筆者の狭小な印象では、歴史的な見どころは少なく、魅力に乏しく、むしろ一抹の寂しさ、時の移ろう哀愁を感じている。
『Iconografia Paulistana do seculo XIX』(19世紀のサンパウロの図像)と、『Palliere e o Brasil obra completa』(アルノー・ジュリアン・パリエールの描いたブラジル)
手元にあるこれら二冊の画集は、19世紀のサンパウロが描かれた傑作集である。『19世紀のサンパウロの図像Iconografia Paulistana do seculo XIX』は、ペドロ・アランハ・コレア・ド・ラーゴ(リオ・デ・ジャネイロ、1958―)によって収集され編纂。2004年1月のサンパウロの450周年を記念して、1998年にカピバラ・エディトーラから出版され、初版はすぐに完売し、再出版された。
アルノー・ジュリアン・パリエールにより描かれた色彩豊かな美しいサンパウロの風景画とともに、昔日のサンパウロの姿が実に美しい。この絵画集は、今日、19世紀のサンパウロの図像画の最も重要な作品群と言われている。
図像学(Iconografia)とは、絵画・彫刻などで、そこに描かれた対象物の表す意味やその由来などについて研究する学問であるが、この本には、19世紀にサンパウロを訪れた15人の画家たちが見て描いた180枚の図像から、当時の景観のみならず、風俗、生活習慣などを知ることができる。
1870年以降、コーヒーが町の発展の最初の波となり、1875年にはわずか人口3万人ほどのサンパウロが、周辺地域から続々と人が集まり始め、1995年には世界有数の経済都市として大発展した。それまでは近隣ののどかな田舎町の一つであった。
ラバを交通手段としていた日常活動や、住宅街は、こじんまりとして、清潔で整然としていた。
住居は、タバティンガの石灰を使った版築工法で建てられ、広い軒が張り出し、ほとんどの家には空気の入れ替えのためにパティオ(中庭)があり、それに面した窓を開ければ、通り側の窓は閉じたままにすることができた。
他にも、当時の男女の服装は興味深い。豊富な食べ物を前に奴隷の子供たちが楽し気に遊んでいる絵からは、ブラジル社会特有の奴隷制度の断片を窺い知ることができる。小高い丘には教会の尖塔が聳え、眼下の町を見守っている。
この画集には、アウグスト・デ・アゼヴェド・ミリタンの写真も多く掲載され、1860年当時のブラス、グローリア通り、サン・ベント通り、ラルゴ・ド・パラシオなど興味は尽きない。
怪物収集家、ペドロ・コレア・ド・ラーゴ

これらの作品を発見し、編纂・出版したのは、リオ・デ・ジャネイロ在住のペドロ・アランハ・コレア・ド・ラーゴ氏である。彼は、編集者、作家、歴史家、コレクター、キュレーター、美術史において卓越した業績を上げ、世界最大の写本の個人収集家と認められた人物である。その功績を「エルパイス」のトム・アベンダニョ記者の独占インタビューから紹介したい。(2018年6月9日)
コレア・ド・ラーゴ氏のコレクションは過去の歴史的人物の絵画、本、書簡、原稿、写真など膨大である。彼は、妻のビア・コレア・ド・ラーゴとともに、ブラジルの芸術を専門とするカピバラ出版社を設立。国内外で埋もれたブラジルに関連する何千もの作品を発見し収集した。
出生は、リオで、アントニオ・コレア・ド・ラーゴ大使の息子であり、オズヴァルド・アラーニャ政治家の孫で、幼少期のほとんどをブラジル国外で過ごし、父親と一緒に国外のさまざまな役職に就いていた。彼はフランス語で読み書きができ、5つの言語を話す。作家ルーベン・フォンセカの義理の息子ともいう、並外れた名家の出身である。
コレア・ド・ラーゴが6つの分野、芸術、文学、歴史、科学、音楽、娯楽の中から半世紀かけて、西暦1500年から最も優れていると認めた4千人から5千人に及ぶ数万の手紙、文書、署名入りの写真、およびあらゆる種類の手書きの書簡を集めた。
1908年の『蝶々夫人』(1904年)で有名なジャコモ・プッチーニによる「西部の娘(A Fanciulla do West)」の手書き楽譜。マーラーがお金の工面のために音楽を書いていたと述べる書簡、ベートーベンの走り書きに記された精神的消耗の状態が読み取れる文書。
アインシュタインが、自閉症の息子の治療のための精神分析を拒否したこと。サルトルはノーベル賞の受賞を拒否。アラビアのロレンス自身が回想録《知恵の七柱》(1926)に言及した文書など。これらはほんの一部に過ぎず、挙げればきりがないほど興味深いものばかりである。
これらの膨大なコレクションの始まりは、外交官の父が、当時世界で最も重要な人々の伝記が掲載されていた本を持っていて、その本には住所が付いていたため、何十通もの手紙を書き送ったことから始めたという。
2018年、このような歴史的著名人の重要な作品が、ニューヨークのモーガン図書館で展示され話題を博した。
彼は言う。「自分は百科事典のようなコレクションをしたいのです。たしかに、誰にも収集癖はありますが、私は1500年以降の4―5千人に及ぶ人物の遺物を収集しているのですから、変人と呼ばれるのは当然でしょう。莫大なお金も使いました。しかし、値段のつけられない作品を見つけた時の興奮や、それらが将来のために計り知れないほど重要な意味を持つことか。ひとつ例を挙げましょう。900年前の羊皮紙に多くの関心が集まった。そして今、それが目の前にあります。ブラジルで最も偉大な宝物のひとつとなった一枚の羊皮紙が、過去と現在、そして未来をつなぐのです。これが私のコレクターとしての最高の喜びであり、誇りでもあるのです。」
「いつか来た道」「いつか見た町」
20世紀後半から21世紀前半の数十年を通しての国際紛争で、現代人は古代の文明都市イラク、シリア、そして今、学生時代にキエフ王国の繁栄と呼んで学んだウクライナが壊されていくのを連日目の当たりにしている。やがて再建の日が訪れるであろうが、昔日の面影はもう留めないであろう。
万物はすべて変転し生滅するもので不変のものは一つとしてない、と仏教は教える。しかし、人間が営々として築いた都市には、そこで生きた潜在意識が横たわっている。人間の脳裏には、刻み込まれた過ぎし昔の残像が消えず、時空を超えて、かつてそこに居たかのような思いを抱くことがある。
色褪せた絵葉書や画集で見たような、ここは「いつか来た道」「いつか見た町」という不思議な体験である。