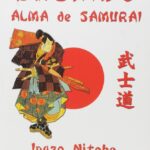明治の男子、青柳郁太郎を突き動かす情熱

イグアッペ植民地を建設した中心人物は青柳郁太郎(いくたろう)である。彼をつき動かしていた情熱は「日本人は海外に発展せざるべからず」(発展せざるをえない)という明治の若々しいテーゼだった。
明治40年ごろ、北米の黄禍論に暗い思いを抱いていた海外発展論者たちにとって、杉村濬(すぎむらふかし)ブラジル公使が提出した報告書の、人種偏見がなく未開の原始林が広がるブラジルは、明るい青空のように感じられただろう。
青柳たちは「東京シンジケート」という企業組合をつくった。そこから実地調査に派遣された青柳は単身、明治43(1910)年6月に東京を出発して、まずドイツに2カ月滞在してドイツ政府の移民制度を研究した。
9月14日にリオ・デ・ジャネイロに入港し、サンパウロ州を中心にブラジル各地を視察した。
サンパウロ州の地形は海岸近くに1千メートル程度の急な海岸山脈が走っているので、海岸と内陸をつなぐ道がない。平坦でコーヒーや綿で開けつつある内陸部と比べると、海岸は人口希薄で荒涼とした風景が続いていた。ところどころにブラジル発見当時に探検家たちによって開かれた小さな港町が、繁栄を内陸部に奪われ、時代に置きざれにされ、すっかり寂れて残っているだけだった。
そんな町の一つにサントスから100キロメートル南下したイグアッペがあった。古い小さな港町だった。月に2回サントスから小さな連絡船がやってくる。
青柳はイグアッペにやってきて、リベイラ川を遡ってみて川岸の両側に広がるほとんど無人の処女林が州有地であることを知り、ここを植民地建設の候補地として、サンパウロに戻り、グランドホテルに腰を落ち着け、州政府との長期の交渉に入った。
交渉の結果、「東京シンジケート」はリベイラ河畔に州有地2万ヘクタールの無償譲渡を受けた。ただ、4年後に占有されていない土地は返還する義務があった。そして、レジストロと称する場所に本部を設置するために50ヘクタールの土地を譲渡する一項もあった。リベイラ川上流は以前は砂金の産地だったので、ポスト・ド・レジストロ(登録所)という地名は砂金の登録所があったためである。
たった一人で未知の国に乗り込み、州法を一部改正させてまで日本人の自由になる広大な土地を獲得した青柳の信念と行動力は高く評価すべきであろう。
彼は明治元年の生まれだから、ブラジルに来たときは満43歳だった。千葉の堀田藩の侍医の家に生まれカリフォルニア大学を卒業した。26歳の時、自費でペルーの農場を視察しているから移住についての関心は留学時代に抱くようになったのだろうし、移住は出稼ぎ移民であってはならないという持論も留学時代に根無し草の日本移民を見ての実感だったろう。
州政府との契約にサインした青柳は急遽、帰国し、明治45(1912)年12月に第3次桂内閣が成立し、桂の肝いりで渋沢栄一、高橋是清らを集めて資本金100万円「ブラジル拓殖株式会社」ができた。
青柳がブラジルで視察した場所だが、コーヒーや綿の地帯には全く足を向けていない。のちに桂内閣で農務大臣になった子爵大浦兼武たちとブラジル移住研究会を作った頃から、日本のコメ不足を解消する米つくり移民を考えていたようだ。(その危惧は数年後に現実になる。1石15円だったコメの値段が大正7年から急騰し、1石50円を超えた。はじめは局地的な騒ぎだったが、ついに大正の米騒動とよばれる全国的な暴動になった)
なお、なぜ彼がリベイラ河畔を最終的に選んだかについては、彼の口から語られたものは伝えられていない。「立地条件がいい」とは語っているが。
ふとしたことで私はリベイラ川の水量や流程が彼の故郷の利根川とほぼ等しいことに気づいた。痩身長躯の洋行帰りの紳士の脳裏に、わんぱく時代に遊んだ故郷の川の面影が何らかの作用をしたと想像するのも、あながちこじつけではないかもしれない。

ジププーラ(桂植民地)
河口のイグアッペ町の郡会では、将来レジストロが発展してイグアッペが置き去りになることを危惧して、レジストロとイグアッペの中間のジププーラに郡の土地を提供し、小植民地をつくるよう青柳に申し入れた。
土地の広さから測ると約30家族分の広さだった。青柳は、既にブラジルにいて義務農年を終えた人々から入植者を募集した。しかし当時の人々ははやく儲けて日本に帰ることしか頭になく、定住を前提にした入植希望者はいなかった。
…そのころ、サンパウロ市にはコーヒー園労働に耐えられず夜逃げしてきて、都会の一隅に吹き溜まりのように集まってその日暮しをしている落ちこぼれの移民の一群れがあった。コンデ坂のポロン(半地下室)に住んでいたので、人々は「コンデのバガブンド(風来坊)」と呼んでいた。
ポロン(半地下室)は急な坂道に面して家を建てるとき、土台を平らにするために構造上できる部屋だ。低い天井にはむき出しの下水管が走り、青や緑のカビがいつも壁に繁殖している。鉄格子の小さな窓が石畳の歩道すれすれに開いているが、青空などは決して見えず、道を行く人々のズボンや靴が見えるだけだった。
時々犬がこちらを覗いたりする。何時も雨の夕方のように薄暗くて、家賃は格安だが、住んでいると身も心も腐り始め、はやく上の部屋に住みたいという希望が心をしめるようになる。
青柳はそこでようやく30家族をかき集めることができた。彼はそんな境遇の人たちにイグアッペの川や青空の話をしたに違いない。
この30家族は大正2(1913)年11月にサントス港から400トンの蒸気船に揺られてイグアッペについた。
若くして海外移住の夢を見続け、いま最初の入植者たちを従えてイグアッペの浜に降り立った長身の青柳の姿は颯爽たるものがあったに違いない。しかし、そのあとについている落伍者風の30家族の人々がさっそうとしていたとは想像しがたい。
人々は河船に乗り換えて10キロほど上流のジププーラに遡った。
そこは川が大きく曲がり、のちに桂山と呼ばれる小山が突出した、親しみのもてる風景だった。男たちはさっそくフルチンになって川に飛び込んで泳いだ。
遠くからそれを見ていた土着の住民たちはそれ見て目をむいた。ブラジルの田舎の住民にとって他人に肌を見せるのは非礼の最たるものだ。水浴の場合、男はパンツをはき、女は服を着たまま体を洗う。驚いた住民の何人かはカヌーを漕いで、急いで下流のイグアッペの警察署まで訴えに行った。
警察では、郡会が後押ししている日本人入植者たちのことだから「風俗の違い」ということでこの訴えを取り上げなかったが、森の中に静かに暮らしていた住民にとって、新来の日本人たちはずいぶんと騒々しい威勢のいい集団に見えたに相違ない。ほんとうはコンデ坂のポロンで希望のないその日暮らしをしていた人々に過ぎなかったが。
資本金100万円の「ブラジル拓殖株式会社」(ブラ拓)の初仕事として、彼らを成功者にするのは難しい仕事ではなかった。入植地を作るための仕事は山ほどあり、自分の家を作っても日当がでた。
1年後にブラジルと日本で配られたパンフレットを見ると1家族平均1300ミルレース(900円)の利益になっている。ブラジル移民たちもそうだが、利益どころか生きるのに精いっぱいだった大正期の日本の百姓にとってどんな効果があったか想像に難くない。
この年に亡くなった桂太郎を記念して、イグアッペ郡会の承認を得て、ジププーラは正式に「桂植民地―コロニア・カツラ」と命名された。…このようにして、イグアッペ植民地は「桂」「レジストロ」それから後の大正9年にさらに山奥の、レジストロの4倍の州有地をもらって「セッチ・バラス」の3植民地になった。

権兵衛とカラス
サンパウロ州海岸のマングローブ地帯に大正6(1917)年に入植して農業を続けていた松村栄治さんのお宅に伺って入植当時の話を聞いたことがある。
マングローブはタコの足のような空中根を張っているが3、4メートルの低木だし、松村さんのところはマングローブから他の種類の樹木(ニャクチロンなど)に林相が変わる地帯で、ニャクチロンも樹高4、5メートルくらいなので、うっそうたる森と言うほどではない。入植当時にすでにぽつりぽつりと先住民がいたそうだ。
松村さんは入植してすぐに米を作った。これは当時の日本政府の方針だった。工業などの発達で都市化が進み、それに反比例して農業人口が減少して、コメ不足が日に日に深刻になった(松村さんが入植した翌年には、いわゆる大正のコメ騒動が起きている)。
海外に日本人の手で米作基地を作る必要を感じて、地理的には遠いが排日論のないブラジルが選らばれた。移民を運び、帰りにコメを運べば立ち遅れている日本の海運業界の刺激にもなるので、遠いことはさほどの障害とは考えられなかったようだ。ここで思い切って米を作れば日本のコメ不足などたちまち克服できる。
それを運べば定期の南米航路が開発できる――そういう目論見というか、壮大なビジョンだった。
私が訪ねた時、松村さんは白髪の品のいい老人だった。住まいは白壁に広い窓をとり、ピカピカに磨きこんだ板の間にうすべりを敷いて一枚板の机をはさんで座った。地酒のピンガとマンジューバ(ワカサギに似た小魚)のから揚げが机にのっていて、窓からは濃い緑色の風が吹いていた。
入植当時の思い出話。「ここは海岸に近くて標高が3メートルくらい。木こそ生えていたが、まあ沼地みたいなところだった。雨が多くて、そう、あの頃は今よりたくさん降った。実った稲は立ったまま芽がでたし、刈り干ししても芽がでてきて困った。日本の米作技術を基にしてさらに大農式でやろうと意気込んできたが、とにかく気候が違うからはじめのうちはやることなすことすべて失敗だった。
こちらの春の10月頃にモミを播くんだが、沼地の草をきれいに刈り取って田のように整地して、穴を掘って丁寧にモミを植える。そうやったんだ。すると、たくさんの鳥が来て土をほじくり返してモミをみんな食ってしまう。どうもこれには弱ったな」
松村さんがそう話して苦笑したとき、私は思わず大笑いして(ピンガの軽い酔いも手伝って)、「権兵衛が種まきゃカラスがほじくる」と歌いそうになった。もっともその歌の節を知らないので歌えなかったが…。日本にもブラジルにも似たような話があるものだと思った。ただしブラジルにはカラスはいないけど(カラスに似た鳥でアヌーという鳥がいる)。
「ところがわしたちが入ったころ、ポツポツと、森の中に住んでいた住民たちのコメの作り方は沼みたいな湿地にいきなりモミをぱらぱらと播いて、それからざっと草を刈る。そのまま草の葉は片付けない。それだけさ。実にいい加減な頼りないようなやり方だ。ところが、そのやり方だと不思議に鳥はモミをつつかない。はじめのうちは新技術で大々的にやろうと意気込んでいたが、失敗して結局、先住民たちの素朴なやり方を見よう見まねでやるようになった。わしらも沼にパラッと播いて草を切り倒す。それだけ。…そうやって米を作るようになった」
パラッと播いただけのモミはついばまずに、丁寧に埋めたモミをほじくる鳥の習性は矛盾しているが、鳥にとってはそれなりに意味がある行為に違いない。私の素人推測を言えば、刈った草が散乱していると外敵の蛇などが潜んでいる危険があるので、鳥は警戒するのかもしれない。
あるいは動物には餌を根絶やしにしないあるメカニズムが働くというから、そういった類の何かのメカニズムかもしれない。いずれにしても当時の大浦農相たちが閣議で練ったプランと入植者たちがやっていたことがあまりに違うので、日本へなかなか米が送られなかったのも仕方ない。
このようにイグアッペ植民地は人々を受け入れて発展したが、母体となった「ブラジル拓殖株式会社」は大正6年に消滅した。
7月の臨時議会で関連会社合同法案が通過し、資本金1千万円の「海外興業株式会社」(いわゆる海興)が成立し、ブラ拓もそこに吸収された。移民送出業務主体の移民会社中心の海興と、定住による海外発展をめざすブラ拓の理念が合うはずがなく、青柳はイグアッペ植民地から去っていった。
青柳が去った後も、彼の理念を受け継いだ植民者たちがいたが、その話は別の物語になる。
山奥のセッチ・バラス植民地はついに適作物が見つからず、一時は養蚕に活路を見出そうとしたが、普及し始めたナイロンと価格で太刀打ちできずついに廃村になった。
私は人の住まなくなった旧セッチ・バラス植民地の跡を訪ねたことがあるが、放置されて大木になった桑の木に紫に熟したグミがたくさんなっていて、鳥たちがそれを啄んでいた。私が立ち止まって見上げても、鳥たちは逃げようとはしなかった。普段は人の気配のない自然がそこにあった。