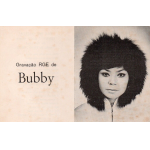国外成功者に関心が低いブラジルマスコミ
6月16日付け本紙の記者コラムは「アストラッドの死がブラジルで話題にならない理由」というタイトルで、ボサノーヴァを世界中に広めた功績者の訃報がブラジルであまりにも小さいのは何故か、についての論評だった。誠にご尤もな指摘だが、私はこのコラムを読んで別の観点からひと言追記しておきたいことがある。
そもそもブラジルのマスコミは国外で成功した自国の芸能人に対して関心が低い傾向があり、ハリウッド大スターになったカルメン・ミランダでさえ故郷リオのコンサートでは冷ややかな反響だった。しかし日本人がブラジル音楽になじみ始めたのはボサノーヴァの世界的ヒット後なので、アストラッドやセルジオ・メンデスも北米経由の日本公演だったから大スター扱いされたが、渡米前には無名だったアストラッドは「イパネマの娘」一曲で一躍有名になったので本国での評価が低いのは仕方ないだろう。
モンローよりヘップバーンが好きな日本人
ブラジルは1960年代後半から、いわゆるフェステイバル時代と呼ばれるロック・ポップが若者を魅了してしまい、ボサノーヴァは完全に消えてしまった。在サンパウロ総領事館へ赴任してきた元バンドマンの領事が「楽しみにして来たのにラジオ、テレビ、ライブ等でボサノーヴァが全然演奏されない」と驚いていたくらいひどかった。
ベテラン・ミュージシャンの多くが転職、隠居、海外移住などに転向して、トム・ジョビンが「空港はブラジル音楽家の出口だ」と言った暗黒時代に入ったのである。ところが日本においてはブラジル音楽評論パイオニア故大島守氏が残した名言「ボサノーヴァはリオで生まれ、サンパウロで育ち、バイアで死んで、日本で再生した」の最後の段階に入っていたのだ。
ブラジル人の間で「日本人はボサノーヴァ好き」だと定評があるのは何故だろうか。これは日本人の性格に発するところが大きいと思う。面白い例を挙げてみよう。日本円の価値が上がり日本企業が米国の不動産を買い出した頃、在サンパウロ総領事館で広報文化の仕事を担当していた私のところへ或るブラジル人実業家が資料を求めに来た。
その後、市場調査の訪日から帰った彼の日本印象が非常にユニークだった。「日本はマリリン・モンローよりオードリー・ヘプバーンの方が人気が高い世界で唯一の国だ」と言ったのである。この言葉に私は「日本人のボサノーヴァ好き」のヒントを得たような気がしたのだった。
確かに日本人にとってはマリリンのようにセクシーな成熟女性より、可愛い女学生タイプの方が近づきやすいという傾向がある。つまりソフトムードなのだ。大島さんがミューズ歌手ナラ・レオンに「あなたにとってボサノーヴァとは何ですか」と質問した時に彼女が英語で答えた「インティメート・ウイスパリングよ」と一致するではないか。
その上、大ヒットを飛ばした歌手が素人っぽいソフトなささやき調のアストラッドなのだから欧米人やアフリカ人と比べて線が細い大和なでしこには「これなら私も」と挑戦する気になるのは納得できる。

女性とサンパウロがけん引した日伯音楽交流
実際に1972年からサンパウロ総領事館に勤務した私のところへ日本から紹介状を持って訪問してくる人は大半が女性だったし、日本からのブラジル音楽研修についてのインクァイアリー・エアメールも女性が多かった。
日本人の殆どがポルトガル語を理解しないのにポルトガルをはじめ言語的に近いイタリア、スペインよりも日本で最高に受けたのは、メロディー、ハーモニーがモダンでリズムが心地良いから歌詞など関係なく、おしゃれでソフトなBGM(バックグラウンド・ミュージック)として今でも愛好されているのだ。
実を言えばボサノーヴァが世界的に広まった契機となったカーネギーホール・コンサートよりも前に、日本人はサンパウロのトリオ・タンバタジャというコーラスグループ本邦長期公演によってボサノーヴァ実演を見ているし、1960年のフランス映画「黒いオルフェ」は日本で新しいブラジル音楽愛好者が生まれるきっかけとなっていたのである。
だからアストラッドが訪日した際に大島守氏がマッチ箱でバトゥカーダ・リズムをたたいて見せたら彼女は驚いて「あなたはブラジル生まれでしょう」と言って信じられない様子だったそうである。
1977年にブラジルの美空ひばり的存在のエリゼッチ・カルドーゾ訪日公演直後にリオでジャーナリストやミュージシャンに日本ではサンバ、ボサノーヴァが多く演奏されて日本人の音楽的レベルは非常に高い、と話しても誰も信用せず、まるで自分がホラ吹きと思われているみたいだと憤慨していた。
ブラジル音楽の日伯間直接交流は1960年からすでに始まって、ミュージシャンの訪日や日本人のブラジル音楽現地研修などはすべてサンパウロが中心となって活動が始まったのである。
浜口庫之助(ハマクラ)さん作曲のトヨタカローラ初のCMソングを歌ったクラウジア、トリオ・パゴン、パウ・ブラジル、トキーニョ・グループ、日本に永住したソーニャ・ローザ、皆サンパウロからの送り出しだった。
日本人のブラジル音楽現地研修生がわんさとやってきたのもサンパウロで、1960年代に早くも現在赤坂ボッサジャズクラブ・ケイのママである歌手のオケイさんは日本移民の殿堂サンパウロ文化協会でボサノーヴァ・コンサートを開催したのである。渡辺貞夫(ナべサダ)さんのブラジル・ミュージシャンとのレコーディングもサンパウロで1968年だった。
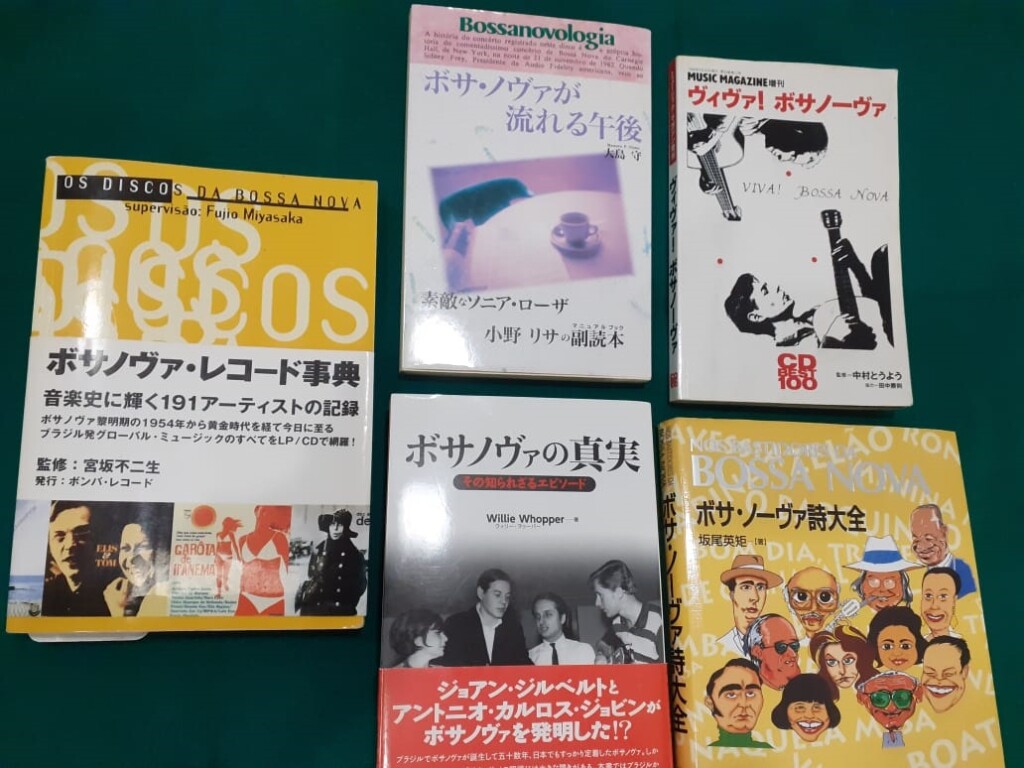
日本で再起してもそれを語らないブラジル人音楽家
リオ市南部地区の音楽エリートたちが、日本ではボサノーヴァはビジネスになると目が覚めたのは、ボサノーヴァ創成期の中心人物ロベルト・メネスカルのつくば万博1985年初公演からである。
彼は日本の音楽市場を目にして自分たちのお蔵物が金になると知って狂喜し、再びボサノーヴァに積極的に取り組んだのである。それがブラジルにおけるボサノーヴァ・リバイバルの口火となったと言えるだろう。
情報化時代以前に日本人とあまりコンタクトがなかった首都のリオっ子(カリオカ)には、自分たちが文化商工業のトップだと言う気風があって、日本人農民にはジャズやサンバなんて無関係と言う先入観を潜在意識に持っているので、日本を知ったメネスカルの驚きは大きかったに違いない。
一方、北米から帰って来て仕事も少なく忘れられてしょぼくれ生活をしていた作曲家ピアニスト、ジョアン・ドナートへ再起の手を差し伸べたのは、日本のボサノーヴァ女王小野リサちゃんである。彼を日本へ連れて行き豪華なドナート名曲集CDアルバムを制作してやったり、リサちゃんとの演奏旅行などでドナートはすっかり生き返り、それが契機となって彼の名声がはなばなしく復活したのである。
それは喜ばしいことであるが、それ以来ジョアン・ドナートはマスコミで自分の芸歴について多くのインタビューの中で日本の「ニ」もリサの「リ」も語られたことがないのは如何なるものか。彼がジョアン・ジルベルトに次ぐ風変わりな性格のせいであろう。
最後にボサノーヴァ全盛時代のスター歌手二人、歌姫ダルヴァ・デ・オリヴェイラの息子、ペリー・リベイロとサンパウロのシンガーソングライター、セルジオ・アウグストが私に偶然にも同じような内容の述懐をしたので紹介しておこう。
「この年になってから昔と同じレパートリーをくり返して仕事になるのは日本のおかげだよ」