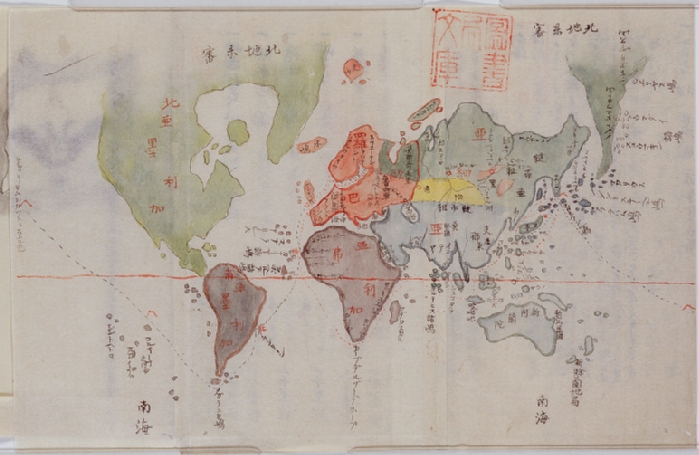
長崎港では、幕府の奉行の上陸許可を待たされた。お役所仕事で手間取り、ために太十郎は精神に異常を来し、刃物で自殺をはかった。一時は危篤となったが、助かったという。
やがて四人は、迎えに来た仙台藩の役人に引き渡され、江戸に送られた。
江戸では同藩藩侯が、家臣の大槻玄沢(蘭学者)、志村弘強(儒学者)らに命じて、四人の体験談を聞き取らせ、書物にまとめさせた。
これが『環海異聞』である。
玄沢は「未曾有の一大奇事にして…(略)…古今三千年来…(略)…の奇話異聞なり」と、その驚きを文字にしている。
『環海異聞』の記事の中には、デステーロの風景描写が載っており、
「湊は大なれども入り海にて、至って浅く、大船は岸に寄る事能わず…(略)…英船二隻、異国船二隻碇泊中…(略)…此の地の舟は細長く笹の葉の如し…(略)…此の地極熱、冬季なし…」
などとある。
四人が上陸して見た町、家屋の造り、食物、果実、野菜、動物などが絵図つきで記されている。
一方、四人を長崎に送り届けた使節レザノフにとって幕府側の応対は、意外にも冷淡かつ非礼であった。
実はロシア側は、その十二年前、やはり別の漂流民であった大黒屋光太夫ら二人を蝦夷のネモロ(根室)まで送り届け、国書を幕府に差し出していた。その時は、丁重な応対ながらも実は追い返された。さらに、その十二年前も似たようなことが起きていた。
レザノフは激怒、その感情が尾を引き、以後、両国間に波風が立つ。それは江戸時代末期に関する史書類に詳しい。
足跡を求めて
南樹は『埋もれ行く…
…』の再版の十一年前、若宮丸の水主たちの足跡を求めて、一人、フロリアノポリスを訪れている。一九五八年のことで、八十歳であった。
生涯、金銭には無縁の生活を送った彼は、この時も、費用については「貧困の懐中を傾けた」と自身、記している。
現地では、州政府の役人や地元の歴史学者を訪ね「百五十五年前に、日本人四人を乗せて寄港したロシア軍艦」に関する資料を探した。
そんな大昔、ただ寄港しただけの外国船の記録など残っている筈はないのだが、大真面目であった。
結果的には、やはり何も得られなかった。やむを得ず、海岸を散策、往時を偲び短歌を詠んだ。彼は歌人でもあった。但しその歌は、ひどく素人臭い。
ついでながら記しておくと「南樹」は、彼が歌を作った時に使った号である。それ以外、例えば前記の二冊の著書の執筆者名は「貞次郎」を使用している。が、世間では南樹の方が通りが良かったし今もそうである。それで筆者も、こちらを使用している。
話を戻すと、フロリアノポリス行だけでも驚きだが、南樹は二年後の一九六〇年、訪日して水主の一人の墓石を求めて、仙台を訪れている。墓石が現存することを、何かの資料で知ったらしい。この訪日は別の用件も兼ねていたが、仙台行は主目的の一つであった。
時に八十二歳。取材に協力した地元の人も呆れたのであろう、墓石のある場所が辺鄙すぎることを理由に、現地入りは止めるよう忠告した。南樹はそれに従ったが、諦めた動機は体力の問題ではなく、旅費の不安であった。訪日経費はサンパウロの友人たちの醵金に頼っていた。
榎本武揚

話は再び若宮丸の水主のデステーロ寄港の頃のことになるが、その数年後の一八〇八年、ブラジルでは、ポルトガルから国家そのものが亡命してくる━━という一大変事が起きた。
本国がナポレオンの侵攻を受けたためで、王族、貴族、役人、軍人などから成る大亡命団であった。人数は一万数千人ともいうし、数千人ともいう。
十三年後、ナポレオンが没落、王族はポルトガルへ帰った。その時、皇帝は長男ドン・ペドロを摂政として残し、植民地ブラジルの統治権を与えた。
そのドン・ペドロは翌一八二二年、独立を宣言、君主制を布き帝位につく。しかし九年後に退位、彼もまたポルトガルへ帰った。
以後、執政府時代を経て一八四一年、ドン・ペドロ二世が帝位を継承した。同皇帝の在位は長く、半世紀に及ぶことになる。
その在位中の一八六七年、一隻の日本軍艦が首都リオ・デ・ジャネイロに寄港した。幕府がオランダから購入した開陽である。これに榎本武揚が乗船しており、十一日間滞在した。(リオ・デ・ジャネイロは以下、リオと表記)
榎本は日本に帰国後、幕末の争乱の中で、海軍副総裁に任ぜられる。しかし、その幕府はすでに崩壊中で、官軍の攻撃を前に降伏を決定する。
が、榎本はこれに従わず、艦隊を率いて脱走、蝦夷地へ至り、独立政府を樹立、新天地の開発・経営を企てる。官軍はこれを許さず、いわゆる函館戦争が起こる。
榎本は破れ降伏するが、新天地への夢は忘れることなく、それを二十年以上も後に、海外への移民事業として具体化する。その対象国の一つとして浮上してくるのが、彼がかつて立ち寄ったブラジルなのである。(つづく)








