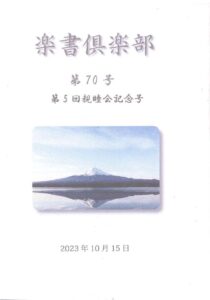
サンパウロ市リベルダーデ区の元ニッケイ新聞社の建物内に、「楽書倶楽部」という文芸雑誌社(電話11・3341・2113、Eメールnitimaisousho@gmail.com)がある。今年で14年目を迎える当文芸冊子の投稿記事は、健筆家揃いである。俳句・短歌、エッセイ、小説、そして表題に沿った感動的な挿絵、その他がぎっしりと詰まり、全編を精読するのにひと月はかかる。
その中でも筆者のように昔の移民生活を知らない者にとっては、衒いのない率直な言葉で綴られた、悲喜こもごもの体験談が、庶民による移民の歴史として毎回勉強になっている。
「毒姑」はどのように改心したか
「第70号・第5回親睦会記念号(2023年10月15日号)」の中の、末定いく子さんの『毒姑の改心』では、「永遠のテーマ・姑と嫁の理想的な関係」について深く考えさせられた。
この中で登場する「嫁」の体験記は、「現代の嫁なら絶対に堪えない」であろう、過酷な家制度に縛られた移民社会での「姑と嫁」の話である。ちなみに、文中で末定さんは「毒姑」は自分が作った造語である、と断っている。この物語は次のとおりである。
かつて、末定さんの営んでいた鍼灸院に「N」という70代後半の女性が来院した。彼女は現在、ご主人亡きあと、息子に家業を任せ楽隠居をしている。Nさんは19歳の時、酒飲みの父親同士が酒の席で決めた縁談によって、他所の植民地の、とある一家の長男の嫁へと、追い出されるように嫁がされた。
嫁ぎ先には40代半ばの舅姑(きゅうこ)(夫の父母)がいた。22歳の夫と、18歳、2歳の義弟があり、暮らしぶりは裕福だった。Nさんは全ての家事一切と、2歳の義弟の世話を任された。嫁は家族と同じ食卓で食事をすることを許されず、少しばかりの残り滓だけを口にし、いつも空腹であった。夫は嫁の辛酸な立場を知っていた。しかし、舅姑に媚び、妻を阻害した。
当時の移民社会で世話役になった姑は、出かける前に、バナナやリンゴ、卵などに番号を書き、米には川の字をなぞって、嫁が隠れて食べないようにした。夫は妻の身に付ける衣類や靴が傷んでいても、決して新しいものを買い与えなかった。
やがて義弟が結婚すると、姑はその嫁を「娘ができた」と自慢し、Nさんとは全く違う待遇をした。
Nさんはついに決断する。4人の子供を連れて家を出てサンパウロに向かった。偶然に出会ったクリーニング店主の厚意に甘え、店に住み込みで働いた。当時から、クリーニング分野では日系人は良い仕事をすると評判で、彼女も一生懸命働いて、子供を育てた。
ところがある日、義弟夫婦に追い出された夫がひょこり訪ねて来て、自分も店で働きたいという。事情を察した店主が承諾し、一家はその店で働くことになった。夫の働きぶりも認められ、Nさんはようやく穏やかな幸せを実感する。
ある日、「毒姑」の義母が乳癌で床に臥せているとの知らせを受けた。Nさんは積年の思いはさておき、義母を見舞い、サンパウロに連れ帰り、2年間、在宅看護に徹する。
やがて、人生の終焉を迎えた義母はNさんの手を取り、「生まれ変わったら、あなたの嫁になり、うんと尽くします。あの世からもあなたのことを見守ります」と語り、静かに逝った。
Nさんはその時、「姑の酷いいびりが一瞬に溶けた思いがした」と、笑って言ったという。
この話を読んで思い出したのは、芥川龍之介の「一塊の土」という、姑と嫁のエゴをテーマにした傑作と言われる作品である。この作品の時代は、Nさんの時より前になるが、一つ家に暮らす姑と嫁の関係が描かれている。ここではNさんの場合とは逆で、「働き病」の嫁の立場が圧倒的に強く、姑が嫁の顔色を窺いながら生きる話である。
「一塊(ひとくれ)の土」の場合

「一塊(ひとくれ)の土」の解釈や読み方は、いくつかあるが、一つの塊になって寄り合って生きる、あるいは所詮人間は一塊の土に戻っていく、と解釈されている。まさに、ある農村の一家を舞台にして、永遠のテーマとしての姑嫁問題、「家を守るとは」「女の幸せとは」ということを、現代に突き付ける作品である。
登場人物は、姑のお住(すみ)。実の息子仁太郎は8年間寝たきりだった。息子の嫁はお民。そして、孫の広次。寝たきりの息子が亡くなり、介護から解放されたお住はホッとした。気がかりは嫁の身の上だった。嫁が外の男と再婚して孫を連れて出られては困る。
そこで姑が考えたのは、息子の従弟を婿にしようということだったが、嫁は一切話に取り合わない。嫁にすれば、この家を出て行く気はないし、亡き夫の分まで畑で働けば良い。いずれ広次が相続する財産をわざわざ二つに割ることもない、と言った。嫁に家を出られては困るが働き手の入り婿の男は欲しい、しかし、嫁は家に留まると聞いて嬉しくもあり、姑はそれで納得した。
嫁の働きぶりはまさに男勝りだった。「稼ぎ病」に罹ったように朝早くから晩まで働く。畑で働く嫁の代わりに、孫の世話と家事全般はすべて姑がこなした。姑は嫁にいつも敬意を感じていた。敬意というよりもそれは畏怖であった。それほど嫁の働きぶりはすごいものだった。
働き者の嫁は家長となり、姑のお住は家長でありながら、嫁に気兼ねして、わがままは一片も思ってはいけない、息抜きしたい、小遣いほしいなど言ってはいけない。従順でなければならないのである。
ある日、嫁は土地の一部を桑畑にして、片手間に養蚕もはじめようとする。姑はこれに反対した。家事だけでも大変なのに、これ以上は手に負えない。本音は隠居したそうな姑に対して、嫁が次のように言い放った。「男手もなく、貧しい農家で、隠居したいなどとは恥を知れ」と一喝する。
話し合いの末、桑畑はやることにして、養蚕のほうは断念した。とはいえ、この一件以来、互いの関係にしこりが残る。姑は、嫁からいつもの強い口調で小言を言われ続け不満が募っていった。
3年経ち、4年が経った。嫁は相変わらず外でせっせと働いて、姑はひとり家事全般を引き受けていた。が、老いた姑にとってそれは大変な重荷になってきた。しかし、嫁は実によく働く。姑は結局、ひたすら家事をこなすほかなかった。孫が母よりも祖母になついてくれているのが、唯一の慰めだった。
8年目、嫁の働きぶりは村でも評判になった。いまや世の女性の鑑とまでいわれるようになっていた。12、3になった孫が学校から帰ってきて、「ぼくのお母さんは偉い人なのか」、と聞かれて、お住の堪忍袋の緒が切れた。
「あの女は人前ではよく働くが、心はうんと悪い」。お住の怒りは、嫁に対するばかりでなく、「嘘の皮」が横行する社会に対してか、また同時に、孫がそんな評判を刷り込まれて母親を偉い人と口にすることに激しく怒った。
とうとうお住は、孫の前で泣きながら嫁を罵しった。嫁は冷笑を浮かべてお住みに言った。
「お前さん、働くのが嫌になったら、死ぬよりほかはねえよ」。8年間の我慢の限界で、姑ははじめて、嫁を大声で罵ったが、嫁は寝転んでその言葉を聞き流していた。
ところが翌年、嫁が腸チブスで突然亡くなった。村長をはじめ、村人は一人残らず会葬し、嫁の早逝を惜しんでくれた。しかしお住はほっとしていた。貯金もあり、畑もあり、孫も一緒にいてくれる、これからは小言を言われる心配もない、自分の好物だって気兼ねなく食べられる。
ああ、一生のうちでこれほどほっとしたことがあっただろうか……。ハッとした。姑は9年前に、同じように安堵したことを思い出した。それは息子の葬式の済んだ晩のことだった。
姑は自分の情けなさに涙した。たしかに嫁は強情な人間だった。自分と息子、嫁3人、ことごとく情けない人間だ。しかしその中で、いまでもひとり生き恥をさらしている自分こそが、最も情けない人間ではないか。
「お民、なぜ先に逝ってしまった? ああ、嫁よなぜ先に逝く…」。お住の涙は止まらなかった。
さて、この二つの「姑と嫁」の立場の違いの底に横たわる共通点を探ってみる。第一に、表で働く姿は評価され、家事一切は評価されないという不満。団塊の世代が後期高齢者となった現代社会で、最も多いのは「姑と嫁の付き合い方のコツを教えて」という相談だそうである。
親の自分たちが諍いの種にならないためには、ひたすら息子夫婦に黙して従う。それが嫌なら、別居かホームに入居する。理由は只一つ、嫁への気兼ねから生まれる選択だという。息子一家に早々に財産分与した。
そして、自分たちは住み慣れた家で最後まで暮らすので、息子夫婦は別居してくれという条件を付ける。その時は機嫌良くお互い納得したが、すぐに家事や、孫育ては両親に頼み込む。これが意外に大変な労働で、高齢者の体力では到底及ばなくなる。もめ事が始まるのである。
つまり、現代女性やシングルマザーの社会進出によって生じる、祖父母の家庭内労働、専業主夫の負担は、家庭内の事であるがゆえに、その負担は深刻な問題になっている。たとえ、保育所やオール電化住宅の充実や、あらゆる社会的サービスが昔よりも充実しているとはいえ、家庭内の仕事は評価されにくいという現実がある。その務めの煩雑さ憂鬱さを、当人も不満ながら抱え込んでいるので、何かのきっかけで爆発してしまう。
『一塊の土』で如実に描かれているのは、村の共同体が常に目にした嫁の働く姿に対する評価と、女にとっては当然と思われている家庭内作業への無評価である。お住の不満はここに尽きるのではないか。
Nさんの場合も、姑が移民社会で世話役という重職をして、家事一切をNさんに背負わせ、Nさんへの日常的な嫁いじめは非常に手厳しく、弟夫婦と、Nさん夫婦に対する差別は酷すぎた。
そこで、見えてくるのは、Nさんの夫の不甲斐無さである。
第二に、姑と嫁の間にいる息子の自立が肝心

Nさんの夫は、なぜこうも嫁を守らなかったのであろうか。
昨今共通した戒めとして、息子の役割は、両方の愚痴の聞き役に徹し、その愚痴を双方に漏らさず、嫁の立場に立って母親の説得にあたるがよい。親の理想的な態度は、結婚した息子夫婦の日常は大筋を把握して、あとはできるだけ関わらず、頼まれごとの時だけ耳を貸す。簡単にお金で解決という愚策は施さない、というカウンセラーの意見である。
現代の「姑嫁の付き合い方」のコツは…。
ある姑さんが息子の家でくつろいでいるのに、嫁がお茶を入れてくれない。二人だけで飲んでいる。その理由を尋ねると、以前に嫁が黙ってお茶を入れて持っていったら、「頼んでもいないのに」と姑に言われた。だからもうお茶を出さない」なんと、互いが気持ちを察することができないことか。このような話は山ほど聞かされる。
『一塊の土』のお住もお民も、要するに、このような類の感情のズレが互いの気まずさに拍車をかける。それは何かというと、「私は一家のために身を粉にして働いている」立場と、「家事ばかりしているが、私こそがこの家の主人である」という家族内のパワーバランスのこだわりであろうか。
世代間の意識の違いが云々されるが、姑と嫁の関係だけでなく、人間関係は、互いに遠慮・節度・思いやりの心を尊重する余裕がないと成り立たない。
二つの物語の最後に、二人の姑が嫁のことを想い涙を流したところに、この問題の終着点が見えたように思う。結婚して嫁になったらそこには姑がいて、嫁もいずれ姑になるという輪廻は否が応でも繰り返される。
Nさんが尽くした姑への最後の親孝行と、お民を失くして、いずれ自分もお民と同じ一塊の土となるのだ、と悟ったお住の涙が、芥川龍之介からの教訓と感じた次第である。
【参考文献】『一塊の土』芥川龍之介、青空文庫(https://www.aozora.gr.jp/index_pages/person879.html)








