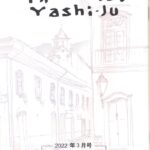瀬戸際にいるコロニア日本語文芸
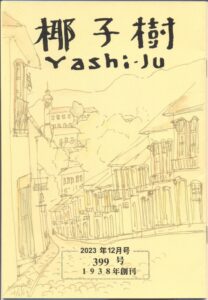
短歌誌『椰子樹』が創刊から86年後のこの4月に、大きな節目となる400号を迎えることを心から祝いたい。思えば昨年10月には、佐藤念腹が1948年11月に創刊した月刊俳句誌『木陰』とその後継誌『朝蔭』が通巻第900号という節目を迎えていた(1)。
その一方で、41回も行われた岩波菊治短歌賞は2008年に終了、第36回をもって「武本文学賞」も2019年に終了(2023年にポ語表彰だけ復活)。2019年、同文学賞主催のブラジル日系文学誌は日本語からポルトガル語主体に変わった。
コロナ禍は、ただでさえ瀬戸際にいたコロニア文芸をさらに追い込んだ。2019年9月に開催された第71回全伯短歌大会(椰子樹社、ニッケイ新聞共催)を最後に、同大会は誌(紙)上大会に変わり、以後、対面開催はされていない。
また昨年12月22日付本紙では《伝統あるサンパウロ短歌会が閉会=85年前創立、寄る年波に勝てず》(2)と報じたばかり。
これらの動きをコロニア日本語文芸の節目として、『椰子樹』を中心に振り返ってみる。
大正デモクラシーが地球の反対側で文芸運動に
1923年9月に関東大震災が起き、日本政府は罹災者救済の目的で一人200円のブラジル渡航費補助を同年末からはじめ、翌1924年から本格的に国策移民政策となった。これにより1927年から30年代前半が移民渡伯全盛期となり、邦字紙は部数を拡張し雑誌なども生まれた。
この時代はサンパウロ州やパラナ州の植民地で日本人地主や自営農が増えて経済基盤が固まり、文学活動が盛んになってきた時期でもある。経済基盤が整って、はじめて文化を語る精神的な余裕が生まれた。各地で短歌や小説などの集いがもたれ、コロニア文学が芽吹いた。植民地の青年会の会報に発表して腕試しをし、次に邦字紙に発表するという順番で活躍の場を上げていった。
日系文学先駆者の多くはアリアンサ移住地に最初に入植したという不思議な共通点がある。その第1アリアンサは1924年創立で、今年100周年の節目を迎える。
半田知雄は著書『移民の生活の歴史』のなかでアリアンサ移住地を、「はじめて試みられた日本の中産階級の移住」と位置づけた。大正デモクラシーの時代のそれだ。
研究者の渡辺伸勝は「海を渡ったデモクラシー」(『地理』2008年10月号、古今書院)のなかで「大正デモクラシー期の政治・文化・社会の特徴を体現する人びとや、この時期に活躍した人物の関係者が数多くアリアンサ移住地に移住している」(64頁)と書いた。
100年前アリアンサに続々と入植したインテリ
渡辺論文では大正デモクラシーの流れを汲む人物名として次の例が挙げられた。高浜虚子の愛弟子である佐藤謙二郎(念腹)が1927年にアリアンサに移住。東京帝大工科を卒業した橋梁技師の木村貫一朗(圭石)も同派俳人で1926年に移住した。
俳誌『ホトトギス』を掲げて大正や戦前の昭和期に俳壇に君臨した高浜虚子は、愛弟子念腹の渡伯に際して「畑打って俳諧村を拓くべし」という餞別句を贈った。念腹は地方の俳句会を巡回して回り、多くの直弟子、孫弟子を育て上げ、1948年に虚子本人から『木陰』と命名してもらい、俳誌を開始した。
「俳諧村」どころか地球の反対側に数千人の〝俳句王国〟を築き上げた。念腹の代表句「雷や四方(よも)の樹海の子雷(こがみなり)」の句碑は聖市イビラプエラ公園日本館内にある。
短歌界では、アララギ派の島木赤彦に師事した岩波菊治が1925年にアリアンサに先発隊として入り、この3人が中心になって最初の文芸雑誌『おかぼ』を1932年に創刊した。
その後、この日系文学先駆者の多くがアリアンサ入植後に過酷な生活就労環境から数年で病気になり、療養のために聖市やその近郊に転居したことから集まる機会が増えた。その中で1937年1月にピニェイロス区にあった暁星学園に武本由夫、徳尾渓舟(けいしゅう)ら5人が集まって第1回の歌会が開催されたのがサンパウロ歌会の始まりだった。
その翌年、『椰子樹』は1938年10月に岩波菊治や木村圭石らが中心になり、当時の坂根準三総領事とリオ横浜正銀の椎木文也支店長らが経済的な後ろ盾となって、34人の同人と共にサンパウロ市で創刊した。命名は坂根総領事で、日本の短歌誌には樹木名を冠したものが多いことと、椰子の木から《ブラジル気分の横溢、亭々と聳ゆる有様が、若い人達の気持ちにも合ひはせぬかと考えたからで、年の進んだ者は進んだ者らしく、すくすくと伸びゆく雄々しい椰子樹の将来の姿を胸にハッキリ描きながら静かにしみじみと、本誌の誕生を祝福したい…》と本人が創刊号巻頭で説明している。
当時はヴァルガス独裁政権で日本移民に対する風当たりが強まる逆風の中での出発であり、日本語出版物は戦争中に全て中断。だが、終戦直後の47年にサンパウロ歌会は復活。仲眞美登利、岩波、武本、清谷益次、徳尾宅などを会場に持ち回り開催された。
戦争中に暗号俳句で目覚めた天声人語の荒垣秀雄
『椰子樹』も真珠湾攻撃の2カ月前の1941年10月にいったん休刊した。ブラジル政府は1942年1月29日に日本に国交断絶を宣言し、首都リオ近郊の日本人の一部はフローレス島にスパイ容疑で収監された。
1948年11月に創刊された『木陰』第1号23ページには、「綴字俳諧」という宮坂国人による興味深い逸話が綴られている。日米開戦の半年前、朝日新聞の特派員荒垣秀雄は、宮坂に誘われて初俳句を作りに句会に参加した。
1942年1月にブラジルが枢軸国3国と外交断絶を宣言したことから、外交官や特派員らはリオ湾内のフローレス島の外国人移民収容所を獄舎にして抑留された。外にいた宮坂らは慰問品として書籍を届けようとするが、日独伊のものは不可として頑として受け入れなかった。
タイムとかライフなどの英字雑誌なら良いとのことで、一興を案じた宮坂は暗号もどきの綴字俳句を編み出した。《雑誌の所々のページの或る行の或る字の上に一寸した赤点を打って行くのである。その赤点付きの字を次々に書いて行けばローマ字綴の句になる》というものだ。
最初に贈った句は「秋の風獄衣の袖に吹く勿れ」で、《それが判らぬやうな頭なら、日本第一の新聞社の特派員などとは申されぬぞと意気込んだものである》とし、次の句を「友の居る獄遠くみて島の秋」と送った。同特派員は2カ月余り後、交換船で帰朝した。
荒垣は1939年に朝日新聞の東京本社社会部長、開戦前にリオ支局長、戦中にマニラ総局長を歴任。終戦直後の1945年11月に論説委員となり、同紙名物コラム「天声人語」を17年半にわたって担当したことで有名だ。
荒垣はマニラ総局長時代、ブラジルで俳句仲間だった市毛孝三のことを手紙で宮坂らに伝えていた。市毛は在サンパウロ総領事として赴任した1934年、俳句研究誌『南十字星』を仲間と創刊した俳人外交官だった。日本病院建設運動にコロニアと共に邁進、実現させた。
その後、鐘紡に入社、フィリピン支局長として戦地に渡り、1945年8月、日本軍敗戦とともにジャングルに逃亡、11月に病死した。そんな市毛に関して宮坂は、《終戦近くにルソンの山中にて「天心に日ありて我に影なかり」と云う悲壮鬼神を哭かしむる名句を残して長逝せられたのは痛恨無限である》と綴る。当地に関わりのある俳人だけに心に刺さる作品ではないか。

〝ブラジル短歌の父〟岩波菊治の生涯
『椰子樹』編集に長いこと携わり、2020年9月に104歳で亡くなった安良田済(あらたすむ)は「海外に現存する短歌誌としては世界最古」と繰り返し延べていた(3)。
日本人集会禁止だった戦時中にも関わらず、モジ郊外のコクエイラにあった、周囲に日本人ばかりが住んでいた養鶏場では、岩波や古野菊生、武本らも参加し、「秘密の歌会が年に3回ほど行われていた」という逸話も安良田から聞いた。椰子樹が再開した翌1948年からブラジル全土短歌大会も始まった。
〝ブラジル短歌の父〟岩波菊治は農業の傍ら、『椰子樹』の選者を兼ねつつ、戦前は日伯新聞の「日伯歌壇」の隆盛をもたらす中心人物として精進し、1952年に惜しくも胃潰瘍で52歳という若さで逝った。1954年、サンパウロ市誕生400周年を記念してコロニアが力をあわせて取り組んだ日本館の庭には、彼の歌碑が除幕された。今年はそこから70年だ。庭には代表歌「ふるさとの信濃の国の山河は心に泌みて永久におもわむ」と故郷・信州への望郷の想いが刻み込まれている。
《岩波は百姓が上手で、能く働いたに拘らず、どうした事か一生金には恵まれなかった。働き働いてもその暮し意の如くならず、さぞかし心身共に疲れたであろう。そのやるせない感情》がその歌には込められていると『物故先駆者列伝:日系コロニアの礎石として忘れ得ぬ人々』(日本移民五十年祭委員会、1958年)には記されている。
60~70年代が『椰子樹』の全盛期

『椰子樹』は終戦2年後の1947年5月に再刊された。1958年1月に出された同50号の「椰子樹概史」(吉本青夢)によれば、戦中の5年余りの空白を挟んで、50号に達し、その間に掲載された作品は総計1781首にもなる。延べ人員3712人、実質人員546人にもなり、当時いかに多くの歌人がいたかが伺われる。
『椰子樹』は当初年4回発行されていたが、戦後すぐに参加した安良田が編集を手掛けていた1965年から年6回になった。最盛期1960~70年代には200人以上の会員がおり、70頁もあった。清谷益次の後、安良田が椰子樹代表を務めていたが、日本移民100周年だった2008年3月から上妻博彦に代わった頃には40頁になっていた。第399号は28頁だった。
100周年当時、約150人会員中、中心は戦前の子供移民で、2割程度が戦後移民で、代表になったのは上妻が初。当時上妻によれば短歌人口は「500人に満たない」と言っていたが、現在は数十人だろうと思われる。
2009年3月25日付けニッケイ新聞によれば、2008年に創立70周年を迎えた『椰子樹』は翌2009年を機に刷新を図った。それまで10年間に渡って多田邦治が担ってきた編集は、梅崎嘉明、上妻代表、藤田朝日子の3人体制になった。年6回発行を09年、以前の4回に戻した。
2008年まで41回も行われた岩波菊治短歌賞は終了し、代わるものとして「ブラジル短歌賞」を2009年から創設するなどの新機軸も打ち出した。その後、多田に編集が戻り、現在に至る。多田が今日に至るまで長年『椰子樹』編纂に尽くしてきた時間と労力は、何物にも代えがたい貴重なものであり、何らかの表彰で報いるべきだと心底思う。
「文学の鬼」の武本文学賞も役割を終える
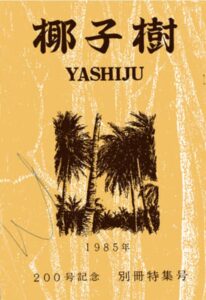
海外日系人文学研究ノート「ブラジル日系人の短歌(阿尾時男、元奈良産業大学教授)」(4)は、『椰子樹』創設、『地平線』『コロニア文学』『コロニア詩文学』など数々の日系文学活動に関わった武本由夫(1911―1983年)をこう解説する。
《安良田済は、武本由夫の歌碑序幕式の挨拶で彼を称して「文学の鬼」と呼んだ。確かに、武本ほどその一生を日本語だけにかかわって生きた人物を見出すことは難しかろう。コロニアに於ける他の文芸人は、当然のこと文芸以外に生活を他の職業によって成り立たせてきた。武本は、人生の節々でこれで良いのかと自問することを繰り返しながらも、結局、文芸以外の生活を意志的に拒否することを彼自身に課したのだった。コロニアの文芸にのみ情熱を燃やして一生を送るという、誠にいさぎよい見事な生涯であった》(16頁)
東洋街の一角にある彼の歌碑には「砂丘にまろびて韜晦を楽しめば海よりそよぎて朝は流れるる」と代表歌が刻み込まれている。前述論文は「真に武本を知る人には象徴的」な代表歌の選択だとし、《文学というものを時代と風土の所産とみなし、風土にしっかりと足を下した生活者の詩歌、土着的情緒を根底とするものでなければならないと考えていた。しかし、彼は実作者としてはそれを果たせず、内心忸怩たるものを好きな酒に紛らわせていたところがあったのではないか》という心情が歌に込められていると解説をする。
彼が亡くなった1983年に「武本文学賞」が設置され、2019年3月の「第36回」をもって同賞は終了した。ただし、2023年からポ語作品の表彰だけを行うものとして、武本文学賞は復活を果たした。その賞を主催していた「ブラジル日系文学」誌はそれを機会に日本語主体からポ語に変わった。
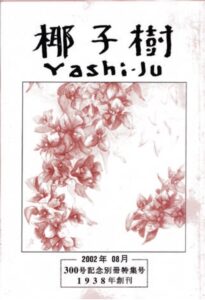
サンパウロ市ガルボン・ブエノ街の大阪橋の袂の日本庭園入り口に立つ句碑には《幾山河ここに恋あり命あ里》(安藤魔門)という川柳が彫られていることも忘れてはならない。東洋街で心を焦がすような熱い恋をして、命を削るような辛い思いをした人には、ここは異国の地だが故郷(里)のように感じるという移民ならではの想いが込められた名句だ。
今も続く『椰子樹』『朝蔭』はもちろん、本紙『ぶらじる俳壇』(選者=小斎棹子、伊那宏)『ぶらじる歌壇』(小濃芳子)にしても、続いていること自体が〝奇跡〟だ。おそらく当地以外の日本移民社会ではとっくに移民文芸は滅びているのではないか。
ブラジルにおける移民文学は十分に役割を果たしたと確信する。『椰子樹』を編纂する多田邦治、『朝蔭』の佐藤寿和(すわ)、本紙選者3人にしても「日本語移民文学を遺そう」とする意志の強さと志の高さには本当に頭が下がる思いだ。(敬称略、深)
(1)https://www.brasilnippou.com/2023/231207-24colonia-2.html
(2)https://www.brasilnippou.com/2022/221222-21colonia.html