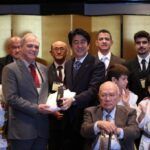その後、訪日の機会が二度あり、田島家にも寄ったが、双方から千江子の話はでなかった。その頃、田島はかなり憔悴して、絵の具が身体に悪いんだが絵は止められない、と自嘲まがいに話していた。そして、別れた翌年に逝った。それ以来、矢野の故郷訪問の楽しみは半減したが、田島を悼むとき、つい千江子に思いを馳せて、電話を入れたのである。
その後、訪日の機会が二度あり、田島家にも寄ったが、双方から千江子の話はでなかった。その頃、田島はかなり憔悴して、絵の具が身体に悪いんだが絵は止められない、と自嘲まがいに話していた。そして、別れた翌年に逝った。それ以来、矢野の故郷訪問の楽しみは半減したが、田島を悼むとき、つい千江子に思いを馳せて、電話を入れたのである。
電車は、広島駅に着いた。プラットホームに、千江子と瓜二つの八重子が立っていた。最後に逢った頃の千江子の年齢に見える。
矢野が初対面の挨拶をすると、
「あら、田島さんも一緒じゃなかったのですか」
と八重子は怪訝な顔をした。
「電話で話せばよかったのですが、期待を裏切るようで、言いそびれました。田島も四年前に亡くなりました。彼と千江子さんを弔う意味でやっきました」
「まあ、そうでしたの」
八重子は、失望の色を見せた。が、それ以上、何も言わず駅を出ると、近くに駐車して置いた自家用車に矢野を招じ入れた。
「母の墓は家の裏山の中にあるんです。草に覆われているので、夫に会社を休んでもらい、今日は草刈りです。もう終わった頃だと思いますので家を廻ってそれから墓に行って頂きます」
八重子は気さくに話しながら、慣れた手つきでハンドルをさばいていく。
「あそこが私の村です。というよりおじいちゃんの代々の土地で、おじいちゃんは、俺の死に場所だと言って動かないから、そのお守りで、私たちこんなところに住んでいるんです」
指された所は村はずれの、分厚い茅葺きの大きな家で、柱や障子はすすけている。明治時代を象徴しているような、しかも大変落ち着きを感ずる場所だった。家の横に柿の大木があって、広い緑葉が今を盛りと萌えあがって家の片隅を覆っていた。そのせいか庭土がじめじめとして、いかにも田舎然とした風景だった。
「お母さんはここに住んでいたんですか」
「そうなんです。姑が亡くなり、義兄夫婦が海外旅行で事故死してから、舅が許してくれて、私と一緒に住めるようになったの。母は大変喜んで、これでもう思い残すことはないと言い、死んだらお父ちゃんの所へ行ける、などと、まるでそれを楽しみにしているような日々でしたわ。この古風な家がとても気に入ってました」
「落着ける村なんですよね。僕なんかもこういうところで住めたらな、と今考えたところです」