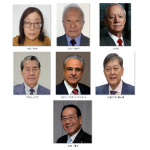「どうにか生きているわ」
「どうにか生きているわ」
「主人を亡くしてから、何とかいう宗教に凝り、教祖の鞄持ちでアマゾン河畔まで彷徨したって、本当かい?」
「勧められるまま入信してみたけど、それでも、私の心は救われなかった」
「インチキ宗教じゃないんか」
「そう極端なこと言わないでよ」
「だけどさ、短歌作っていた方が、まだ君らしかったぜ」
「どちらも私のうらぶれた心を救ってはくれなかったわ。でも、くしゃくしゃする時、仏壇に向かって合掌すると気持ちが安らぐわね。そこには主人も娘もいるから……」
「そういうもんかな」
「そうよ。女って、そういうものなのよ」
「やっぱり、それが女の弱さかね」
「ときに吉本さん、その後、奥さんとは元の鞘に納まったの? それとも別な女性?」
「冷やかしなさんな。この年で再婚でもあるまい。こうして仲間と飲みながら世間話でもしている方が天下泰平だよ」
「それで暮らしていければ、ね」
「で、お前さんはどうなんだい」
「私だって求婚してくれた人はいたわ……」
「どうしたんだい」
「亡くなった主人や娘のことを想い出して、何だか求婚者がいやらしく感じられたりしてね。女って駄目なのね。思い切らなきゃ再婚ってできないものね。こんなこと、中嶋さんに言うのは早いけど、いい縁があったらパッと再婚することよ。その点、吉本さんも私も意気地なしなんだわ」
言いながら、朋子は外した近眼鏡をハンカチで拭ったり、何となく落ち着かぬ動作をしている。白く、滑らかそうな皮膚。そして、その顔立ちは未だ若さがあり、よく整っていた。彼女もまた満たされぬものを抱えている一人なのだ。
「中嶋、聞いたか」
「うん、面白いな」
妻貴美の病臥以来続いた重苦しい日々、見舞い客の接待、病院通い、生計を支えるための稼業などからくる心労で、私はすっかり体調を崩していた。極度の神経質になり、沈静剤を飲まないと夜も眠れず、娘やお手伝いたちに当り散らすことが多かった。そういう状態から脱しきれずにいた自分に吉本と朋子の気がおけない会話は、一服の清涼剤に似て私の心を和ませてくれるのだった。
「今日は後家とやもめの懇親会だな。愉快だ。大いに飲もう。中嶋、もっと辛口のがあるかい」