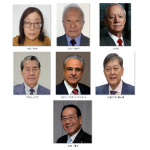その日田守は、終日、悶々として仕事も手につかなかった。夕刻、再び家に帰る気がしなかった。ふと思いついて、同僚の日浦良夫を訪ねることにした。パトロンの篠崎と同じくらい彼も縁談を勧め、結婚を喜んでくれた男であった。
「オイ、今夜《青柳》に行こうじゃないか」
田守は出し抜けに言った。
「しばらく見えなかったが、その後うまくやってるんじゃないか」
「もう愚痴をこぼすのもあほらしい。俺には女難が付きまとっている」
「そんなこと言って、《青柳》なぞに行くと、また女難だぞ」
《青柳》というのは、サンパウロ屈指の料亭であった。常時、五〇名ちかい女給を抱えて、バタタ(馬鈴薯)成金、コーヒー成金、棉花成金どもが夜ごと高級車を乗り付けては、豪遊・散財に溺れていた。後に共産村創設者として知られた馬場勇など、取り引き銀行が傾くほどの金を動かして、浪費を重ねていたという、日系社会の浮沈を左右してきた不夜城だった。
「田守と、ちょっと外出してくる」
日浦は、女房にそう言い残して、田守と家をでた。日浦はその方面によく通じた男だった。
黒松やつつじを築山に植え込んだ、見せ掛けの日本庭園に沿って、数十メートル下りたところに和風造りの家屋が見えた。近づくと、障子越しに三味の音が聞こえていた。
「つやちゃんいるかい」
田守がなじみの女の名を呼ぶと、申し合わせたようにつや子が出てきた。髪の毛を後ろにカールして、襟首の白い四〇代の肉感的な女で、この日は黒いスーツに身を包んでいた。
「まあ、珍しいこと。何年ぶりなの」
彼女は田守に近づいて頬を寄せた。田守も内心は、彼女と逢えるのを期待していたのだ。
「俺にはキッスしてくれないのか」
日浦が横から彼女の手を握る。
「貴方は珍しい客じゃないもの。田守さん珍客なんだから」
とわざとしらけて見せる。
「結婚生活うまく行っているの」
「それが破滅なんだ。つまらん女だったと後悔している。最初、つや子を知った時、プロポーズすればよかったな。だけど、つや子はこんなところへくるもんじゃないよ、などと妙な教訓めいたことを言ったりして」