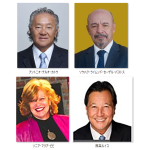「だって、ここで幼馴染に出会えば、そう言う以外に私たちの立つ瀬がないじゃないの」
「だって、ここで幼馴染に出会えば、そう言う以外に私たちの立つ瀬がないじゃないの」
田守の幼時に住んでいたルビアッサという町で、つや子の父親が床屋を営んでいた。田守が母に連れられて散髪に行くと、つや子は、可愛い合いの子だと頭を撫でてくれた。その頃、つや子は十四、五歳だったろうか、父親に弁当をもってきては、同じく散髪に集まっていた植民地の青年たちと賑やかに話していた。その後、サンパウロ市へ移ったと聞いた。田守にはそんな昔を思い出す気持ちの余裕もなかったが、日浦から誘われてきたこの料亭で彼女と再会したのである。その後、再三出逢ってねんごろになったが、結婚と同時に遠ざかってしまった。
「あんたは混血児だからこの国の娘さんと一緒になって当然だし、うまく行っていい筈なのにね」
「混血だから、俺の半分は日本人なんだ。あらゆるもので日本人的なものに惹かれている。つや子と仲良くなれたのもその現れだと思うよ」
「体躯もいいし、政界にでも打って出ると当選間違いなしよ。駄目な奥さんなら捨てて出直しなさいよ。そうでしょう日浦さん」
「全くだ、そうすべきだ。今日のつや子の言葉は気に入った」
そこへビールが運ばれてきた。その娘をまじえて四人は乾杯をした。
「浮世カルタの浮き沈みって言うけど、世の中って色々なことがあるわね。田守さんみたいな真面目な人に奥さんが尽くせないなんて……」
「いや、俺の心には女を可愛がれない悪魔が棲みついているんだろう」
「いいえ、結婚前には、わたし随分可愛がってもらったけど」
「あれは俺の仮面だったんだろうな」
「インテリさんはうまいことを言うから、どこがどうなっているの解りゃしない」
四人はしたたかに飲んだ。日浦は田守の心の荒びを察してか、つや子との会話は避けて別の女とぶつぶつ何か囁いていた。
看板になって田守はつや子を送ってゆくことにし、日浦は途中で降りた。
「うちに寄って行く? 私、最近日本間を作って畳の上の布団で寝てるのよ。子供の時に日本から来たんだけど日本的な雰囲気が気に入ってるの。こう見えてもお茶の作法に通ったりしてるのよ」
「つや子のそういう性格が昔から好きだったけど、結婚するとは言わなかったものな」
「料亭の姉さん女房なんてことになると、若い貴方が可哀想だもの……」