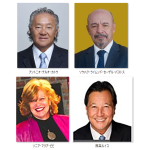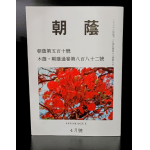ダニエルは田守に分厚い封筒を渡した。
ダニエルは田守に分厚い封筒を渡した。
ジョージ様
お前の生い立ちがあまりに悲しいことだったので、ずっと真相を話してあげることができなかった。だが、お前が一人前になった時は全てを打ち明けて納得してもらいたいと考えていたのよ。だけど、あの日、あれだけではお前に理解できなかったろうし、お前は家を飛び出してしまったので、私が伝えたかったことはこの胸の中に一杯詰まっている。それを話さないと死ぬにも死にきれない気持ちなので、この手紙を書いておきます。
小学生の頃、日本語学校に通ったのだから、これぐらいのことは読めるでしょう。私の父(お前のおじいちゃん)は田村幾也といったの。母(お前のおばあちゃん)は早苗といい、美人だった。
父は軍人で、その人事関係における依怙贔屓が嫌いだと言い、嫌がる母を説き伏せて三人でブラジルに移って来たの。アリアンサという日本人の集団地に入植したのが一九三×年だった。私は十四歳になっていた。農業に経験のない私たちに原始林の開拓は過酷すぎた。それは猛牛に立ち向かう蟷螂の斧ように、歯の立たない重労働だった。
開墾、耕作すべてが現地人を頼っての作業となった。パトロンが農耕作に無知では支配、監督が充分に行き届かず、効果が上がらない。その理由は日雇の怠慢だとして、父は毎日機嫌が悪い。気位だけ高くて、言葉を自由に操れない父を現地の人たちは尊敬するどころか、馬鹿にして嘲笑った。
こうした侮辱を毎日聞かされていた私は、いたたまれず父を手伝って畑にでた。日本からの航海中に少しブラジル語を習っていたので、少々の受け応えや指図ができた。
私が畑にでて、日雇人を相手に一人前の仕事ができるようになったのを父は非常に喜んだ。入植二年目の収穫が終えてから、農事の一切を私に任せた。父自身はその頃、設計を進めていたチエテ河の架橋工事事務所に勤めるようになったの。
私は日雇人を相手に四アルケーレス(一アルケールは二万四千二百平方メートル)の土地を耕作した。ジューリオというスペイン系の農業に詳しい男がいて、従順に働いたので私はその日雇人を信頼し、何彼と相談するようになっていた。私のそうした行為を愛情とでも感じたのか、彼は好意以上の動作を見せるようになった。私はそ知らぬ顔で振るまっていたが、ある日、作物の豆を物置小屋に運んだ時、ジューリオは、
「俺は八重が好きなんだ。本当に好きなんだ」