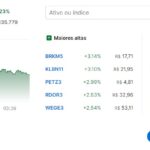と言い、私の両肩に手をかけた。私は無視し、急いでその場を逃れようとしたが、辺りに誰もいないことを知ると、後ろから抱きつき押し伏せられた。私は驚いて声もでなかった。必死で抵抗 したが、どうにもならなかった。信頼していた男からこういう屈辱を受けるなんて考えられないことだった。私は何も知らない、うぶな娘だったの。言い逃れの言葉一つ出せず、ただ抵抗して相手の情欲をそそったようなものだから……
と言い、私の両肩に手をかけた。私は無視し、急いでその場を逃れようとしたが、辺りに誰もいないことを知ると、後ろから抱きつき押し伏せられた。私は驚いて声もでなかった。必死で抵抗 したが、どうにもならなかった。信頼していた男からこういう屈辱を受けるなんて考えられないことだった。私は何も知らない、うぶな娘だったの。言い逃れの言葉一つ出せず、ただ抵抗して相手の情欲をそそったようなものだから……
私はこの事実を父母に打ち明けて彼を解雇したくても、その勇気がなかった。信頼している男を理由も告げず辞めさせることはできない。そのうちに、私は妊娠していることが解った。これ程の皮肉があるだろうか。誰にこのことを打ち明けたらいいのだろう。厳格な父がそんなことを知ったら、激怒して、私を痛罵することだろう。私は死のうと考えた。家には殺蟻用の農薬があった。それを水に溶かして飲むと、死に致ると聞いたことがある。
ある植民地で、恋をして男に捨てられ、死んだ娘さんがいた。自業自得ではあったが、子供まで道づれにしなくとも、生きる方法があったろうにと批判された。こういう話と思い合わせると、死ぬことだけが美しいのではない。私の場合は他人から辱められた。死にたいと考える一方でそんな声が聞こえた。子供一人を育てるくらいの甲斐性はもっている。傷めつけられた女として敗れてはいけない。立派に生きて思い知らせてやるべきだ。私はそう決心すると黙って家をでた。その時はどうしても言えないこの事実も、いつの日か打ち明けて、許される日もあるだろう、と一人決めにしていた。
後で知ったところでは、父は激怒のあまり、飲めない酒を呷っては、母に娘の躾が悪かったのだと、日夜責め立てたそうです。ジューリオも遁走したことを知ると、父は狂乱となり、二人を撃ち殺すのだと息巻いていたとも聞きました。そして終には、自分が家族を率いてこの国に移住したことが、悲劇の初まりだったと母に言い残して、その夜、独り裏山に分け入り、割腹して果てました。苦悶の跡は無残で、辺りの草が鮮血に染まり、短刀を包んだ白紙に《無念》と記してありました。
よく行商にくるその男から、父の最期を聞かされ、私はその場を何とか取り繕った。が、後に、死ぬより辛い思いにさい悩まされたわ。あの時、私がお前と一緒に死んでいれば、父は不憫な娘として許してくれたかもしれなかった。いつの日か、親子が仲睦まじく暮らせるだろうと楽観していた私は、何たる愚か者だったのでしょう。世間に恥を忍んで生き、お前と二人の将来を夢見ていた私の独断が、父をして、あの最後を選ばせたのでした。