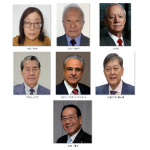「クヤバ方面だ」
「クヤバ方面だ」
「ちょうどいい、お願いだ。これから五〇キロほど先のターヴォラ耕地まで行くところだが、見てのとおり、カミニョネッテ(小型トラック)が故障しやがって……」
「よかろう、乗りたまえ」
田守は言った。
「俺の車の中に、少し運びたい荷物があるんで、お宅の車のトランクを開けて欲しい」
黒人の車中にいた他の二人の男が、釣道具か鉄砲のような包を抱えてきた。男たちはそれを田守の車のトランクに収めると、さらに重そうな二箱も積み込んだ。黒人が助手席に入り、他の二人は後部座席に座った。
国道を小一時間走った地点で右折して降り、郡道に入り、もう一度右に曲がった。
「俺の名前はジョンという。よろしく。で、そちらは何かの販売員……?」
ジョンは訊いた。
「いや、奥地で、何処かのんびり暮らせる場所を探してる」
「失恋でも?」
「捨ててきたんだ」
「ほう、それで別の女性と」
「いや、女はもう沢山だ」
「俺もそうだ。女はなくてはいられない。かと言って、居るとうるさい」
ジョンは笑った。後部座席の二人も笑っている。田守の緊張はほぐれた。その時、前方に大きな黒い板の門が見えてきた。立ち入り禁止の札がかかっている。
「行けないじゃないか」
「ここでいいんだ。この道の右側がターヴォラ耕地だ。左側はアギアル耕地なんだが、右よりの小川まで自分の耕地だと言い張って通せんぼしているんだ。もう十年近くも続いている境界争いで、両耕地の使用人が毎年殺されている。こういう争いは世のためにならない」
黒人はそれまで言って話をやめた。二人の男に荷を降ろさせ、ゆっくり煙草に火をつけた。
「ターヴォラ耕地の特殊用心棒にと頼まれて、やってきたところだ。どうだね田守氏よ、ひとつ仲間入りして、その腕を貸してはもらえまいか」
「面白そうだが、俺の専門ではない」
「仲間になれるだろうと思って経緯を話したんだが、嫌だと言うなら俺たちも考えねばならない」
「……」
―― 車に乗せた時点から疑ってはいたが、トランクの荷物は銃器に違いない。ここで余計な質問や助言などをするより、彼らが如何なる冒険をするのか、それを見届けるのも面白そうだ。相手を知るためにはその懐に入り込む要があるだろう ―─