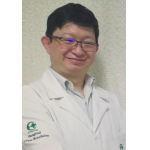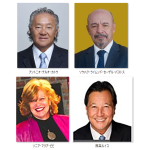「よし、そうこなければ」
彼らは分担して荷を担いだ。二〇分歩いてターヴォラ耕地の事務所らしい、闇の中に白く浮いている建物の前へきた。自家発電の鈍い光の電灯が庭の樹々を照らしていた。
(七)
聞くところでは、ターヴォラ耕地は四百五〇アルケーレスの面積をもち、カカオ、コーヒー、パパイアなどの栽培を主とし、他に牧畜も手広く経営していた。
耕主ターヴォラは、ポルトガルから派遣されたバンデイランテス(新大陸探検隊員)と、原住民の娘との混血の子孫とかで、かなり悪辣な手段で土地を増やしていた。表面は紳士を装っていたので、ジョンたちは彼の計画を信じていた。
事務所の外からジョンが声をかけると、
「おう!」
と返事があって、内側から戸が開いた。濃い髯で顔全体を埋めたターヴォラが葉巻をくわえて立っていた。二人は肩を叩き合って挨拶した。
「仲間です」とそばの三人を紹介した。
「よろしい。それではこの前話したとおりだよ。向かって左側からアギアル耕地を襲撃する。左三軒は椰子葺きの家だから、近づいて火炎瓶を投げ込む。敵は右側へ逃れようとする筈だ。そいつらを狙い撃ちにしろ。正面には耕地の男五人を配置する。アギアルの住宅は煉瓦造りだから最後に残していい。右側からは、俺と手下が待ち伏せる。最後まで抵抗するのはアギアルに決まっている。これを左右から滅多撃ちにするのだ。
いいか、全滅させた後、お前らはこの場から姿を消せ。加勢を得て襲撃したと知れてはまずい。俺はアギアル耕地からの襲撃で、正当防衛として訴える。死人に口なしだ。善後処置は、俺が引き受ける。万一、お前らが捕まってもターヴォラ耕地に加担したとは、絶対に言うな。それでは、午前一時の決行だ。ジョン、お前が口火を切るんだぞ。これは約束どおりの報酬と口止め料だ」
ターヴォラは札束を、ジョンに渡した。
「さあ行こう。弾箱は一人ずつ担げ。田守も一挺使ってくれ。カラビーナ(カービン銃)だ、撃てるだろう」
田守は頷いた。が、猟銃捌きに豊富な経験はあっても、人殺しに銃を握ったことはない。
「相手は五家族とアギアル兄弟の七家族だ。せいぜい三〇人ぐらいだろう。抵抗できるのは十数人だ。田守は後方から見守っていてくれ」