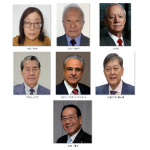「相手が富豪の娘だったんだ。美しい娘とは思いつつあまり関心を持つこともなかったんだ。身分が違いすぎるからな。けど、タニアは夢中になって、何かと口実を設けて俺の試合を観にくる。試合が終わると、コーヒーを飲んだり、夕食を一緒にしたりする交際だったが、そのうちにタニアは俺とデートするようになった。俺は女に困っているわけでないから、身体を許さないタニアとの交際は面白くない。彼女は、結婚前には一緒に寝るようなことはできないと言う。俺は、そんなデートなんか止めてしまおう。それがタニアの身のためだと諭したが、そう言えばなおさら、
「相手が富豪の娘だったんだ。美しい娘とは思いつつあまり関心を持つこともなかったんだ。身分が違いすぎるからな。けど、タニアは夢中になって、何かと口実を設けて俺の試合を観にくる。試合が終わると、コーヒーを飲んだり、夕食を一緒にしたりする交際だったが、そのうちにタニアは俺とデートするようになった。俺は女に困っているわけでないから、身体を許さないタニアとの交際は面白くない。彼女は、結婚前には一緒に寝るようなことはできないと言う。俺は、そんなデートなんか止めてしまおう。それがタニアの身のためだと諭したが、そう言えばなおさら、
「ジョンには他にたくさんの娘がいるからでしょう。知ってるわ。でもその人たちに負けたくない。ジョンを取られたくないの」
と泣きながら身を投げ出してくるんだ。逃げるわけにはいかない。俺は義務を負わされた思いで、あるとき一緒に寝たんだ。その後からは、よくホテルにいった。しだいに情が移って、別れられなくなった。今までの女の中で一番いいと思うようになっていた。
タニアは、両親の前で求婚してくれと言うので、俺はジュアレースを通じて申し込んだ。が、親の返事は、否だった。俺は最後の切り札として、タニアはもう生娘でないということを匂わせたんだ。すると父親は、『そんなでたらめをよく言えたものだ。私の娘が、お前みたいな男と寝たなどと断じて信じぬ。娘の友人のイザウラに聞いてみろ!』と、烈火 の如く怒って、俺たちを追い出した。ジュアレースは俺の心を察してタニアを連れて逃げろと入れ知恵してくれた。しかし、タニアは家の中に監禁されて、逢う機会がなくなったんだ。その上、フットボール・クラブから俺を除名しやがった。それからの俺はもうめちゃくちゃだ」
「ジョンは、才能のある屑でね」
ジュアレースは言った。
「昨夜のことを忘れて、こんな話ができるなんて、お前たちの神経もたいしたものだ。さあ、旅を続
けるとするか」
三人は、ふらつきながらレストランをでた。ハンドルを握る田守をおいて、他の二人は車に入るなり、深い眠りに落ちていった。田守も眠たかったが、ハンドルさばきは確かなものだ。夜通し走り続け、東方の空が白んできた頃、ジョンが眼を覚ました。じっと辺りを眺めていたが、
「この国道を左に折れて二〇キロほど行くと、以前、俺たちがダイヤモンド掘りをやった低地に着く。どうだ、田守は行く宛てもないと言っていたが、あそこに行かないか。俺たちの作った山小屋もある筈だ」