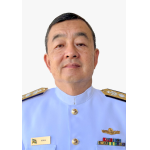「俺は無能者だけどな、ジョンよりは正直だし、処世術は田守にも負けない。車を貸すなと助言したのも当たってるだろう」
「俺は無能者だけどな、ジョンよりは正直だし、処世術は田守にも負けない。車を貸すなと助言したのも当たってるだろう」
「その通りだ。俺は母親も女房も捨てた。だけど己に忠実だった。今後もそうだ。模範的なものは何もないが、美しい人生だと思っている」
「田守は聖人だ。けど俺は ……」
「おべんちゃらなぞ言わずに、町に行きたかったら行くがいい。上等なピンガを下げて帰るのを待っているとしよう」
結局、ジュアレースも戻らなかった。田守にとっては、不可解な野郎どもが消えたので、すっきりとした。こんな辺涯の地に隠棲する自分も、粗野な人間に違いないが、未だあの連中よりはましじゃないか。俺は家庭のいざこざ、利害のかけ引き、毀誉褒貶、心にもないお世辞、政治の矛盾、それら諸もろが嫌になって人里を離れた。この地は俺にとって安息地なのだ。途中で妙な事件に巻き込まれたものの、とにかくここまで辿り着けたことは、僥倖と言っていい。
田守は、独りになった一夜が明けると、小川に下りた。水流は誰に引き留められ急かされることもなく、自然の姿で流れていた。田守自身も一茎の草となった心境で、傍らの岩に腰を下ろした。 男たちの置き去った縄煙草をナイフできざみ、それを唐黍の薄皮で巻いて咥えた。マッチの軸が燃え尽きるまで丹念に火をつける。ゆっくりと、吸い込み、煙を吐く。満たされた表情で、田守は辺りの風景に眼をやった。
葉の散った篠竹のような灌木が、川向こうに透かし彫りで林立していた。農業に従事する少年の田守が見かけた低木と同じものだ。春になると房状の白い花が咲く筈だ。栗の花に似て、野一面をさながら雪景色に変える。蜂どもが花に集う。花にとまる虫を狙って小鳥が飛んでくる。蜜蜂の往来も精力的になり、やがて花をめぐって厳しい生存競争がはじまろうとしている。
熱帯なりの四季の変化は巡っているのだ。一雨くれば、この森は見違えるような明るい緑に萌えはじめる。こうした自然界の移り変わりに感動し、感興を覚えるのは、老いの証なのか。
永い時間を生きてきたとも感ずるし、また一瞬のようでもある。その喜怒哀楽を反芻してみて、今の自分の居場所は、新天地であると思う。そこには命令もなければ、責任もない。己の仙境に浴していられる。月に一粒の、いや、一年に一個の《石》の収穫でも、質素な生活の俺には充分だ。日ごと繰り返す砂利掬いは、身体の運動になるし、端的な人生を満喫しているようで、きわめて健康的だ。