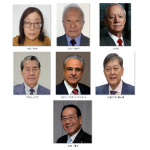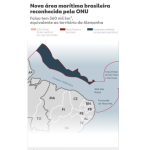「信二さ~ん」
「信二さ~ん」
と、戸外で少女の声がした。さ~ん、とアクセントをつけて呼ぶのは、三軒隣に住む、幼馴染みの寺田良子だ。信二は雑誌を放り出し跳ね起きた。カンテラを窓に突き出すと、左の肩に籾袋を背負った良子が、泣き出しそうな顔で立っていた。
「秋ちゃんいる?」
信二の妹である。秋子に用事なのに、何故信二を呼ぶのか、信二には良子の心が読めている。
「秋子は今、風呂だよ」
「あらそう。私、今バッタンに籾の入れ替えに行くんだけど、独りじゃ恐いの……」
「……ん、そうか」
「夕方入れ替えるのが遅れちゃって。籾は搗き過ぎると小米に割れてしまうとお母ちゃんは言うけど、兄ちゃんは都合が悪いし……」
良子はかなりしょげて、痛々しい。
「じゃ、俺がついて行ってやるよ」
多少恩にきせた言い方だが、本心は良子について行きたかったのだ。秋子は風呂だから、俺が代わりについて行っても家族の者は咎めないだろう。思春期に達した信二は勝手なことを考えた。荷の重みで前かがみになった良子の歩調は乱れていた。信二は直ぐに籾荷を肩代わりしてやった。持ち替えの時に触れた良子の手は冷たかった。
背丈以上にも伸びて、呆けた茅草を分け広げながら進む水車小屋までの道のりは陰惨だ。
「こんな夜道を、女の子一人でバッタンに行かせるなんて、ひどいと思わない」
「良子ちゃんを、強い娘に鍛える訓練かもな」
「無茶だわ」
良子の声は湿っぽく、少し震えて聞こえた。信二には良子の気持ちが解らなくもなかったが、一緒に歩くことを楽しみたかった。
「この間の日曜日だったな、僕この川岸を通ったら、良子ちゃんと秋子がいたよ」「二人で洗濯してたんだわ」
洗濯に違いなかったが、岸の草の上に洗濯物を広げたまま、二人は裸になって水を浴びていたのだ。水泳の稽古らしかった。うまく行かないと互いに水を掛け合ったり、突き倒したり、かかっと笑いながら日光と水に戯れていた。良子の乳首が杏の実のように可愛く膨らんでいるのを信二は見た。そのことを話そうかと思ったが、へたに彼女の心を傷つけてはと思い、黙っていた。
単調なバッタンの音が近づいてきた。闇をかき混ぜる不気味な音に聞こえる。時期はずれの蛍が飛んでいた。
「今頃でも蛍がいるんだな」