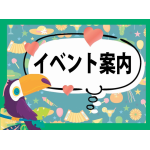「ブラジルと日本、地球の反対側同士を行き来する2つのディアスポラによって刻まれた歴史の断片を“金継ぎ”のように糊付けする」――茶屋道イナラ監督(ちゃやみち・39歳・4世)のドキュメンタリー映画「Onde as Ondas Quebram」(波が砕けたところ、2023年)が22日午後3時、第10回サントスフィルムフェスティバルで上映される。19日、イラナ監督に単独オンラインインタビューを行った。

同作は、波の映像と祖先を想うイラナ監督の父キヨシさん(3世)の語りから始まる。ブラジル生まれの祖母ミチコさん(2世、88歳)や、日本へ30年デカセギに行っている叔父、日本で育ちブラジルをほぼ知らない従妹を訪ねる中でイラナ監督自身のアイデンティティを探求していく。鹿児島県に出向き、日本人の親戚を探す場面が感動的な作品だ。
制作のきっかけは2020年、イラナ監督がオランダに移住し、文化や社会の仕組みの違いに困惑したところにある。イラナ監督の曾祖父母は1932年にブラジルに移住した。自身の苦労と曾祖父母ら移住者の姿が重なり、「ネットも何もない時代に日本からブラジルに移住した人たちはどうやって生活していたの?!」と衝撃を覚えた。当時の人々がいかにして困難を乗り越え、そして今の自分の存在に繋がっているのかを映像に残すことを決めたという。
「ばっちゃん(ミチコさん)はカメラの前で次第に自分の話をしてくれるようになりました。ばっちゃんとの信頼関係が強まっていくのを感じました」と続け「ばっちゃんは6歳の時のことを今でも鮮明に覚えていました。それほどトラウマ的な体験だったんだと思います」

その体験とは「サントス強制退去事件」のことだった。第二次世界大戦中、サントス市在住だった茶屋道一家は、ブラジル政府の命令により、市内からの強制退去を余儀なくされた。ミチコさんは、知らない土地で服も寝る場所も食べ物もない生活を強いられたという。
制作にあたって、サントス強制退去事件に関する調べを進める内、これまで知られていなかった新聞資料などを発見し、図らずも同事件の研究に貢献することにもなった。
自身のルーツを辿る手がかりの一つに名字がある。茶屋道(ちゃやみち)という名字は、ブラジルでも日本でも珍しい。19歳の時、大学の休みを利用して3カ月、日本のパナソニックの携帯電話工場にアルバイトに行ったが、工場の担当者は「イナラ」を名字、名前を「さやみ(茶屋道)」と勘違い。判子が必要になると、「イナラ」も「茶屋道」も無いので、担当者はイナラ監督の祖母の旧姓「タケナカ」の判子を用意した。しかし、判子の文字をよく見ると「タカナカ」となっており、「茶屋道」という名字には苦労させられていると笑う。

そんな珍しい「茶屋道」という名字だが、日本での親戚探しで鹿児島県枕崎市を訪ねると、枕崎市には同じ苗字の茶屋道さんが溢れていた。「生きていて初めて茶屋道が通じる!」と大きな喜びを感じたという。
イナラ監督はサンパウロ州リベイロン・プレットで生まれ育った。母親は非日系人で、日系社会に関わることなく生きてきた。
「父は7歳まで家庭内でポルトガル語の使用を禁止されていたそうなので、対照的な育ち方をしたと思います。生後8カ月の娘はポルトガル生まれです。移民の歴史はどんどんと複雑化していきますが、歴史を語り継ぐことは自分を知る為にも社会で生きていくにも大事なことなので、語り継いでいきたいです」と笑顔で語る。
同作はこれまでに、オレゴン・ディスオリエント・アジアン・アメリカン映画祭、第47回公式パラレルセレクション映画祭2024、第10回サントス映画祭全国コンペティションショーにノミネートされている。
昨年6月に行われたブラジル日本福祉文化協会主催の文化祭りでも上映された。
イラナ監督は、ロンドリーナ連邦大学ジャーナリズム学科を卒業後、TVグローボ、フォーリャ・デ・サンパウロなどで多くの作品制作に携わった。現在は、自身のプロダクションを立ち上げ、ポルトガルの大学院で映像分野の研究を行っている。
サントスフィルムフェスティバルは、SESCサントス(R. Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida, Santos – SP)で開催され、同作の上映券は上映1時間前に無料で配布される。