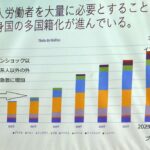日本でも引けを取らない大正小学校の授業内容
「大正小学校の教育が優秀だったから、日本で学校にいっても自分の学力不足にはまったく困りませんでした。ただし、日本の地理や歴史をやっていなかったので、とても困りました」―川村真倫子さん(96歳、2世)は昨年末12月3日朝、アクリマソン区の自宅アパートで取材に応じてくれた。
今年は日系社会初の政府公認私立校「大正小学校」開校110周年であり、それを記念した日本語教育イベントが1月末から企画されている。大正小学校は1915年に最初の日本人街であるサンパウロ市セントロ区のコンデ・デ・サルゼダス街38番に宮崎信造が開校した。彼は笠戸丸以前の1907年に、料理人として内田定槌ブラジル公使に同航した変わり種だ。だが宮崎は9年余りで病没した。
同校は有資格の伯人女性教師を雇ってポ語教育を始めて私立校として公認され、1929年に総領事館や父兄らの協力でサンジョアキン街に移転した。長野師範を卒業した柳沢秋雄、坂田忠夫、二木秀人ら教師が派遣され、ブラジルの教育大学で教師資格を取得させた上で、大正小学校で教鞭をとらせた。だから日本の小学校の卒業資格が取れた。
1930年代後半には生徒数は200人を超え、ピニェイロスに分校まで開設した。これが現在アリアンサ会館がある場所だ。このように拡大する中で、同校は戦前の日系子弟教育の中心的機関となっていった。
戦争中もブラジル国籍の二世を校長にしてコレジオ・ピラチニンガと改名して授業を続け、1966年まで続いた。その土地は、現在ブラジル日本文化福祉協会となっており、当ブラジル日報協会もそこに入居している。多くの生徒は大正小学校で半日授業を受け、サンジョアキン街を少し上って左側にあった公立校カンポス・サーレス(現在は建設中の間部学美術館)でもブラジル教育を受け、日伯双方の卒業資格を取得した。
卒業生には、1954年に日系初の連邦下議になった田村幸重、やはり連邦下議として長年日系社会を支えた野村丈吾、ジャーナリストの山城ジョゼ、中央銀行理事の横田パウロら錚々たるメンバーがいる。
戦前の大正小学校卒業生の数少ない生存者である川村真倫子さんに貴重な人生の道程を振り返ってもらった。
大正小学校とサーレス校で日伯双方の卒業資格

1928年、三重県出身の両親が渡伯した直後、真倫子さんは9月3日にサンパウロ州ボツカツで生まれ、二重国籍を持つ。父・川村清作さんは郷里でも米問屋を営み、当地でも商店を経営して、家族は裕福な生活を送っていた。大正小学校の学費は当時の普通の移民には高額なものであり、駐在員や領事以外で、日系社会の子弟で大正小学校に学んだものはそれほど多くなかったはずだ。
大正小学校に6歳で1934年に入学し、6年間そこで勉強した。卒業後、1941年3月、まだ12歳だった真倫子さんは母と共に訪日した。「日本語をもっとしっかり覚えろという父の命令で、日本の小学校6年生の1年間をもう一度やってこいと言われて日本に行きました」。
今回のインタビューで本人は1939年訪日と言っていたが、2009年に取材した際は「1941年3月に訪日して、1951年に帰伯した」と明言していた。当時のパスポートなどがなく確認のしようがないが、15年前の方が記憶は鮮明だったはずだとの判断から、本稿では41年訪日を採用した。
大正小学校の校舎があったのは、今の文協の裏の方、体育館があるあたりではないかという。「校庭と言えないような小さな広場があって、よく遊んだりした。日本で師範学校を卒業して来られた先生たちだったから、日本語教育はとても強かった。私は二木先生の生徒です。あの頃の先生は非常に優しい先生ばかりでした」と懐かしそうに思い出す。
更に「大正小学校は国語中心で、日本の歴史や地理がなかったので、日本へ行ってからその部分では苦労しました。ただし、ブラジルの地理や歴史は公立小学校(グルッポ・エスコラール)カンポス・サーレス校で4年間学びました。3部制の学校で、大正小学校と両方いっぺんに通い、日伯双方の卒業資格を得ることができました。でも戦争が始まったので、卒業証書とか写真は何にもありません」と笑う。
大正小学校は「日本語や日本精神が中心で、他の教科は覚えがない」という。日本語の教科書『小学校国語読本』(旧文部省)を使い、毎日通い、2~3時間程度だったという。ブラジルの監督官が来ると「日本語の教科書を隠す。そんな中で一生懸命に日本の文化や精神を伝えてくれようとしていた」。「両角(もろづみ)貫一先生が校長先生、二木先生、イゼリ先生、小川先生、アキ先生」などの名前が次々に飛び出す。
「経済的に恵まれた生徒たちが通っていました。私は木綿の靴下を履いていましたが、みんなは絹の靴下を履いていたので、外で遊ぶ時に少し恥ずかしい思いをしました」とも。当時は領事や駐在員の子供と日系社会の生徒が同じ教室で学んでいた。いわば、日本人学校と現地日系校が一緒になったような状態だ。
「どっかの公園に遠足に行くのが楽しかった」と思い出す。歩いていったというので、おそらくアクリマソン公園だ。「父はとても愛国心が強い人で、まったくの日本人で、『必ず日本に帰るんだからブラジル化してはいけない』と家の中では必ず日本語をしゃべるように言われていました。大正小学校だけでは足りないからと、アキ先生や渋谷慎吾さんに日本語の個人授業も受けていました」
渋谷慎吾は東京帝大法科卒で、台湾総督府の官吏をした後、ブラジル移住した。戦後は赤間学院で歴史や地理を教えていた戦勝派の教師だ。
「授業はなにしろ楽しかった。宿題はあまり出なかったので、宿題で苦しんだ覚えはない。天長節もやっていたので、日本に行っても困らなかった。日本人を育てることが目的の学校だったので、私は日本人に育ちました」。今でいう日本人学校と一緒だ。
教室は多くなく、複数の学年が一つの教室で学んでいたので今でいう複式授業だった。「(大正小学校の野球チームに)カッコいいピッチャーがいて、家族でよく野球観戦にいった」と懐かしそうに思い出す。

空襲で防空壕の同級生が皆殺し、平和教育誓う
「1941年3月に訪日し、途中で父から『戦争が始まるかもしれない。危ないから早く帰れ』と連絡がありましたが、もう帰る船がなくなっていました」と振り返る。予定では同年12月に父と弟が訪日して、翌年3月に小学校6年生を修了した真倫子さんと母をブラジルに連れて帰る予定だった。だが戦前最後のブラジル移民船は1941年8月12日にサントス港着の第306回移民船「ぶえのすあいれす丸」となり、12月8日に真珠湾攻撃、太平洋戦争勃発となった。
笠戸丸からの33年間で約19万人の日本人がブラジルに渡っていた。大半の移民は「数年間コーヒー農園で働いてお金を貯めたら錦衣帰郷する」つもりでいたが、その夢は叶わなかった。真倫子さんのように勉強のために訪日させるような資金力のある親は、当時とても少なかった。
真倫子さんは両親の郷里である三重県川越市に住み、小学校6年、桑名高等女学校(今の中学校)で3年間、亀山師範学校で3年間学んだ。戦争中、桑名高等女学校時代に飛行機部品工場へ学徒動員させられた。桑名には友達が多く、B29の空爆が爆撃でその多くが死んでいった。
「空襲の時、学徒動員の工場のすぐそばに学徒のための大きな防空壕があり、そこに友達の多くが逃げ込みました。でもそこに逃げ込んだ友達は直撃を受けて全員死にました。私は何を思ったか、そこではなく遠くに走ったんです。他人の防空壕に飛び込んだら、そこは家族用の防空壕で『よそ者は出ていけ』と言われた。仕方なく別の防空壕に潜り込んで、今度も『出ていけ』と言われたが、聞こえないふりをしてやり過ごした」という辛い経験を思い出す。
空襲が終わった後、外に出てみたら、友人らが逃げた大きな防空壕も、次に逃げ込んだ家族用の防空壕も爆弾の直撃を受けていた。「その時の友達の死に方が、あまりにも無残でね…。一番、今でも瞼に残るのは、小さい女の子、1歳から2歳ぐらいの女の子だと思いますが、道端に斃れていたが、助ける気にもならなかった。私の心も荒れていて、見て見ぬふりをしていっちゃった…」と今も辛い記憶として脳裏に刻まれている。
「皆気持ちが荒れるんですよね。辛い思いをしたので、戦争なんかするんじゃないよと子供たちに教えているんです。今でも亡くなった人たちがチラチラと見えてくる」と、その辛さをテコに「教育で戦争のない世界を実現できないか」と思うようになった。
終戦直後、ブラジルに戻りたいという気持ちが強く、師範学校を出て早く帰伯して教師になろうと心に決めた。
戦争で家族がバラバラに、血判状で父説得

終戦直後、米国からプロテスタントの布教師がたくさん日本にきて、母が生活の苦しみの中でそれに入信した。彼らから「仏教はダメだ」と言われて、母が賛美歌を歌いながら海岸で先祖代々の仏壇を泣く泣く焼いた。そして父にその仏壇を焼いた顛末と「日本は戦争に負けた。ブラジルに帰りたい」と書いた手紙を送ったら、勝ち組だった父は烈火のごとく怒って「帰ってくるな」と頑として帰国旅費を送ってくれなかった。
何度手紙を書いても父はきいてくれないので、真倫子さんは指を少し切って流れ出た血で、再度許しを請う手紙を父に書くと、今度は許してくれた。血判状だ。「戦争前はあれだけ仲の良かった家族が、戦争でバラバラになってしまった。だから私は家族の大事さを痛感している。戦争は怖い」と繰り返す。
10年後の1951年にブラジルに戻った。最初は自宅で個人授業をたくさんこなして、少しずつ生徒を増やしていった。翌52年に自宅を日本語学校にする際、「母は、学校名は『日の出』とか優しい名前がいいよと言っていたけど、私は最後まで頑張る理想を持つという意味で『松柏』を選んだ」という。当時真倫子さんははまだ23歳。「松柏」は盆栽によく使われる常緑樹の松と真柏を合わせた言葉であり、かなり硬派な選択だった。
松柏学園の卒業生にはリオ連邦大学教授になった二宮ソニア、USP日本文化研究所所長を務めた鈴木妙、連邦下議になった飯星ワルテル、藤田エジムンド・ススム在韓国ブラジル大使、高級日本食レストラン「村上」オーナーシェフの村上強史など多彩な面々がいる。「教え子の数は数えたことがない。学校は生徒数ではない、精神を入れるところ。戦争で家族が死ななくてもいいようにするために」という方針だ。
松柏学園では戦後もずっと日本の教科書を使ってきた。「日本人の心を教えるのが私の教育。だから日本の教科書を使います」。日本語学校「松柏学園」が41年目を迎えた1993年、私立校「大志万学院」(Colegio Oshiman)を創立してステージを上げ、娘の真由実さんや斉藤永実さんらに経営を委ねるようになった。

「日本語に宿っている言霊を子供たちに伝える」
最近日本で起きている様々な事件に、真倫子さんは「最近はウソの日本人も多いけど、本当の日本人は真心を込めて他人を助ける」と心を痛めている。
大志万学院の生徒が訪日旅行で靖国神社や皇居、伊勢神宮参拝、広島平和記念資料館視察を欠かさず行うことに関し、「兵隊さんは国を護るために命を捧げたから靖国神社を参拝する。日本は天皇陛下がいらしてくれるからまとまっている。政府だけだとバラバラになってしまう。だから皇居参拝をする。生徒たちが伊勢神宮に行く前には、『古事記』『日本書紀』について予め勉強をする。そこに書かれた物語は本当かもしれない、そうでないかもしれないけど、その物語が日本人を作ってきたのは事実。神様たちがずっと昔から日本を守ってくれている。日本人というのは、いざとなると立派になる。グアーっと集まって日本を護る。それを私は自分の目で見ている」との信念を貫いている。
「消防団でも自衛隊でも日本は素晴らしい。東日本大震災の時もそうでしたね。それがずっと日本人の心の中に根付いている。どんな歴史が来ても無くさない立派さがある。それを子供たちに教えないといけない。ある程度は見せかけもあるかもしれないが、日本人の真の芯は立派だと思う。習慣や祖先を大事にしながら、何千年も日本を支えてきてくれた。今ちょっと崩れてますが、苦しくなるとシャキとします。地震とか起きれば、皆さん力を合わせるでしょ。その姿を子供たちに教えたい」
さらに「日本語教育は、ただの語学ではなく人間教育ですよ。日本語に宿っている言霊をいかに子供たちに伝えるか。それを子供に伝えると、泣きますよ。非日系の子供たちも同じ。人間ってそういうものじゃないですか。それが平和教育にもつながっていく」と強調する。
「日本の将来、日本人の心を信じています。だってこうやって大正小学校のことを思い出してくれていますから。カンポス・サーレス校なんて今時誰も思い出さないでしょう。日本人にはその気持ちがある。大正学校の先生方にもそれがあった。私が10年ぶりにブラジルに帰ってきて二木先生にご挨拶行くと『おお、マリちゃんか』って覚えていてくれる。そして私が最初に生徒がいなかったときに『ボクが教えていた生徒に教えてくれないか』と言って助けてくれた。それが本当の日本人ですね」と温かい思い出を振り返った。
最後に「今はただお迎えをまっているだけ」と現在の心境で締めくくった。(一部敬称略、深)