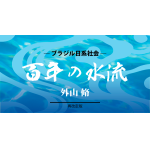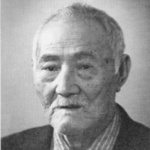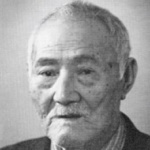一九三二年、健さんは組合に蔬菜部を設置しようとして、大混乱を引き起こす。組合員の中から激しい反対の声が上がったのである。
一九三二年、健さんは組合に蔬菜部を設置しようとして、大混乱を引き起こす。組合員の中から激しい反対の声が上がったのである。
モイーニョ・ヴェーリョでは、バタタ以外に蔬菜の生産者が増えていた。これを加入させようとしての事であるが、既存の組合員は「それが軌道に乗るまでの資金負担が、自分たちにかかってくる」と警戒したのだ。
健さんの独断専行的なやり方が反発を招いた点もあった。
反対を抑えきれず、非登録の別組合をつくって、蔬菜はそちらで扱うこととした。
一九三三年、健さんは、また大事件を引き起こした。元専務理事二人を、組合から除名しようとして、紛糾を招いたのである。
二人は、その役を退いてから営農資材商を営み、ピニェイロスのコチア産組本部の近くで営業していた。
これは、組合の購買部と競合する形になる。そこで「組合員としてあるまじき行為」として、総会の席上、除名することを健さんが提議した。
告発された二人の内の一人中尾熊喜は、肥料を販売していたが「自分は、すでにバタタの植付けをしておらず、定款により組合員の資格を失っている。支障はない筈」という認識を持っていた。
が、健さんは「植付けをしていない」という報告を組合は受けていないと逆襲、激論になった。
もう一人の元専務吉本亀は、種イモやバタタ用の袋を扱っていたが「自分は、しかるべき場で組合脱退を表明済み」と、やはり非組合員説を主張した。
二人の除名案は票決にかけられたが、否決されてしまう。すると、健さんと他の理事(二人)は、直ちに辞表を出した。
そこで定款にそって、前回の理事選挙で次点以下になった候補者を繰り上げて補充することになった。
ところが、繰り上がってきたのは吉本だったのである。が、当人はそれを受けなかった。次点の次点、そのまた次点の候補者も受けなかった。
そんな具合で、補充は出来なかった。止むを得ず日を改めて臨時総会を開き、健さんを含む前理事を再選した。
健さんは専務に復帰した。中尾・吉本の除名案は改めて承認された。
外部の人間には、何がなんだか判らなかったろう。
右の話の中に出てくる中尾熊喜は熊本県出身で、健さんと同じ一九一四年に、十四歳で渡伯した。独学で二十二歳の時、ポルトガル語の入門書を出版したというから大変な勉強家であったのだろう。もっとも彼の話すポ語は熊本弁だったという。無論、発音のことである。
青年会活動では、健さんと並ぶ頭株であり、組合創立時は専務理事を務めた。が、その後「専務をしていると、自分の仕事ができない」と退いていた。
クリスチャンであった。健さんとは肌合が違っていた。
中尾は、この除名事件の後、肥料工場をつくり成功、晩年は私財を投じて、日系社会のために尽した。
吉本亀は下元や中尾よりかなり年輩であった。中尾の後、専務を務めた。しかも前記した一九三一年の危機乗切りのための醵金もしている。健さんの恩人だったわけである。
この解任事件の直後、とんでもない事実が発覚した。健さんが一友人と共同で農産物商を設立、登記していることが判ったのだ。中尾たちと同じことである。当人は、その重要性に気づかず、別の理由で何げなく、それをしていたようだが…。
スッタモンダの挙句、結局、健さんが謝罪、事は収まった。どうも釈然としない落着の仕方だが、要は健さん以外に専務の引受け手がいなかったのだ。
こんな具合で、健さんは組合内部を統率するどころか、当人自身が統率を乱し続けていた。
前出の村上誠基の夫人が──ずっと後年──健さんの没後、組合の機関誌などを見ては「下元さんのことを、神様みたいに扱っているけど、昔は、そんなモンじゃありませんでしたヨ!」と憤慨していたという。
つまり、健さんは未熟だったのだ。
筆者は本稿の一章で書いた様に「人間誰しも長所と欠点を併せ持ち、成功したり失敗したりしながら生きている。表もあれば裏もある」という観点から、本稿の主要な登場人物については、その両面を敢えて描写している。無論、歴史をより正確に捕捉するためである。健さんの場合その欠点、失敗、裏面がこの組合創立から数年の間に、集中的に露出していた。この限りでは彼は失格であった。