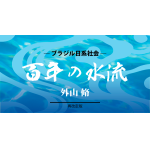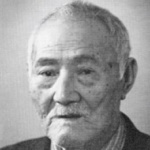付記しておけば「下元健吉という人は生涯、血気が溢れていたが、若い頃は溢れ過ぎていた」と語り継がれてもいる。
次の様な話もある。
時期は組合の草創期の頃であるが、一日、サンパウロの市街地を車で走行中、路面電車にぶつけ「何故よけんか!」と、車掌に殴りかかり、その無茶ぶりを目撃していた市民たちに袋叩きにされたというのである。
これは無論、伝説で、真相は前方を塞いで止まった電車に「道をあけろ!」と怒鳴り、隣にいた車の運転者から「電車は居るべき場所におる」とたしなめられ、返す言葉がなかった…という程度のものであった。
しかし路面電車に「道をあけろ!」と怒鳴ったというだけでも、溢れ過ぎる血の気を想像できる。
また、組合の従業員と口論し激昂の余り殴り合いになることすら間々あった。もっとも喧嘩が終ればケロッとしていた。
ただ、その血気を理解するためには、健さんに限らず戦前の日本人は今日の日本人とは、かなり違っていたことを知る必要がある。現に右の殴り合いは、相手が役員であろうと一歩も譲らぬ従業員がいたことを物語っている。
こうした風潮は、コチア産組に限らなかった。当時の邦字紙を捲ると「(ある地域の)日本人会の役員同士が乱闘」などという見出しが目につく。
総領事館で日系産組の育成を担当していた青木林蔵という技手が殴りあいをしたという記事も載っている。
青木が、総領事館の入り口で偶然出会った蔬菜生産者の某を、裏庭に連れて行き二、三発喰らわせ、某も傍に転がっていた煉瓦を掴んで逆襲、双方ともに怪我をした…というのが粗筋である。無論、それ以前に相応の経緯があったわけだが、これは別項で触れる。
日系社会の御三家の一つブラ拓の最高幹部、宮坂国人にすら同種の話があった。
前章で記した排日法で、誰もが緊張していた時期、総領事館を訪れ館員と会話中、意見が衝突して立回りとなり、小男の宮坂が大男の相手を組み敷いたという。
実は宮坂は学生時代、柔道や相撲の選手であった。
ついでながら宮坂はブラ拓の事務所で、職員数人と乱闘したこともある。彼らから歳末手当を「出せ」と要求され、出さぬと拒否しているうちに、口論となり取っ組み合いになった。
これは、それを目撃していた邦字紙の先輩記者から、ずっと後年、筆者が聞いた話である。「宮坂さんは強かった!」と、その記者は感嘆していた。
青木は当時三十代、宮坂は四十代。しかも、どちらも日系社会の指導者であり、宮坂などは、その筆頭であった。それが、こういう調子だったのである。従って一般の若い連中の間では、喧嘩沙汰など珍しくなかった。
往時の日本人は、そういう覇気、闘志の持ち主が多かった。
それと、時代も、血気を孕んだ風が吹いていた。その頃の邦字新聞を見ると、祖国日本関係の記事では、一九二八(昭3)年の張作林爆殺事件、三一年の満州事変、三二年の血盟団事件、満州国建国、五・一五事件、三三年の国際連盟脱退、三六年の二・二六事件などが目につく。
ブラジル国内でも、一九二〇年代は国内のアチコチで軍の若手士官たちが火つけ役となった騒動が相次ぎ、さらに一九三〇年ゼッツリオ・ヴァルガス革命、三二年サンパウロ州の反乱…と続いていた。
ヨーロッパでは三三年、ドイツでヒットラーが政権を握り、虎視眈々、前大戦の報復を期していた。
こういう風が、その時代を生きる人々を猛々しくしていたのである。
七年目の転機
健さんが、大ポカ連発から脱するのは、組合の創立七年目の一九三四年のことである。
その年の十一月、一つの事件がピニェイロスの市場で起きた。コチア産組と仲買人たちが真っ向から衝突したのである。
これは、バタタ取引のもつれによるものであったが、仲買人は主だった五、六人が突如コチアのバタタのボイコットを始めた。他の同業者にも同調させた。
コチア側は丁度、出荷の最盛期で、不意討ちを食らった。健さんは急遽、組合員代表を招集、対策を練った。その結果、満場一致で徹底抗戦、仲買人たちへの販売拒否が決議された。
数年前の世界恐慌の折の乱れに比較すると、意外なほどであった。
組合外のバタタ生産者にも協力を求め、同調して貰った。
コチアの役員・従業員は総員、夜を徹して駆け回った。
出荷がピタリと止まった。