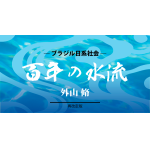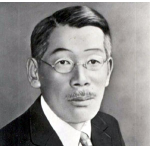対して仲買人側は「コチアは出荷停止で、価格を吊り上げようとしている」とポルトガル語の新聞に記事を書かせ、その上で、州政府へ苦情を持ち込んだ。
対して仲買人側は「コチアは出荷停止で、価格を吊り上げようとしている」とポルトガル語の新聞に記事を書かせ、その上で、州政府へ苦情を持ち込んだ。
ところが、その思惑は外れた。州政府の産組奨励局のルイス・アマラル局長が、
「ここで負けたら、ブラジルにおける産組の発展はありえない。最後の勝利を得るまで闘いぬいてくれ」
と、コチアを激励したのである。
実は、二年前に立法化された産組法に基づき州政府内に設けられた奨励局は、組合育成に懸命になっていたのだ。
コチア側は俄然、勢いづいた。謄写版刷りのビラを数千枚、市中に配って、自分たちの正当性を市民に訴えた。すでに倉庫に滞貨していたバタタを、市中の小売商人に直接販売した。従業員が全員…といっても未だ十数人という規模だったが、注文をとって歩いた。
仲買人たちは旗色が悪くなり、何を思ったか突飛な行動に出た。日本総領事館へ仲裁を依頼したのである。総領事は健さんを招き、
「騒ぎが大きくなったら外交問題になる。妥協したらどうか…」
と勧めた。が、健さんは、こう拒否した。
「これは、外交問題ではない。イモづくり対商人の問題。そこへ総領事が首を突っ込んできたら、そのことで外交問題になってしまう」
イモづくりとは、バタタ生産者のことである。
出荷停止は一週間続いた。結局、仲買人側が敗北を申し入れ、市場は元に戻った。
後日、健さんは「あの時は死ぬか生きるか、二つに一つだと思った」と、述懐している。
コチアが勝ったのは、州政府(産組奨励局)が味方になったことが大きかった。錦の御旗が翻ったのだ。それと、世界恐慌の時ほど生産者が窮境になく団結できたことにもよる。
事件そのものは小さな産組と数人の仲買人の争いに過ぎなかった。が、農産物の取引における同種の悶着は、他の市場でも起きていた。それだけに、コチアの勝利の報は、電撃的に邦人農業界に広く伝わった。
産組の存在価値が改めて認識され、それは組合外の邦人社会にも浸透した。
この抗争の起きた一九三四年は、その五月、既述の様に排日法が成立、日系社会が危機に陥り、誰もが悄然としていた。
そのさ中でのことであり、社会的期待がコチアひいては産組そのものに向けられた。
当時、産組は未だ少なかったが、以後、増え続け、事業量は増大して行く。
急成長
仲買人との抗争勝利は、コチア発展の起爆剤にもなった。
組合員が急増したのだ。事件の前年の一九三三年末には三七〇人だったが、この年の末には五六〇人、翌年末は九三〇人、翌々年末は一、一八〇人…という勢いだった。
これは、抗争勝利でコチアと健さんの人気が一挙に上ったことによる。「コチアに入れば、これまで自分達の利を盗んでいた商人に対抗、勝つことが出来る」と喜んだのだ。
これに応じて、コチアは定款を改正して事業地域を広め、取扱い品目もバタタだけでなく蔬菜(主としてトマテ)、鶏卵、綿、その他を加えた。
既述の非登録の蔬菜組合も合併した。
バタタ生産者の反対はなかった。バタタだけの組合経営が却って危険であることが判ったのである。
ともあれ、仲買人との抗争勝利の経験は、健さんに何事かを悟らせたようである。以後、大ポカと言えるような失敗は犯していない。
年齢的には三十六、七歳頃からのことである。
そして、創業からほぼ一〇年後の一九三八年末には、コチアは驚くほど大きくなっていた。次の通りである。
ピニェイロスに組合本部。
組合員は一、五〇〇人(含、一割ていどの非日系人)。その所在地はサンパウロ周辺、州の西部地方。
従業員は百数十人。
バタタの収納用倉庫
三棟をサンパウロ市内に所有。
販売所をサンパウロ二カ所とサントス、リオに一カ所ずつ所有。
組合員の多いヴァルゼン・グランデ、モジ・ダス・クルーゼス、スザノ、ジャカレイ等に〝部落〟を設置。
ほかに、要所々々に〝倉庫〟を設置。
購買部門で、営農資材や生活用品を販売。
信用部門で、組合員を対象に各種貯金制度を設け、集まった金は、組合の運転資金に充当。組合員に対する融資にも利用。
運搬部をつくり生産物、営農資材・生活用品を輸送。組合員家族、従業員を対象に医療部を開設…(以上)(つづく)