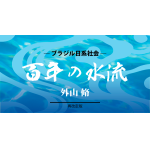一九三五年、サンパウロの西側のムニシピオ、ヴァルゼン・グランデに事業所を開設した。
一九三五年、サンパウロの西側のムニシピオ、ヴァルゼン・グランデに事業所を開設した。
同年、同じく東側のモジ・ダス・クルーゼスにも進出した。が、ここには、すでに邦人の蔬菜生産者たちのモジ産組が生まれており、その理事長が「コチアの進出は無法行為である」と抗議した。
モジはその頃、サンパウロ、リオ両市場向けの蔬菜(主としてトマテ)の生産地として、急速に開発が進められており、奥地から邦人農業者が多数、流入していた。
コチア側の記録類によれば、進出は前年、モジ産組の一部組合員が、コチアへの鞍替えを申し入れたことがキッカケになっていた。その時は健さんが、先方の渡辺孝理事長を訪れ、話し合ったが、物別れに終わった。
これを憂慮して、総領事館の青木技手が調停に乗り出した。が、これも成らなかった。「血気」の項で記した総領事館の裏庭での、青木と某の乱闘は、この時に起こっている。
青木が、その調停の折「両組合の蔬菜販売を統一し、コチアの販売所を通して行なう」という案を出したところ、某がある場所で「青木はコチアに買収された」と口をすべらせた。それが当人の耳に入ってしまった。その直後、二人が総領事館で鉢合わせして…という次第であった。
結局、調停は不首尾なまま揉め続けた後、コチアはモジへ事業所を開設した。以後も各地へ進出した。
増資積立金
マジック、独創の二は増資積立金制度である。
これは「組合員の出荷物の販売額の一部を、組合が自動的に天引きして資本金に組み入れる」という仕組みである。
組合員はコチアに加入時、出資金を納め、以後は生産物を出荷、販売してもらう度に、手数料を払っていた。
それ以外にこの増資積立金を引かれたのである。資本金に組み入れるわけだから、原則的には、その組合員が脱退時には、出資分は払い戻されることになっていた。 が、その間、価値がインフレ以上に調整されるという保証はなかった。(現実には、目減りした)
この増資積立金が制度化されたのは、一九三六年からで、最初は販売額の二㌫であった。三六年というと、仲買人との抗争勝利の翌々年であり、組合員が一、〇〇〇人を突破した時期である。そういう勢いの中で健さんは、この制度をつくった。皆、その抜け目のなさには驚いた。
しかし当人は、
「既存の組合員の増産分や新しく入って来る組合員の生産物の保管倉庫、市場での販売場所が必要であり、そのための増資積立金である。それが厭なら、誰がその資金を負担するのか…」
と強行、この増資積立金でアチコチに施設を確保、新組合員をジャンジャン受け入れた。
新組合員が入ると、その分また増資積立金が入ってきて、投資ができるというカラクリだった。
産組は一般企業と違って、利益率を一定限度内に押さえられており、そうである以上、これしか方法はないというのが健さんの理屈であった。
その利益率は、法律では(資本金対比で)一二㌫を限度とすることになっており、コチアでは定款で一〇㌫と決めていた。それ以上の利益が出れば、組合員に払い戻す規定だった。
健さんは、この増資積立金で大胆に投資を推し進めた。例えば公営の蔬菜市場が、サンパウロの中心部アニャンガヴァウーに新設された時、広大な売場面積を買い取った。一九三八年の事で、面積は二、五〇〇平方㍍、四年払いの八五〇コントという買い物であった。当時の蔬菜部の販売高は、年間五〇〇コントに過ぎなかった。これには、組合員も従業員も度胆を抜かれた。
しかし、こういう投資の結果、施設に余裕が生じ、新しい組合員を受け入れることが出来たため、事業量は大きく伸び続けた。
サンパウロ市場の拡大は止まらず、それを当てにしての、奥地からの邦人農業者の流入も同様だった。
彼らが頼るのは組合くらいしかなかった。が、施設に余裕のない組合は、受け入れることはできなかった。
コチアには、その余裕があった。
増資積立金は、健さん式無限錬金術であった。
無論、これを嫌って脱退して行く組合員が多く、新規の加入者も少なければ、この錬金術は崩れたであろう。が、脱退者は少なく、加入者は増え続けた。
別の組合が、新規の加入者を受け入れる余地がなかったためである。
先に記したコチアの資本金の桁外れの大きさは、この増資積立金によるものであった。