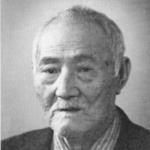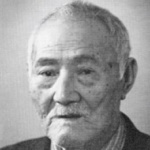この後、連盟はサンパウロに中央訓練所をつくった。そこでは盟友たちが、よく合宿していた。週末になると下元がやってきて、テニスをしたり、訓練生のつくった稚拙な食事を喜んで食べたりした。
この後、連盟はサンパウロに中央訓練所をつくった。そこでは盟友たちが、よく合宿していた。週末になると下元がやってきて、テニスをしたり、訓練生のつくった稚拙な食事を喜んで食べたりした。
若者を経営戦略の中に組み込んで行くのは、事業体の幹部なら誰でもすることである。が、それは、あくまでもピラミット形の組織構成を尊重しつつである。
しかし下元は組合の内外で、直接、彼らと結びついた。それには無論、理由があった。
コチアを創立した頃、その主力メンバーの多くは若かった。理想に燃え、純粋に組合のことを考えていた。
下元自身は歳を重ねても、その若き日の心を持ち続けた。しかし、ほかの者はそうはいかなかった。人というものは青年期を抜け、家族を持てば、自然に現実を、目前のことを優先して生きるようになる。
新規に加入してくる組合員たちも、多くは生活の苦労を背負っていた。
こういう人々にとって、組合とは、まず「生産物の有利な販売、安い営農資材・生活用品の購買」のための機関であることが必要だった。自分たちの仕事や生活が、少しでも良くなる事が第一であり、組合はそのための道具であった。
だから下元が強引に進めるコチアの拡大政策は迷惑であった。彼らにとって、設備投資は既存の組合員の必要を満たすだけで十分であった。新規の組合員用の設備投資の資金まで、自分たちが負担することには反対であった。
ところが下元はコチアの大型化を追求していた。彼によれば、組合は強くなければならず、それには巨大化する必要があった。さらに、繰り返しになるが「産組を核に、農業者が支配する一個の新会を建設しよう」とまで本気で考えていた。
下元の構想は、普通人には、壮大過ぎる夢であった。が、当人にとっては、それは自然な発想であった。農業、産組というものを徹底的に研究し、そこに現実を組み合わせて行けば、そういう結論になるのである。
無論、そんなことは、その日の暮らしに追われる年輩の組合員の理解と協力を得難いことは判っていた。だから見限った…というわけではないが、彼らに不足するその部分を、若者に求めた。若者のエネルギーによって事を進めて行こうとしていたのである。
若者は理想を理解し、憧れる。理想のために、時には身も心も投げ出そうとする。しかも組合事務所では業務の第一線に居る。農場では労働の主力である。まとまり易く数は多い。組合内に占める比重は大きい。
新社会
では下元は、どんな新社会をつくろうとしていたのか?
中尾熊喜の除名事件の折、彼は、こういうことを言っている。
「産業組合は、被圧迫階級が共に手を携えて、資本家階級に対しつつ、地位の向上を図ろうとすることが目的であり、一人のカーネギー、一人のロックフェラーをつくることを目的とはせず」
カーネギーは、中尾が師表とした米国人である。一代で巨大な富を築き、社会事業に投じた。
対して、下元はマルクス主義に関心を寄せ、それに関する本を読んでいた。日本では、マルクスの本を読むだけで、赤呼ばわりされた時代であり、そういう雰囲気は、ブラジルの日系社会にも持ち込まれていた。が、彼は熟読した。後で、こう嘆息していたという。 「我々がやろうとしている産組運動なんて、全くケチ臭いものだナ…」と。
若者たちの前で、こう明言したこともある。
「共産主義とコペラチヴィズモの差は紙一重である」(コペラチヴィズモ=組合主義)
この紙一重の差の説明は無く判りにくいが、あるいは私有財産を認めるか認めないか、の差であったかもしれない。
一九三九年のコチアの機関紙の年頭所感に、下元の次の言葉がある。
「我々は、此処ブラジルで産業組合を組織した。組合運動の究極の目的は、新しい社会の建設にある。新しい社会とはなんであるか、それは言わずとしれた共存共栄の社会である。従来の利益社会から共存共栄の社会を創造する。利益社会人から組合人となる」
利益社会とは資本主義社会のことであろう。
共存共栄の社会について詳しくは、別章で以後のコチアの歴史を追いつつ考える。