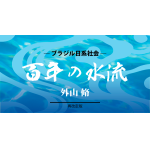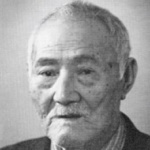下元は、やはり同年の産組中央会の役員会で「産業、経済、教育、衛生、その他百般の事業を産組が統括、経営せよ」
下元は、やはり同年の産組中央会の役員会で「産業、経済、教育、衛生、その他百般の事業を産組が統括、経営せよ」
と熱弁をふるっている。
他の産組にも新社会建設を慫慂、鼓舞したのである。
ここで思い出すのは、上塚周平の「日本外に新日本を建設する」、山県勇三郎の「日本国家の分封をする」、宮坂国人の「拓殖事業は国づくりに似ている。最も男らしい仕事」という言葉である。
下元の「新社会建設」論も、これに通ずる勇壮な心意気がある。
蛇足だが、右の「心意気」とは、日本人だけの独立した地域社会や小国家をつくろうとした…という意味ではない。言葉に出してしまっては味気無くなるが、理想社会創造への志、夢のことであり、勿論、ブラジル社会への融合、貢献を含めている。
「新日本」も「国家の分封」「国造り」も、言葉に熱気を込めるため、そういう表現をしたに過ぎない。戦前の日本語は、おおむね、こうであった。
その志、夢はこの四人だけでなく、当時の指導者や気概ある若者の胸中に、多かれ少なかれ燃え続けていた炎である。
それを知らずしては、日系社会の歴史は理解できないし、その炎の存在を否定したら、歴史から艶が消え、ただの、つまらぬ移民の苦労話となってしまう。記録するには値せぬ。
下元健吉は「産組を核とする新社会」を建設しようとし、同志を若者たちの間に求め、産青連運動を起こしたのである。
だから、若者たちに招かれれば、喜んでどこへでも出掛け、講演した。それに酔う者が少なくなかった。
その一人は、こう記している。
「講習会の講師として頼めば、厭な顔一つしないで、必ずいつでも気持ちよく、あの忙しい仕事を放っておいて、下元さんは遥々七〇〇㌔の山奥へ、ゴトゴト汽車に揺られてやってきて、うわついた机上論ではなく、実際的産組論をふりかざして、諄々として説き来たり説き去り、聴講時の経つのを忘れたものです。
ときには、机を囲んで、あの卓越した特有の話術で、聞く若者に夢を与え、奮い立たしめ、夜のふけるのも忘れて、語り明かした事も度々であった。
講師と呼ぶより親父と呼ぶにふさわしく、どんな土臭い青年にも『団結は力だ、協同すれば必ず勝つ』と叫んで、夢を与えて下された」
ブラジル版産青連運動は、地方からも澎湃と沸き起こった。
外部から、下元を親父と慕う者が現われる位だから、コチアの若者たちにとっては、下元専務は完全に親父であった。面と向かって、そう呼ぶ者もいた。
その親父は、若者を魅了する美点を豊富に備えていた。まず、私利に恬淡としていた。「私利を去れば、先が読める」とは、よく言われることであるが、親父は先見性にも優れていた。若者の一人は後にこう語っている。「親父は、サンパウロという市場の無限に近い拡大を読みとっていた」
その親父が指揮するコチアは、西に東に北に南に…組合員を増やし、資本力を強化、施設を作り、事業を拡張した。
最初は、粗末な砦に拠る野武士の群れだったのが、戦場を駆けている内に、いつの間にか一国一城を有する軍団になっていた…のである。
コチアの若者は陶酔した。
組合と親父を誇り、その下に結集した。やがて彼らの中から一生をコチアに捧げてしまう者が少なからず出ることになる。
組合の内外で若者たちの間に高まる下元人気は、彼に批判的な組合員や役職員も、軽視できないものになった。いや、引きずられていた。
下元はコチアを牽引、新社会建設を目指して突き進んでいた。
一九四一年、組合員は二、二〇〇人を越した。