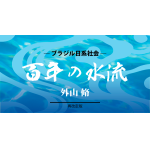かくしてコチア産業組合は、日系社会最大の城郭となりつつあった。とすれば、下元健吉はその代表的指導者として推戴されるべきであったろう。しかし、そうはならなかった。何故か?
実は、彼の無礼さが嫌われていたのである。外部の人間に対する礼儀、口の利き方は、組合の若い連中を相手にするのと変わらぬ乱暴さで、ために「下元なにするものゾ!」といった反感を生じさせてしまったのだ。
無論、誰もが彼を、その事業面では評価していた。排日法の衝撃の中で、日系社会の新たな歴史の水流を形成しているのが産組であり、その先頭に立っているのがコチアである…とは解っていた。
しかし、それと下元個人に対する感情は別であった。
同業の産組の幹部たちですら、その無礼な言動に辟易、距離を置いていた。
先に、下元が中央会の役員会で「…百般の事業を組合が統括、経営せよ」と熱弁をふるったと記したが、これも聞き手を発奮させるには至っていない。
実は外部だけでなく、組合の内部にも、下元を嫌う者が少なからず居た。それは古参の組合員に多かった。彼らは、後にこう語っている。
「下元健吉は、コチアは自分が作ったかの様なことを外部の人間に吹聴しているが、創立の最大の功労者は村上誠基であって、下元は同志の一人に過ぎなかった」
「組合が大きくなったのは、組合員の力である」
「組合員は、高知県人と鹿児島県人が多く、両派には暗黙の対立があった。が、鹿児島派の頭株の鳥原巳代治が事情あって帰国した。ために高知派が優勢になり、自然、下元が組合の経営権を握った。その後、コチアはコウチヤ(高知屋)と呆れられるほど、高知県人が幅を利かすようになった」
ともあれ、かくの如くで、下元健吉は、彼を慕う若者たちの目には、長所のみが光って写っていたが、彼を嫌う人々の目には、短所のみが陰って写っていた。これが彼のハンディキャップになっていた。
産組中央会
ところで、同時期、コチア以外の邦人産組は、どう動いていたろうか。──
例の日本政府の奨励金で、一九二七年のコチアに次いで、一九三一年までに七組合が生まれていた。
一九二八年、イグアッペの桂、レジストロ、セッテ・バーラス、二九年にジュケリー、三〇年にカフェランヂア、三一年にプロミッソン、イガラパーバである。
その間、三〇年に日本から総領事館の勧業部に、前出の青木林蔵技手が着任している。
青木は産組づくりに非常な熱意を持っていたが、奨励金の方は、三一年が最後となった。
しかし青木は精力的に地方を回って、自力による産組設立を説き、協力した。
青木は一九〇〇(明33)年の生まれで、京都帝大の農政経済学部に学び、在学中、高文試験に合格、卒業後は拓務省に入り、数年後、サンパウロ総領事館に出向した。
日本出発の折「ブラジルで、邦人の農業経済機構を建て直す」と、意気込んでいた。そして既述の様に一九三四年、日系産組の連合機関として、日伯産業組合中央会を設立した。
この中央会に十六組合が参加した。青木はこれを基盤に、日系産組の拡充を内容とした五カ年計画を立て、具体化しようとした。
拓務省の資金協力をアテにしての企てであったが、予算がつかなかった。ために、しばらく休業状態が続いた。
が、一九三五年、前章で触れた平生使節団の来訪があり、翌年から綿の対日輸出が始まった。中央会はその取引に参入した。
ただ綿は資金がかか り、邦人農業者は非日系の綿花会社の下請け的立場で営農せざるを得ず、不利な条件下におかれていた。
そこで中央会が、彼らが自立した綿作りができる様、支援をした。同時に、その(精綿後の)綿を日本から進出していた商社に販売した。さらに傘下の組合が、精綿工場をつくるよう計らった。組合のない地方には、設立を勧めた。
青木が、この一連の動きを指導していた。中央会の綿の取扱量は増え、経営は軌道に乗った。
一九三九年、中央会への参加は二十組合となり、その二年後の一九四一年には、二十六組合に増えていた。組合名は次の通りである。(つづく)