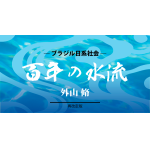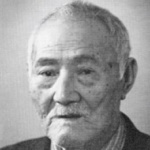産組中央会に関してもう一つ話を付け加えると、その理事会で、しばしば専務の下元とやり合い、時には激論する若手の理事がいた。ジュケリー産組の中沢源一郎である。
この組合は──三章で少し触れたが──サンパウロの北側に位置するジュケリー(現マイリポラン)という村の郊外、丘陵地帯で営農する四〇人の邦人バタタ生産者によって一九二九年に生まれた。
創立時の名称は「ジュケリー農業生産者有限責任組合」であったが、戦後スール・ブラジル(南伯)農協と改称、今日でも、その名で記憶されている。
ジュケリーの発足はコチアに遅れること二年でしかなかった。が、十年経っても、組合員は僅か九二人であった。財務内容も極度に悪化していた。
原因は内紛に次ぐ内紛にあった。それはその度に、組合を興奮のルツボと化し、組合員の集団脱退が出る、という激しさだった。
時には、総会の会場に入る組合員を、警官が身体検査をせねばならないほどだった。武器を持っていないかどうかを調べるためであった。
一九三九年、三度もの紛争を繰り返した上、中沢が実務の中心である専務理事に就任した。三十一、二歳であった。
しかし、この時も脱退組がでた。その中に原田実という男がおり、同年、仲間と別個に新組合を設立した。バンデイランテ産業組合である。二七人が参加した。
この間の詳細については資料も不十分で、名状し難いが、原田たちは以後、中沢とジュケリーに激しいライバル意識を燃やすことになる。
中沢は異色の移民であった。東京帝大の文学部教育学科を卒業した学士であり、その種の人間が移民として来るのは、珍し過ぎる現象だったのである。
一九〇七(明40)年、高知県に生まれた。生家は薬種商で、地元では名家、当人は長男であった。帝大を出た後は、郷里の中学校で英語教師をしていた。
それが何故、移民になったのかは、本人は語らずに終った。一説によれば、一時、陸軍に籍を置き少尉になったが、ひどい軍人嫌いとなり、二度と召集を受けぬため、移民として日本を離れたという。
中沢は、清潔感溢れる大変な美人の新妻を伴って、移住してきた。夫婦とも敬虔なクリスチャンであった。その二人が百姓生活に入り、バタタづくりをしていた。
専務に就任後、中沢は組合再建に没頭、二年後には軌道に乗せた。一九四〇年末には、組合員は一七七人(含、非日系一二人)に増えており、決算は純益が総収入比一割余であった。
この中沢が、中央会の理事会で、下元に対し、しばしば遠慮せず自分の意見を主張した。それを怒った下元が、
「君の組合は、中央会を辞め給え」
と癇癪玉を破裂させ、中沢が、
「そんなことは、貴下の指図を受ける筋合のものではありません」
と、やり返すこともあった。
中沢は、下元と同じ土佐人だが、下元の特異な性格には、実際閉口したようである。後年、こう記して居る。
「下元という人は、なかなか友達になり難い人であった。その子分になるか、敵にならないまでも離れ去るかというような個性の余りにも強烈な独裁型の人であるという印象は拭い切れぬものがあった」
下元は、よその組合の幹部を電話で「中央会の件で話がある」と、礼儀知らずな口調で、近くもないコチアの本部へ呼びつけては、一方的にしゃべりまくった。相手の意見は聞かなかった。ために、誰も呼ばれても行かぬようになった。中沢もそうした。しかし中沢は、下元の行動力や合理的な思考力については、評価していた。
産組については、今回はここまでとし、以後の動きは別章に譲る。(つづく)