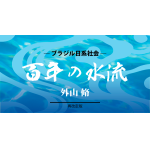ナショナリズムの熱風
一九三〇年代の後半、日系社会は前章で記した様に綿と産組によって、排日法の衝撃に抗し、活気を維持していた。
しかし同時期、またも、早くも、次の危機が近づいていた。それは、ナショナリズムの熱風が運んできた。
その熱風は日本、ブラジルの両方から吹き込んできた。さらに、別方向からも…。
詳細は後で記すとして、まず、ナショナリズムそのものについてであるが。
ナショナリズムは、当時、世界的に大流行していたイデオロギーである。
その生成、変遷、定義には諸説ある。
一説によれば十七世紀の英国で、国内諸勢力の果てしない内乱に辟易した社会的雰囲気の中で、工夫・創案されたという。以後、欧州全域、そして世界へ広まって行った。
別説では、十八世紀の始めに起きたフランス革命に、ナショナリズムの起源を求めている。
他にも異説がある。
右の十七世紀説によれば、そのナショナリズムは初期の段階では、国家の構築・運営のためのイデオロギーであった。法律で権力を中央政府に委託、行政機構を組織、国家を運営しようとする骨組みから成っていた。
従って、この段階では技術論であった。が、技術だけでは、その構成者…つまり国民の間に大きなエネルギーは生まれない。ために愛国心という精神性が加えられた。
以後、変遷の過程で、国内的には革命思想に飛躍したり、対外的には領土・商圏拡大のための帝国主義に化けたり、その帝国主義から自国を防衛あるいは(すでに被支配下に置かれている場合)解放しようとする民族主義に転じたりした。
驚嘆すべきことに、このイデオロギーは神秘的な力を発揮した。人を惹きつけ陶酔させ虜にし、時には命すらかけて行動させた。
その流行は、二十世紀に入ると、最高潮に達した。地球規模で、熱度を高め、熱風を発し、時に発火点に達し紅蓮の炎となり、炎と炎が絡み合い、互いに相手を焼き尽くそうとした。
二度に渡る世界大戦が、それである。
しかし以後、次第に勢いを衰えさせた。
人類史上、最大のエネルギーを発したこのイデオロギーは、純粋な愛国心も育てたが、反面で利己的、排他的で偏狭な自国第一主義を産み、弊害も大きくなった。さらに政治家の野心の道具に利用されることも、少なからずあった。
衰勢は、そういうマイナス面に気づいての興醒め、飽きが広まったことによろう。
つまり流行り廃りは、イデオロギーの世界にもあるということである。
元々は無縁だった邦人移民
さて、一九三〇年代後半、日本もブラジルも、そのナショナリズムの大流行の中に在った。
ただ、ブラジルに移住した邦人の殆どは、ナショナリズムとかイデオロギーとか、そういう難しい言葉とは、元々は無縁だった。
彼らは、日本の農村で素朴に暮らす庶民に過ぎなかった。
渡航前は、郷里の田や畑で自然に逆らわず、御天道様(おてんとうさま)を仰ぎつつ米や麦、野菜、果物を育てていた。それと同じ従順さで、為政者の指導に従って生きていたに過ぎない。
渡航後もそうであった。
ただ、日本でもブラジルでも、為政者が国際的なナショナリズムの流行に染まり、もしくは利用し、庶民を指導していた。
日本では明治維新以来、為政者が新日本の建設を目指して維新以前は無かった。国家というものの構築と国民意識の普及に力を注いでいた。
ために、最初、西欧の国家機構と運営方法を導入していたが、一八八五(明18)年、愛国心を重視する教育制度を制定した。
その四年後、天皇を神格化し国家の頂点に戴いた大日本帝国憲法を発布した。
かくして、外来の思想と古来の天皇制を組み合わせた日本式ナショナリズムが誕生した。
続いて日清・日露の戦(いくさ)での赫々たる勝利が、その日本式ナショナリズムを国民の隅々まで浸透させた。自然にそうなった点もあったが、為政者がそう図ったことが大きかった。
ブラジルに渡った邦人は、そういう時代に育った世代である。無論、為政者の意図を充分に理解していたわけではない。教育制度に関する法令も憲法の条文も、読んだことはなかったであろう。(つづく)