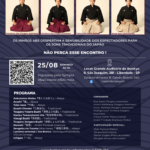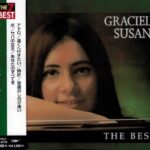「私はスペイン語オタクなんですよ」――本紙にアルゼンチン・ブエノスアイレスから「現地レポート」をたびたび寄せてくれる相川知子さん(57歳、広島県出身)が農林水産省日系農業従事者等連絡協議会の参加者として1月30日にサンパウロ市に立ち寄った折、同地で永住するきっかけなどを聞いた際、そんな印象的な一言を語った。彼女は通訳だけでなく、スペイン語への翻訳もする。現地人並みに読み書きができるスペシャリストだ。
相川さんは広島県出身で、高校から名古屋市で生活し、愛知県立大学スペイン語学科を専攻した。「深い意味があってスペイン語を選んだわけじゃないんです。英語は得意な人がいっぱいいるし、フランス語は難しそう。なら、スペイン語かなぐらいの気持ちで選びました」
だが、大学2年の時に3週間、メキシコに短期留学した際、衝撃的な経験をした。「それまでの私はごく無口でした。一人で本を読んでいれば幸せ、というタイプだったんです。でもスペイン語で話していると、自然に自分が出せることに気付いたんです。私にとっては、日本語よりもいろいろな表現ができると感じました。だって、日本語だとしゃべる必要がないというか、『言わなくても分かるだろう』という空気がありますよね。でもスペイン語は違うんです。好きなことをいっても受容されるというか」
大学卒業後、最初は商社で働いたが「やっぱりスペイン語が好き」との思いから退社。23歳でJICA開発青年制度を活用してブエノスアイレスの在亜日本語教育連合会で日本語教師兼団体事務として派遣され、現地生活がすっかり気に入った。当時の開発青年では永住権がもらえたので、以来住み続けている。
相川さんは1993年からブエノスの大学で日本語を教えている。一クラス25人で、うち学生15人、一般市民が10人。4年間の教程を終えると、日本語で観光ガイドができるレベルを目指しているという。
1994年からは、鉄道会社民営化に伴って日本のJRから技師などが派遣されたのでその通訳の仕事を請け負い、同時に日本語教師をプライベートでやりながら、現地の大学院で言語学を3年間学ぶなど多忙な生活を続けた。「身分や立場によってスペイン語の単語の意味が変わるという現象を調べる社会言語学を主に研究しました」とのこと。
1998年、日亜修好通商条約締結100周年の際には亜日議員連盟の手伝いをし、その時に夫と知り合い、2000年に結婚し、二人の娘に恵まれた。「国民性の違いというんでしょうか。日本人でも信用できない人はできないし、アルゼンチン人でも信用できる人はできる。ただ一般論としては、アルゼンチン人の方が正直というか、建前がない。できないことはできないとはっきり言うのが文化なんですね。それが私には肌に合っていると感じています」
相川さんは翻訳家として、米国に長く滞在して帰国後に数々の文芸賞を受賞している水村美苗さんの初小説『続明暗』のスペイン語版『Luz y Oscuridad una continuación』を手掛け、4月にAdriana Hidalgo editora社から出版されるという。
相川さんは最後にピアーダを一つ披露した。「どうしてアルゼンチンには広大な農地、美しい自然、豊かな資源に恵まれているんだと、世界中の人が神様に苦情を言いました。そしたら神様は『だからアルゼンチン人が住んでいるんじゃないか』と返しました」。アルゼンチン在住者にしか言えない、上級者向けピアーダといえそうだ。
相川さんは「言葉が違う人同士の気持ち、心をつなぐことが人生の目標です」と締めくくった。スペイン語を母語とする人口は約4億8千万人で、世界で2番目に多い言語だ。その割に、日本でスペイン語ができる人は少ない。その意味で、相川さんのような「スペイン語オタク」の存在価値はますます尊重されるようになるかも。