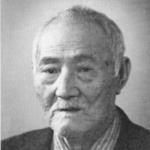ただ、為政者の指導に従って、日本という国家を至上のモノとして愛し、天子様を崇拝し、日本は神国であり戦えば必ず勝つと信じる様になったに過ぎない。
ただ、為政者の指導に従って、日本という国家を至上のモノとして愛し、天子様を崇拝し、日本は神国であり戦えば必ず勝つと信じる様になったに過ぎない。
彼らは、その精神(こころ)を、遠いブラジルに渡っても、忘れることはなかった。子供にも、そう教えた。理由は簡単で、いずれ日本に帰るつもりでいたからである。
祖国日本は躍進していた。明治の末には、朝鮮を併合、大正に入ると、第一次世界大戦に参戦、大陸や西太平洋上に版図を広げた。
もっとも、この段階では、邦人はそれを遠くから眺めて、感嘆していたに過ぎない。それ以上の関係はなかった。
それが、一九三〇年代に入ると、日本の国内情勢が大きく変化した。
四章で触れた様に、第一次大戦後、大不況が襲来、時代が昭和に入っても回復の兆しはなく、むしろ悪化した。都市では労働者のストライキ、農村では小作争議が無数に発生した。
政府はその国難に対し、国民の閉塞感、鬱屈感を和らげるため、ブラジル移住を国策化、ある程度の効果を上げた。が、根本的な解決策を打ち出せないでいた。
それに苛立つ人々の中から、昭和維新を叫ぶ声が高まった。
維新とは無論、革命を意味する。一九三〇(昭5)年『昭和維新の歌』が大ヒットした。
翌一九三一(昭6)年、血盟団事件、五・一五事件が発生、それは三五(昭10)年の永田鉄山少将(陸軍省軍務局長)殺害事件、翌年の二・二六事件へと連鎖して行く。
連鎖は外部へ向かっても起きた。一九三一年の満州事変、翌年の満州国建国、三七年の支那事変勃発がそれである。
いずれもナショナリズムの変形である。
余談
ここで、またひと息入れて、余談を挟む。
右の永田鉄山は、四章で登場したが、日本青年協会の吉岡省がブラジルに旅立つとき、餞(はなむけ)の言葉を贈った人物である、
その時、永田が務めていた軍務局長は大臣、次官に次ぐ要職であった。彼は陸軍きっての逸材といわれ「もし生きておれば、東條の出る幕はなかったろう」と評された。東條とは、後の首相のことである。
二・二六事件では、青年協会の顧問で天皇の侍従長であった鈴木貫太郎が、銃撃され瀕死の重傷を負った。襲撃部隊を指揮していたのは、吉岡と青年協会の小使室で暖をとったあの安藤輝三中尉だった。(事件当時は大尉)
安藤は、これ以前に協会関係者の紹介で、鈴木を二度訪問し面談していた。その折、鈴木は自分たちが思っていたような君側の奸ではないと感じ取り、悩んでいたという。
決起前、鈴木を目標に加えることに消極的になった。が、同志たちから反対されると、侍従長邸の襲撃部隊の指揮を志願した。
当日、安藤が率いる部隊は侍従長邸に侵入、下士官二名が鈴木と「閣下、昭和維新のため、お命を頂戴します」「待て!」「もう時間が、ございません」「それでは、やむをえない。撃ちなさい」 と問答、銃弾を浴びせた。
この時の情景については、現場に居た鈴木夫人から直接話を聞いたという人が、サン・ジョゼー・ドス・カンポスで花作りをしており、筆者に、その内容を話してくれた。二〇〇五年のことである。高梨一男といい、日本青年協会の出身、吉岡の後輩であった。筆者が会った時は八十三歳だった。
「私が夫人から聞いたところでは、鈴木大将は三、四発撃たれて前のめりに倒れた。安藤大尉が軍刀でトドメを刺そうとすると、夫人は、その前に正座、両手を後ろに回して、背後の夫を庇いながら『武士のなさけ、トドメだけは』と…。
安藤たちは、敬礼あるいは捧げ銃をして、引き上げた」
という。
鈴木は一命をとりとめた。
数年後、高梨が日本青年協会の本部で受講したとき、講師として宇垣一成(同協会会長、元陸相)とともに何回か講義にきた。
「和服姿で、いつも遠くを見ている様子だった。一種、独特の雰囲気があった」
という。
支那事変
ところで、前々項の末尾に記した支那事変であるが、これは、ブラジルの日系社会にとっても極めて重要な歴史的事件であった。
何故なら、日系社会にナショナリズムの熱風を吹き込む役割を果たしたからである。具体的なことは、次項以降で触れる。(つづく)