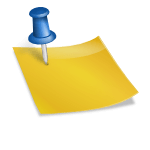毎年恒例のカーニバルまで10日を切り、ブラジル全土で祝祭ムードが高まっている。リオ市のサンボードロモで開催されるスペシャル・グループによるカーニバル・パレード(デスフィーレ)は、今年から1日増え3月2日から3夜にわたって開催される。
初日を飾るのは、過去20回の優勝歴を誇る名門エスコーラ(サンバチーム)のマンゲイラだ。今年のエンレド(テーマ)は、「大地に根ざした花のように―苦しみと情熱を乗り越えたリオの黒人文化(À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões)」。リオにおけるアフリカ系文化バントゥー継承を讃える内容だと20日付アジェンシア・ブラジル(1)が紹介した。
バントゥーはアフリカの中央部、特にコンゴやアンゴラなどの地域で話される言語群のことを指し、その文化がブラジルに持ち込まれて言葉や習慣、音楽などに強い影響を与えてきた。例えばサンバ、キアボ(オクラ)、キロンボ(逃亡奴隷の集落)などの単語はバントゥーに由来する。アフリカから奴隷としてブラジルに渡り、リオで下船した黒人の8割はバントゥー文化圏の出身者だとされている。
マンゲイラのエンレドでは、アフリカからブラジルに渡った奴隷の足跡をたどり、黒人社会がいかに自らの文化を守り、広めてきたのかが描かれる。奴隷貿易の歴史、カトリックとアフリカ土着宗教のシンクレティズム(異なる信仰が融合し共存する現象)をはじめ、バントゥー文化がリオの街にどう根付いたのかをテーマに、サンバやカポエイラ(格闘護身術)、ブラジル音楽の一部ファンキなどが紹介される。
マンゲイラはさらに、奴隷たちが身を守るために形成した「ズング」と呼ばれるコミュニティに着目。ズングとは、アフリカの伝統的な家の形態であり、かつてリオには50以上存在していたとされる。黒人社会が自らの文化を守り、社会的・政治的な抵抗の場でもあった。こうした歴史を再現し、リオにおける黒人コミュニティの文化的影響を浮き彫りにしようとしている。
エンレドを作成したカルナバレスコ(総合演出家)は、歴史学者シジネイ・フランサ氏。サンパウロ市のエスコーラ、モシダーデ・アレグレ出身の彼は、モシダーデなどを何度も優勝に導いてきた。その手腕を評価され、今年リオのカーニバルにデビューすることとなった。
彼は膨大なリサーチを行い、リオにおけるバントゥー文化の起源やその影響を深く掘り下げ、マンゲイラのパレードが単なる祝祭にとどまらず、リオにおける黒人文化の重要性を社会的に認識させるメッセージであることを強調している。
リオの貧困地域や社会的に抑圧された人々の問題を反映した強い社会政治的メッセージが込められている。特に貧困地域に住む若者たちがリオの未来において希望となるか否かは、社会がどのように彼らを扱うかにかかっていると強調。
「黒人の命は脆弱であり、日々を生き抜くことは黒人社会にとっての勝利である」といった強いメッセージも込められており、黒人文化のアイデンティティの重要性も言及されている。