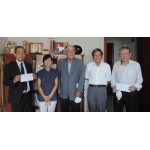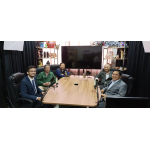「とりあえず、ブラジルでやるだけのことはやりました」――日本語教師一筋に25年間、ブラジルで過ごしてきた渡辺久洋さん(50歳、愛知県出身)が1月31日に編集部を訪れ、翌2月1日に本帰国した。
渡辺さんは大阪大学工学部4年生の時、「研究室に配属されて1日で嫌になった。これは自分がやりたいことではないと確信した」という。そのため卒業後、日本語教師養成講座(420時間)を受講してJICA青年ボランティア(現JICA海外協力隊員)として1999年4月から第1アリアンサの日本語学校に派遣され、「これは天職だ」と面白さのとりこになった。
2年間の任期が終了して帰国するも、すぐにブラジルに戻り、2001年8月から聖南西地区のピラール・ド・スル日本語学校で教え始め、そこから人生の半分を過ごした。「子供本人に日本語を覚えたいという気持ちは普通ない。でも彼らに動機付けすることに困ったことはない。色々試していくうちに絶対どれか上手くいくから」と振り返る。「土日が学校行事で埋まっても、平日の労働時間が10時間を超えても苦だと思ったことがない」と感じていた。
日系社会に伝統的に伝わる「日系子弟向けの継承日本語教育」として、学校のカリキュラムや教材をシステム化し、林間学校やデイキャンプやスポーツ教室などにどんな役割を求めるかなど、教室と課外授業を組み合わせて体系的な日本語教育を整えてきたという。
「去年50歳になった時、サプライズで父兄会の人たちがボクの誕生会を祝ってくれた。100人ぐらい集まってくれたので本当に驚いた。心から信用してくれているのが分かって嬉しかった」と振り返る。地方の日系社会に溶け込んで、必要とされる人材として愛されていた。
そんな昨年12月、仕事関係ではない、純粋な里帰りを四半世紀ぶりにした。「日本のテレビを久しぶりに見て新鮮だった。日本の生活も良いなと初めて思った」と何かが自分の中で変わったのを感じたという。今までピラールでの生活ではインターネットが遅く、テキストメールのやり取りがせいぜいで、日本の動画は見られなかった。ブラジルでは高齢者でも普通に使うセルラーや通信アプリのWhatsAppを、彼はポリシーとして使ってこなかった。
昨年話題になったテレビドラマ『不適切にもほどがある!』ばりの現代日本とのズレが、彼がブラジルで四半世紀も生活する間で生まれていたとしても不思議はない。このドラマは、コンプライアンスが厳しい現在とそうではなかった昭和をタイムスリップするコメディだ。改めて見た日本に、彼の中に見直す気分が目覚めていたようだ。
「日本語学校が自分の人生の全てだと思っていたけど、純粋にそれでいいと思えない部分も強くなるのを感じた」と述懐する。そんな折、年末の里帰りから帰伯した直後、本帰国を決意したという。「日本に帰っても日本語教育に携わっていきたい」と次のステップに進む覚悟だ。
JICAボランティアはたくさん当地へ来ているが、当地が気に入って住み着いてしまう人は極少ない。経済状態の良い日本から来て、家族を養うには厳しい収入なのが一般的な日本語教師という職業に惚れ込んで、それだけを考えて24時間過ごす人はまれだ。
彼が日系社会の日本語教育に尽くしてきたことを否定する人はないだろう。そんな彼が突如帰国することになったのは、日系社会にとっても損失ではないかと思わされた。(深)