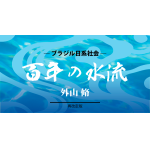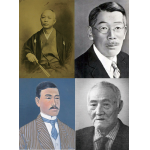この事変は、当初は蒋介石の国民政府軍と日本軍の闘いの筈であった。従って、日本軍は最初「三カ月で片づける」つもりだった。
この事変は、当初は蒋介石の国民政府軍と日本軍の闘いの筈であった。従って、日本軍は最初「三カ月で片づける」つもりだった。
が、いつまで経っても、蒋介石は降参しない。逃げ回りながらも闘いを続ける。ヘンだと思ったら、後方で米国が英国と共に軍需物資を送って支援していた。
時の米大統領はルーズベルトであり、国務長官はハルだった。
五章で触れたことだが、ハルは一九三四年、ブラジルの制憲議会でミゲール・コウトたちを操り、排日法を成立させ、日本の国策・移植民事業を潰し、米の縄張りを守った男である。
それが、この時点では、支那で日本軍の作戦を潰そうとしていた。
ここで注意すべきは、蒋介石軍に軍需物資を援助していたという事実である。これは、戦争に準ずる行為である。
米の日本に対する敵対度は三四年当時より遥かに強まっていたことになる。
それは、米政府の下部機関である在ブラジル公館(大使館、総領事館など)の日系社会に対する警戒度にも、当然、影響していた筈である。
ブラジルでも支那でも、米は縄張り意識で日本に対抗していたのであり、別々のできごとではなかった。
吹き込む連戦連勝報
さて、支那事変で、日本軍は果てしない泥沼に踏み込んでしまった形となったが、当時、日本国内では連戦連勝と報じられていた。
戦争特需で、景気も回復に向かい、国民の間に充満していた閉塞感、鬱屈感も薄らぎつつあった。同時に、ナショナリズムの熱度が急上昇していた。
そして、皇軍の連戦連勝ぶりは、地球の反対側まで伝えられ、邦字新聞によって報じられた。
そのニュースは、サンパウロの日本総領事館を通じて、邦字新聞に提供されていた。
新聞だけでなく日本から輸入される雑誌も、それを伝えた。軍国調華やかな記事や挿絵が満載されていた。
一九三八年、日本放送協会のブラジル向け短波放送『東京ラジオ』が始まった。
短波用の受信機の所有者は少なかったが、それからは勇ましい軍歌が流れた。
邦人相手の商店が、店頭に置いて客寄せに流した。蓄音機とレコードを使うこともあった。
奥地の、邦人入植者が多い土地の中心部、小さな商店街を歩いていると、突如、勇ましい日本の軍歌が流れて来るという具合だった。
因みに支那事変が始まって以後の邦字新聞を捲ってみると、一面は連日の様に、前線の動きを伝えており、社会面は祖国向けの国防献金の記事が目立つ。
皇軍兵士への慰問袋が各地の日本人会からサンパウロへ集められ、送り出されていた。
その熱気は、日本と変わらなかった。
応召を希望、日本へ帰る若者が続々と出ていた。中には、日本の父親から呼び戻されて…とか、予備砲兵少尉が妻子をこちらに残して…という話もあった。
各地で銃後婦人会や銃後男女青年会が生まれ、尽忠報国が合言葉になった。
弁論大会が開かれ、襷がけの弁士が登壇「祖国の為に」「聖戦を思う」などの演題で熱弁を振るった。
支那の前線での軍用輸送機が不足しているというニュースが流れると、献納を目的とする募金運動が起こった。
その宣伝のため、飛行機で地方の邦人集団地を訪問するという企画が発案された。
邦人ではただ一人、操縦資格を持つ青年が、実際、飛行機を操縦してバウルー、リンス、マリリア、アバレーなどを空から巡回した。邦字紙記者が同乗、取材した。
かくして日系社会は日本からのナショナリズムの熱風を浴び、染まり、老いも若きも男も女も子供も刺激され、高揚し夢中になった。「我々も祖国のため何か役に立ちたい」「ジッとしていられない」と興奮していた。
単に「日本での出来事」ではなくなっていたのである。
日本語教育界にも
支那事変で発生した日本国内のナショナリズムの熱風は、日系社会の日本語教育界にも吹き込んできた。
日本移民は渡航後、最初は大抵、辺鄙な土地に在るファゼンダで就労した。そこにはポルトガル語の学校も日本語の学校も無かった。(つづく)