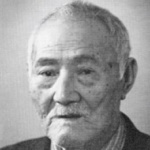親たちは「いずれ日本へ帰るのだから、無理して、子供をポ語の学校へ行かせる必要はない」と割り切っていた。
親たちは「いずれ日本へ帰るのだから、無理して、子供をポ語の学校へ行かせる必要はない」と割り切っていた。
が、日本語は学ばせようとした。初歩的なそれは、親や年長者が教えた。日本から輸入される雑誌類は、無理をしてでも買い与えた。日本語を学ばせ、日本人としての自覚を持たせるためである。
彼らはやがて自営農となり、サンパウロ州、パラナ州その他で、集団で営農した。そこでは、必ず日本人会をつくった。会の主目的は日本語の学校をつくることだった。学校といっても、寺子屋式の粗末なモノであったが…。
このブラジルでは、どこかに植民地ができると、入植者が非日系の場合、真っ先に作られる公共の建築物は教会であった。日系の場合は日本語学校だった。
近くにポ語の学校があれば、そちらにも通わせた。無い処も多く、その場合、日本人会に余力があれば、開校することもあった。
日ポ両校とも小学校で、規模は小さく、多くが教員は一人か二人だった。子供たちは、午前と午後に分けて両方へ通った。
但し、親の方はポ語校については軽く考えていた。当分この国で生活する都合上「子供たちにポ語を覚えさせ、親を助けさせる」ていどの動機で、そうしていた。
それに比較すると、日本語に関しては、真剣だった。それは、その子供がブラジル生まれであろうと、同じだった。親は子供が生まれると、日本の公館(総領事館、領事館)に届け出をし、国籍をとっていた。
因みに、ブラジルの法律では、この国で生まれた者には国籍を与えていたから、登記所にも出生届を出していた。二重国籍になったわけだ。
ポ語校の教員は非日系人であり、当然、教育はこちらに重点を置き、生徒たちにブラジル人意識を持たせるべきであると思っていた。が、政府が地方の学校教育には手が回らず、ポ語校そのものの数も少なく、ある時期までは、余り大きな問題とはならなかった。
そうした中、一九二〇年代末から三〇年代にかけて日本政府は、ブラジルに大型の移住地を造った。(四章参照)
そこでは本格的な日本語の学校が建設された。規模、施設、教育内容は日本と変わらぬ水準だった。それまでの寺子屋式のそれに比較すると、面目を一新していた。
寺子屋式の日本語学校に関しては、サンパウロ日本総領事館が、一九二〇年代から、梃入れを試みていたが進展しなかった。
それが一九三六(昭11)年、総領事館の援助で、ブラジル日本人文教普及会、略して文教普及会が発足、活動を開始した。
その活動は、以後、支那事変と併行して、日本のナショナリズム色が濃厚になって行った。
総領事館によって日本から招かれた指導者たちが、学校と連絡をとって、日本式教育の徹底を図った。
学校では日本と同じ教科書で生徒を指導、御真影を排し、教育勅語を奉読…という具合だった。
教員の講習会も開いた。開会式で祖国を遥拝、皇室の繁栄と皇軍将兵の武運長久を祈り、君が代を斉唱、教育勅語を奉読した。
翌日からは、早朝、太鼓の音で起床、鉢巻きを締めての運動場での駆け足、国民体操の後、清掃、洗面、その後また太鼓の音で講堂に集合、祖国遥拝、静座、朗詠朗誦、精神講和の後、やっと講習…というスケジュールだった。
これも日本の教員養成方法と変わらなかった。
当時の資料に目を通すと、日本語学校のことを「日本学校」と記している。日本学校とは、日本人を育てるための学校という意味であった。
生徒たちに日本人意識を持たせ、祖国の海外発展の一翼を担わせようとしていたのである。
総領事館は学校建設や教員雇用などのため、経済的援助もしていた。
その結果、一九二〇年代は僅か二、三十だった学校数が一九三〇年代には四百以上になった。(いずれも小学校)
上級学校に進む成績優秀な学生のためには、日本への留学制度まで設けた。
子供たちは…
右の様な日本、ブラジルの時勢下、邦人の子供たちは、何の疑いもなく、強い日本人意識と皇室崇拝心、そして「日本は神国であり戦えば必ず勝つ」という信念を育みながら成長した。
その子供は日本生まれ、日本育ちは勿論、ブラジル生まれでも、幼年期に渡航し日本の記憶が無い者でも、同じであった。(つづく)