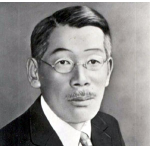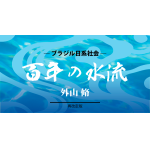男子の場合は、帰国して兵隊さんになり従軍することに憧れる子が多かった。
男子の場合は、帰国して兵隊さんになり従軍することに憧れる子が多かった。
やがて彼らが青年期に入る頃、日系社会は騒乱期を迎えるが、その騒乱の中に身を投じる青年が、少なからず出ることになる。
ここで、参考までに、彼らの内の幾人かを紹介しておく。
サンパウロ州のほぼ中央部、バウルーを起点に西北西へ伸びるパウリスタ延長線沿線の開拓地に、三人の少年(もしくは若者)が居た。(以下のポ語地名は、サンパウロを除き、すべて同沿線の開拓地)
内、一人は日高徳一といった。遥か後年の二〇〇一年、筆者は知己となった。マリリアで息子さんたちと、自転車の修理店を何店か営んでいた。小柄で明るく、話好きの七十代半ばの好々爺であった。
一九二六(大15)年、宮崎県の延岡に生まれ、七歳で家族と共に移住してきた。
子供の頃、一家はドアルチーナで借地農をしていた。が、日本語の学校はなく、ポ語の学校は、父親が「日本に帰るのだから必要ない」というので、行かなかった。だから、学校は何処にも行っていない。
父親と従兄が日本語の初歩の読み書きを教えてくれた。家は貧しかったが、親は本だけは買ってくれた。日本から届く雑誌『幼年倶楽部』や『少年倶楽部』である。戦争の話が多く、支那事変が始まると、日本軍の活躍を盛んに載せていた。
少し読解力が進むと、流行作家の山中峰太郎の日露戦争を題材とした小説、同じく佐藤紅緑の少年向け小説を読んだ。
同じ年頃の子供たちの間で、本を貸したり借りたりした。そのため、山を一つ越して訪ね合うこともあった。
その雑誌や本は「無我夢中になってむさぼり読んだ」という。自分が記事や小説の中に居る様な気がした。
「身を鴻毛の軽(かろ)きに置き、君国に報じる」という言葉も覚え、陶酔した。
筆者は日高とは、長く付き合ったが、彼はしばしばこの言葉を懐かしそうに口にしていた。表情を輝かして…。
日高の祖父は、二人とも西南戦争に従軍した。母の兄弟三人は、日露戦争に出征、一人は戦死、一人は片足を失った。
自分も兵隊さんになって戦地に行きたくてたまらなかった。自分だけが置き去りにされている様な寂しさを覚えた。
そして前記の騒乱期、二十歳になっていた日高は、同志と共に出聖して、当時の日系社会の指導者格の人々を襲撃する。
筆者は、この日高の紹介で、彼の同志であった山下博美とも知合った。やはり二〇〇一年のことである。
山下は、長く臨床病理検査師を務めた後、サンパウロの市内でささやかな年金生活をしていた。年齢は日高と同じくらいだった。穏やかで澄んだ、しかし芯のある老人だった。
山下は一九二五(大14)年、三重県に生まれた。三歳の時、両親に連れられ、この国へ来た。無論、日本のことは記憶になかった。が、日本人として育てられ、当人は何の疑いもなく自分を日本人と思っていた。
少年期、ポンペイアで日本語とポルトガル語の学校に通った。
その日本語の小学校時代の写真を見せてくれた。同級生と一緒だった。男ばかり十数人である。皆、背筋を伸ばしキリッとした表情をしている。筆者の記憶の中に在る敗戦後の日本の同年輩の子供に比較すると、数段上、という感じだ。その印象を口にすると、
「そりゃー、あの頃は日本軍が大陸で勝った、勝った…で、勢いが良かったですからネー」
と微笑していた。
それが子供たちの誇りと自信になり、こういう表情になったのだ。
その写真の中の、もっとも品の良さそうな少年が山下であった。
「級長さんだったのでは?」
と訊くと、
「そんなこともありましたネ」
という返事だった。
「学校では、日本式の忠君愛国教育でしたか?」
とも質問してみた。すると静かに、こう答えた。
「そうです」
筆者は、写真の中に二世らしい顔が無いことに気付いて質問を続けた。
「二世の子供は居なかったのですか?」
ところが返事は、
「イヤー、ほとんどが、こちら生まれだったでしょう」
だった。(つづく)