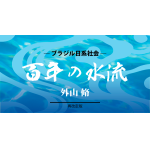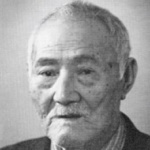大津波、襲来(Ⅱ)
日本が米英に開戦した時、日系社会の表情はいっときは至極明るかった。日本軍の華々しい戦果を歓び、喝采する声が、何処でも上がっていた。
それまでの日本と米英の関係悪化のいきさつを、ある程度知っていたこともあるが、自身の怒りも重なっていた。
一九二四年から始まった日本の国策としての大型移植民事業が、僅か十年で終わってしまったのは、米の干渉による一九三四年の排日法成立が原因であった。
その後のブラジル政府の日系社会への圧迫…つまり日本語学校の閉鎖や邦字新聞の廃刊も、裏で米が糸を引いていた。
右いずれも米の兄弟国の英が足並みを揃えていた。
それ故、祖国日本が彼等に鉄槌を下し、自分たちの恨みも晴らしてくれた(!)という嬉しさが沸き起こったのである。
ブラ拓代表の宮坂国人は開戦の日に「わが海軍、ハワイ真珠湾攻撃の報あり、遥かに太平洋を望みて感激の涙流る」と帳面に書きとめている。
宮坂は排日法で苦汁を呑まされていた。
聖州新報を葬られた香山六郎は、その回想録にこう記している。
「(開戦報を知らせてくれた友人と)痛快々々を連呼した…(略)…二人は肩を抱き合ってしまった…(略)…男泣きにわめいた。日本万歳!と」
彼らの感涙は、多かれ
少なかれ、他の邦人にも共通する感情であった。それを知る上で参考になる資料がある。
当時、サンパウロ市内に住み、ごく庶民的な生活を送っていた画家の半田知雄の遺した日誌である。その中で半田は開戦後の日々の心境を詳細に記している。
以下は、その一部抜粋である。
一九四一年。
「十二月十四日 絵をかいていても戦争のことが気になる」
「十二月十七日 この頃ゆっくり本がよめない。日米戦争開始以来、感情と戦いながら絵をかいているので、夜は頭が働かないのだろう。すぐねむくなってしまう」
一九四二年。
「一月六日 当地の新聞が勿論外電としてではあるが、日本軍の進撃ぶりは文字通り悪魔的だ…(略)…と報じている。…(略)…こんな文字も我々には気持ちよくよめる」
この日誌によれば、半田は、友人の河合武夫(コチア産組職員)が自宅で東京ラジオを聴いていたので、戦況に関する放送内容を訊ねるため、足しげく訪問している。
ポルトガル語の新聞も読んでいた。定期購読はしていなかったが、隣家のドイツ人から借りたり、市電に乗って前の席の人が読んでいると、こちら側の紙面を覗いたりした。自分で買うこともあった。東京ラジオの内容と比較しながら、戦況を追っていた。
因みに、半田は一九〇六(明39)年の生まれで、十歳の時、家族と共に移住、美術学校を出て画家になった。
開戦時、年令は三十代後半で、妻子とともに暮らしていた。
筆者は半田を多少知っており、この日誌を読む前は、
(半田さんは開戦前は同化・永住論を唱えた文化人であり、そういう人なら、醒めた眼で戦争を見ていたのだろう)
と思っていた。
が、右の如くで、これは違った。ほかの邦人と同様、素朴に祖国の勝利を歓んでいたのである。そのことは、日誌の以後の欄にも、しばしば出てくる。
半田に限らず、邦人なら誰でも。自身の生活問題を除けば。最大の関心事は戦争の成り行きであった。
誰もが、同胞と会えば戦争の話という日々だった。
もっとも、そのニュースの入手先は限られていた。ポルトガル語の新聞は、邦人の殆どが購読していなかった。
邦字新聞は発行禁止になっていた。
そういう中で、唯一ニュースが入るルートが東京ラジオであった。邦人の間にホンの僅かだが、短波用の受信機の所有者が居て、それを聴いていたのである。
外国からの放送の受信は、ある時期から禁じられたが、隠れて聴いていた。取締りは厳しい時、所もあれば逆の場合もあった。放送内容は口から口へ伝えられ広まった。
その東京ラジオで流される大本営発表によれば、日本軍は真珠湾以降、無敵ぶりを発揮していた。これが邦人を興奮させ、再移住熱を一段と煽った。
「戦争が終わったら、一旦、祖国へ帰り、日の丸の下での再移住を……」
と。
再移住は戦争で当分不可能になってしまっていたのだが、気運は衰えることなく、逆に燃え上がっていたのである。