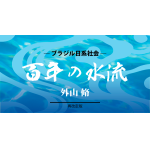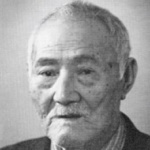何故、右の様な使い分けをしたのか。あるいは、この文書が米英側に渡った時のことを考慮して、内容が厳しく刺激的な部分に関しては、某国としたのかもしれない。
何故、右の様な使い分けをしたのか。あるいは、この文書が米英側に渡った時のことを考慮して、内容が厳しく刺激的な部分に関しては、某国としたのかもしれない。
またボイコットは、この場合、策動の一つと観るべきである。
(この警告文が、国名の順序を英米としているのは、当時の国際的格付けに従ったのであろう。が、五章以降に記した様に、日系社会に対する圧迫の主役は米であり、英は脇役であったので、本書は米英と記している)
筆者は、後にパラナ州々都クリチーバの日本領事館が、これと同趣旨の書類を、同時期に地元の日系社会に配布していたことを知った。他の日本領事館でも、そうであったろう。
なお、ここでいう米英とは、その在伯公館(大使館、総領事館、領事館)や館外の通信社などを隠れ蓑とした工作機関のことである。
その公館や工作機関が、直接あるいは手先として雇ったブラジル人を使って、策謀を仕掛けていた。
アルモレに理不尽な真似をさせたのは、彼らであろう。
一般の邦人にとっては、予想もしていなかった展開だった。戦争は遠く、北半球の、西太平洋や東南アジアで行われており、自分たちが直接関わることはない、と思っていたからである。
ところが、すぐ近くから攻撃を受けてしまったのである。唖然とした。
しかし米英にとっては、ブラジルも日本との戦場に準ずる国だった。 近代に於ける戦争の形態は、第一次世界大戦を境に大きく変わっていた。
それまでの「軍人同士が武器を使用して戦場で戦う」から「民間人も戦場以外で情報、経済その他あらゆる面で戦う」方式へ…である。
そういう意味では、地理的には準戦場は無限に拡大していた。
米にとって、ブラジルは戦略上、極めて重要な準戦場であった。
何故なら、大量の軍需物資の供給国だった。
さらに米が欧州で独伊と闘うための軍事基地として、格好の位置にあった。例えばブラジル大陸の北東部、大西洋に突き出た地点(ナタール)に、軍事基地を建設した。ここは米本土より戦場に近かった。この場合の戦場とは北アフリカ、南欧を指す。
米はブラジルを自陣営にガッチリと確保しておく必要があった。
そのブラジルに、日本人が多数居ってウロチョロしていることは、それ自体、目障りだった。放っておけば、日本や独伊のために何をするか判らない。例えば、スパイ活動や米のブラジル確保の妨害である。
従って監視し、その動きを掣肘、一方でブラジル人と離間させる必要があった。
そのための警告文の中にある様な陰険な策動であったのだ。
ともかくブラジルは準戦場であり、日本人は敵であった。攻撃すべき標的であった。ただ武器を使って実戦をするわけにはいかなかったから、策動という手を使ったのである。
因みに、米の大統領ルーズヴェルトは、当時「世界戦争論」という言葉を使っている。「今回の戦では、世界中が自分たちの戦場である」という意味である。
米に握られたラジオと新聞
一九四二年一月十五日、リオで汎米外相会議が開かれた。
米国が急遽、招集したのである。
会議開催の三日前、米代表の国務次官が乗り込んできた。
石射自伝によると、
「…(略)…米国のサムナー・ウェルズ国務次官が伯国官民の大歓迎裡にリオ入りをし、当夜の記者会見で
『会議の目的は枢軸の西半球攻撃の手を封じ、両米州を安泰に置かんとするにある』
と第一声を放った。
新聞は一斉にウェルズ氏のリオ入りの盛況を報じ、吝しみなく歓迎の意を表した。
伯国の宣伝情報局には、既に米国の情報官が乗込んで言論と報道の指導に当たっていると伝えられ、ラジオと新聞は完全に米国に握られた感があった。
戦況記事は、引続き日本の勝報を伝えたが、見出しが小さくなった。黄色の文字を以て、日本人を侮辱する記事さえ現れて、我々を不愉快にした」
という。
ラジオと新聞を完全に握ったのは、米としては準戦場に於いてはなすべき、当然の策動であったろう。
その手法は五章で記した排日法の時と同様、買収であった筈だ。
再び半田日誌を引用する。
「一月十五日 夕方、電車に乗ってくると、八割迄の乗客は新聞をひろげていた…(略)…すぐ前の人のそれをのぞき見したら、ドイツのことを盛んに悪口…(略)…」
「一月十七日 新聞が盛んに枢軸側の悪口を書き出した…(略)…」
策動の結果である。