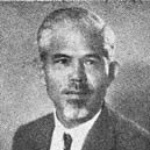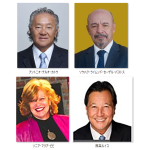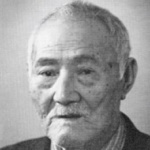しかし実は、策動はこれ以前から始まっており、また、これ以後も延々と続く。それは追々記す。
しかし実は、策動はこれ以前から始まっており、また、これ以後も延々と続く。それは追々記す。
話を汎米外相会議に戻す。会議では、劈頭、ウェルズ次官がこう演説した。
「米州諸国に、枢軸国の外交官がおるのは有害無益だ。彼等がスパイ行為をなし、任国の秩序撹乱工作に従事しているのは証拠歴然だ」
米州諸国から枢軸国の外交官を追い出し、両者の関係を裂こうとする意図が明白であった。
スパイ行為をなし…云々というが、その証拠を明示したわけではない。
因みに、少なくとも日本の外交官は、ブラジルでスパイなどという気の利いたことをする力は持っていなかった。
石射自伝によると、開戦直前、ワシントンの日本大使館から一等書記官が来て、南米に情報網を張る相談をした。
間諜の使用が考慮されたが、結局、この案は捨てられた。危険が大きく適任者も居なかったためである。
任国の秩序撹乱工作をしているのは、前掲の日本総領事館の警告文に記されている様に、米英自身であった。
この大戦で米は、汎米諸国だけでなく、世界中の国々を、より多く味方につけようとしていた。 数が多い方が、自国の正当性を国際的にアピールできる。自陣営を連合国と称したのも、そのためである。
外相会議で米は、参加国の代表に対し、枢軸国に対し宣戦布告あるいは国交断絶をする様、強力に働きかけた。英も協力していた。
しかしアルゼンチン、チリー、パラグアイが抵抗、中立維持を主張した。他の国も直ぐには従わなかった。
それはそうであろう。どこの国も、枢軸国に宣戦布告や国交断絶をしなければならぬ理由はなかったのである。
最終的に米は「国交断絶勧告」の線まで、後退しなければならなかった。
ただ何故か、ブラジルのみは違った。一月二十八日、会議最終日の議場に於いて、アランャ外相が、自国の枢軸国に対する国交断絶を高らかに宣言したのである。
同日夕刻、外相から国交断絶通告書がリオの日本大使館へ届けられた。
国交断絶は策略
以上の展開は、日系社会にとってはマサに凶事であった。開戦時の至極明るかった表情は、アッという間に消えた。
しかし不自然であった。ブラジルの枢軸国に対する国交断絶が…である。(不自然という言葉は前章で何度も使ったが、この章でも、それ以上に使わねばならない)
ブラジルと枢軸国の関係は、断絶しなければならぬほど悪化してはいなかったからだ。
日本の場合、政府間では五章で記した一九三四年の排日法の成立という不祥事はあったが、以後、両国は関係改善に努めていた。(ブラジル政府と日系社会の関係は別であったが…)
それと国交断絶などという重大事の場合、大統領が直接発表すべきである。何故、外相がしたのか?
なお東京ラジオは、外相会議中、ブラジルに向けて、ポルトガル語と日本語で、
「日本にとって中南米は敵ではない。特にブラジルとは友好関係を保っている」
と繰り返し放送していた。
この放送のアナウンサーは、平田進というブラジル生まれで日本留学中の青年だった。
平田は福岡県の隠れキリシタンの後裔で、一九一四年、ソロカバナ線の開拓地サンマヌエルで生まれた。
一九四〇年に、サンパウロ法科大学を卒業、翌年、日本政府招聘の留学生として渡日した。
開戦後、東京ラジオのアナウンサーとなり、ブラジル向け放送を担当していた。
戦後ブラジルに戻り、下院議員になったが、その頃、アナウンサー時代の想い出を、筆者に少し話してくれたことがある。
平田の放送内容は当然、日本政府の意思であった。東京ラジオの責任者は、それに基づいて平田に放送をさせていた。
その放送で送信される日本の友好的姿勢に対し、ブラジルは冷然と国交断絶で応えた。
これは、ひどく不自然であった。
何故だろうか?
この疑問を、ある一通の書簡が解いてくれた。
当時、パラナ州北部の開発地バンデイランテスで、野村農場の支配人をしていた牛草茂という人がいた。