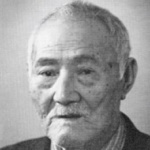彼が、前年の一九四一年八月…つまり開戦の四カ月前に、日本の本社宛て報告書の中で、次の様に記しているのである。
彼が、前年の一九四一年八月…つまり開戦の四カ月前に、日本の本社宛て報告書の中で、次の様に記しているのである。
「最近に於ける北米の伯国に対する圧迫は実に予想以上に猛烈なるもの在之り、心ある伯国人は、自国を属領扱いにする北米に対しては内心痛憤致し居るも、余りある金力と伯国の北米に対する致命的なる経済上の依存関係を利用して迫りくる北米の外交政策には、いやいやながらも、ひきずられざるを得ざる伯国の現状にて、当地有識者の間に於いては万一北米が対日宣戦布告を行えば間もなく伯国も之に追従す可しとの見解が行われている実情に候…(略)…北米は伯国に於ける第五列部隊の本部をリオに置き、月七五万ドルの金をバラ撒き、伯国のあらゆる方面に食い込み居り…(略)…大蔵大臣ソーザ・コスタ氏及び外務大臣オズワルド・アラーニャ氏は完全に北米の手先にて、従来、比較的枢軸国側に好意を有し居りし中堅軍部中にも弗の力に骨抜きとなる者も多き由にて候。
唯、大統領及び参謀総長の二人は飽くまでも独立国としての態面を保ち自主独立的見解の下に行動致したき念願の由に候も…(略)…北米の圧迫は強大にて、愈々となれば大統領の首のすげ換えさえ行いまじきあり様にて…(略)…」
文中のアラーニャ…これもアランャのことであるが、一九三四年、制憲議会で排日法案の審議が紛糾した時、強引に採決に持ち込み、成立させた当時の大蔵大臣である。米英と緊密な経済関係を築き、米から大型援助を取りつけていた。
ブラジルの反枢軸、米英寄りの外交政策は、この男が主導権を握っていた。
牛草書簡は、その情報をどこから得たかは記していない。が、当人が野村財閥派遣の支配人であったこと、本社宛ての報告書であったことから判断すると、確かな処から入手したものであろう。
筆者は晩年の牛草を知っているが、信用してよい人物である。
なお、岸本丘陽は、こう記している。
「ブラジルに於ける英米資本の活躍は実に目覚ましいもので、鉄道、電気、工業、金融界のごときは、かれらの独占事業で、それだけこの国の内部に深く喰いこみ、隠然たる恐るべき勢力を把握している」
枢軸国への国交断絶は、大統領のゼッツリオ・ヴァルガスは乗り気ではなかった。が、すでに経済的にこの国を実質支配している米英の圧力でそうせざるを得なかったのだ。
国交断絶宣言を自分がせず外相にさせたのも、そういう消極的気分のためであったろう。
外相は、米英の視線を意識して、その国交断絶を「高らかに宣言した」のである。
因みにヴァルガスは、七章で触れたが、国家統一という最大の政治課題で腐心していた。そのため、ドイツ、イタリアでそれを見事に成し遂げ独裁体制を確立したヒットラー、ムッソリーニを評価していた。彼が一九三七年強引に独裁体制を敷いたのは、その顕れである。
牛草書簡にある七五万ドルという工作費については(どうして、そんなことまで判ったのだろうか?)という疑問が浮かぶ。
が、五章で記した排日法の成立のため、米が巨額の議員買収費を使った折のことを思い出すと、疑問は解ける。
米は開戦の四カ月以上前から、ブラジルを自陣営に確保するために、金をバラまくという策動をしていたのである。
ということは、四カ月以上前から日本との戦争を予定していたということになり、前章で記した「開戦は米の陰謀」説を裏付ける材料にもなる。
アランャ外相の国交断絶宣言に関して、東京ラジオは放送中、
「これはアメリカの策略によるもの」
と断定していた。
断絶は米の圧力によるものだと判っていたのである。
以上が、不自然な国交断絶の背景である。
日本は、その後もブラジルとは友好関係を保とうとした。東京ラジオも、その意思を放送し続けた。
しかし「ブラジルも日本に対する準戦場」と見做す米英にすれば、友好関係などとんでもない話であった。国交断絶でも生ぬるく、むしろ宣戦布告をさせたかったのである。
ともかく必要な策動は何でもする…そういう腹であったろう。