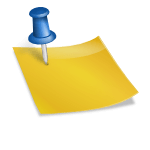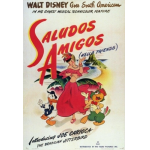広い庭の前は両側に広がる海岸、家の裏の方は野の花が咲く高原で、子供心に丘に登ったり遊んだりして楽しかったことを覚えている。姉たちは市内の大広場小学校と言う日本人の学校に通っていた。
1936年(昭和11年)に日本内地の政変に伴って国策会社満鉄では上層部の大異動が行われた。父は直属の上司であり、尊敬していた大蔵公望理事(男爵)の解任と共に17年勤めた会社を退職、住み慣れた家を処分して内地に引き上げることとなった。
この異動で父は突然左遷され、新理事の気に入りの配下で父からは後輩の下で働けという辞令を受けたからである。左遷の理由はなんと能力不足のため、という無法なものであった。
無能どころか、父は商工課長として社員の生活を植民地の悪徳商人たちから守るため、後では満州全域に店舗を広げた満鉄社員消費組合というスーパーマーケット網の立案と創立を行い、社命で大豆の貯蔵と物流の研究にアメリカのニューヨークにあるコロンビア大学に留学してその部門のために報告を行うなど常に課長クラスのトップを走っていたのである。
辞令をたたきつけて辞職した父と前後して、父の親友の経済課長の上塚司氏も退職、故郷の熊本県から衆議院選挙に出馬して当選した。父たちはその頃拮抗していた二大政党、政友会・民政党の激しい政権抗争に巻き込まれたわけである。
東京には母の両親(坂倉喜豊と坂倉はな)が小石川区(現在の文京区)原町に居住していたため隣接する本郷西片町の貸家にしばらく住むようになり、まもなく学齢に達すると至近距離にある市立誠之(せいし)小学校に入れられた。
この学校は江戸時代、備後国福山藩の藩校の後身といわれる名門の進学校で、担任は和泉量一という数学の専門家で、「算術問題精選集」と言う広く使われていた受験用参考書の著者で、授業中鞭で黒板を何度も叩くという厳しい教師であった。
ところが2年生に上がった時、父の新しい仕事、陸軍の満州派遣軍である関東軍経済班への赴任のため満州国の首府新京市に住むようになり、市内にある白菊小学校という満鉄経営の学校に転校した。
父はまもなく満州国立銀行の創立委員長を任命され日夜努力していたが、銀行設立後は満州中央銀行の筆頭理事である総務理事に就任した。総裁には皇帝溥儀氏の従兄弟で財政学者の栄厚氏、副総裁には銀行経営のベテランで台湾銀行の理事であった山成喬六氏を迎えた。(つづく)