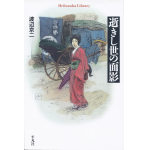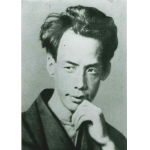「社会を腐敗させるのは、一人の権力者に隷従(盲目的に付き従うこと)する大多数の俗衆である」と説くのは500年ほど前にフランスで生まれた、フランス人法学者エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ(1530―1563)である。「自発的隷従論」というこの名著は、彼が23歳の頃に著わされた。
作者は両親とも法官貴族の家系であったが、早くに孤児となり叔父に養育され、父と同じ法官の道を歩んだ。若くして法学者となり、高等法院の評定官として着任するが、1563年、ペストとみられる病で死亡した。33歳であった。
「これほど多くの人、村、町、そして国が、しばしば一人の圧政者に隷従する、耐え忍ぶということはどういうことか」という問いかけから始まる論説文は、圧政者とその支持者が一体となって、組織的、政治的、社会的、そして戦争へと駆り立てるメカニズムが解き明かされている。
今日の世界情勢解読書かと見紛うばかりの内容で、古典とは思えないほど新鮮で、力強く読者を魅了する。ここでは本書に沿ってその構造を要約して紹介したい。
「多数者が一者に隷従する不思議」
「権力者・圧政者をその地位に留めているのは、つねにそのおこぼれにあずかる連中によって支えられ、それに民衆が自発的に隷従することで完成する。その者(圧政者)の力は、民衆が自ら進んで与えている力に他ならない。・・・神よ。これはいったいどういうわけだろうか。これを果たして何と呼ぶべきか。何たる不幸。無数の人々が隷従され、圧政の元に置かれているのを目にするとは」
すなわち、古代から歴史的権力者たちはどのようにしてその権力を守ってきたか。絶大な軍事力か。厳格な監視体制か。いかなる抜け穴も許さない法の支配か。そうではない。俗衆自らが権力者の礎になっているのである。長いものに巻かれよ、強いものに折れよ、重いものに押しつぶされよと、自らが進んで隷従してるからである。
なぜ人は、そのように自分の自由を犠牲にしてまで権力者に服従するのか。あるギリシャの政治家は毒殺されるのを怖がり、毎日少しずつ毒を飲んだという。それと同じことで、民衆は権力者には服従するということに慣れてしまった。それは、毎日少しずつ毒を飲むという習慣を続けてきたことにより、耐性ができてしまったからである。
習慣は第二の天性を作る。
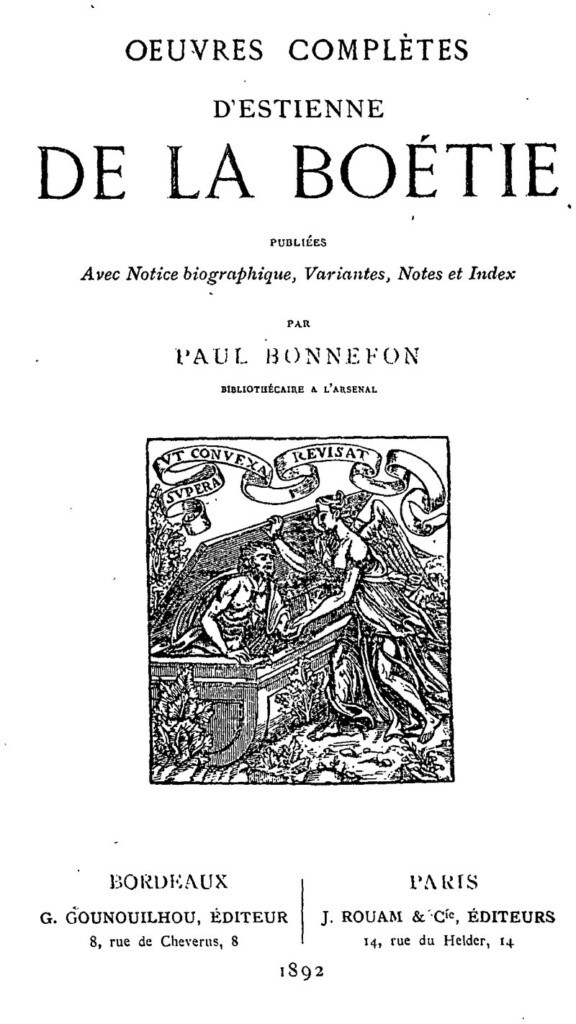
ではなぜ、民衆はそのような圧政者や取り巻きの小圧政者に隷従するのであろうか。
その第一の原因は、習慣である。習慣は生まれ持った性質を容易に塗り替える力がある。
人間の生来持って生まれた性質はわずかなもので、「教育と習慣」によって第二の天性が作られる。健康体で生まれたとしても、成長の過程の環境次第で良くも悪くもなる。
人間が進んで盲目的に従う習慣を身に付けたのは、生まれついたときから、親に従うようにしつけられ、理性という種子を持って、良き助言と良き習慣によって育てられれば、それは徳となって開花する。
人間には、明晰な理解力とともに、物事をはっきりと見通す精神を具えている者がいる。彼らは、俗人の様に目先の欲に心を奪われない。過去を回想し、来たるべき時代の事柄を判断し、現在を検証する。
もともと優れた頭脳を学問と知識で磨き上げ、それを習い性(習慣)にして身に備える。
権力者は人間のそのような知性を嫌悪する。知性で武装した人間を最も嫌い、抹殺しようとするのである。
圧政者とその取り巻き連中
「圧政者」とは何か。それには3種類あると説く。
選挙で選ばれた者は民衆をまるで飼い慣らした猛獣のように扱い、武力によって国を与えられた者は民衆を自分の餌のように扱う。世襲相続した者は民衆を奴隷と考え、自分を「偉大」と思って得意になり、圧政を維持する方法として、民衆の隷従を極めて強く押し付ける。その性格が貪婪(強欲)であれ、放蕩(品行下劣)であれ、意のままに自分が得た遺産であるかのように国を扱う。
このような権力者たちはどのように民衆を騙し、隷従させるのか。その詐術を次のように示している。
圧政者の詐術(人をだます手段)―1《娯楽》
圧政者は娯楽で臣民を骨抜きにする。芝居、賭博、大衆劇、剣闘士と猛獣の決闘、珍獣の見世物、賞牌(賞状やメダル、金品)の授与、その他のガラクタを民衆に与えることは、圧政のための道具である。武力を使わず、相手を圧倒する。こうした手段、慣行、誘惑で民衆の心を翻弄し、民衆は阿呆になり、暇つぶしの一過性の遊興に耽り、次第に圧政者に隷従することに慣れていく。
詐術(人をだます手段)―2《饗応》
民衆は、何よりも口の快楽にたやすく溺れる。これは愚民政策の際たるもので、圧政者は、折に触れて彼らに饗応する。小麦一袋、葡萄酒一杯、小銭を少し、気前よく与えることで、「王様万歳!」という歓呼の声を集める。愚か者たちは、圧政者が所有しているものは、自分たちの税金を奪ったにすぎないことに気づかないのである。
この⑴と⑵は、「パンとサーカス」といって、ローマ帝国の支配戦略を象徴する言葉である。これは、国民の政治的関心を逸らし、権力への不満を抑えるために、食料の供給と娯楽の提供に重点を置いた政策を指す。食料(パン)と娯楽(サーカス)は、民衆の基本的な欲求を満たすことで、安定した社会を維持する手段として機能した。現代社会も同様で、メディアや娯楽に大衆の関心を向け、政治や社会問題への意識を薄れさせる仕組みにする。
詐術(人をだます手段)―3《称号を得る》
圧政者は熱心に自分に称号を付けようとする。この称号や最高位の褒章によって国家という後ろ盾を獲得し、民衆は、その称号を聞くだけで恩恵を感じるからである。また、公共福祉や公的救済などのためには、なんらかの美辞麗句で施し、巧妙な下心で民衆を操るのである。
詐術(人をだます手段)―4《自己演出》
みずからの統治をゆるぎないものにするために、下手な仕掛けの網をかけ、間違いなく引っかかる俗衆を、常に自分の意のままにしようとする。公衆の面前に出るときには、神がかりの演出をし、それを見た俗衆は、あまりにたやすくだまされるので、彼らをバカにすればするほど、上手く隷従させることができると考えている。
詐術(人をだます手段)―5《宗教心を駆り立てる》
為政者は、人々の宗教心に付け込んで、盲人の眼を開かせたり、膝行者(歩けない者)を歩かせてみたり、全能なる父を演出し、悪を罰せんと演じて、我こそが平和の体現者と大芝居を打つ。
小圧政者の存在
圧政者には必ず、ずる賢い取り巻きがいる。それは、騎馬隊でもなく、武器でもない。四、五人の「小圧政者の存在」である。一人の圧政者のために、国全体を隷従の状態に留めておくのは、ほんの四人か五人の仕業である。
彼らは次のように振舞って地位を得る。
圧政者にこびへつらい、嘘を吹き込んで気を引き、満足させるために、好みや癖を知り尽くす。為政者へのご機嫌取りで悪辣極まりないことをし、圧政者と隷従する民衆の両方から利益を得ようとする。
連中は、正に「虎の威を借る狐」の存在であり、莫大な闇の財をかき集めるが、その破廉恥な末路は、堕地獄そのものとなる。
哀れで愚かで惨めな民衆よ
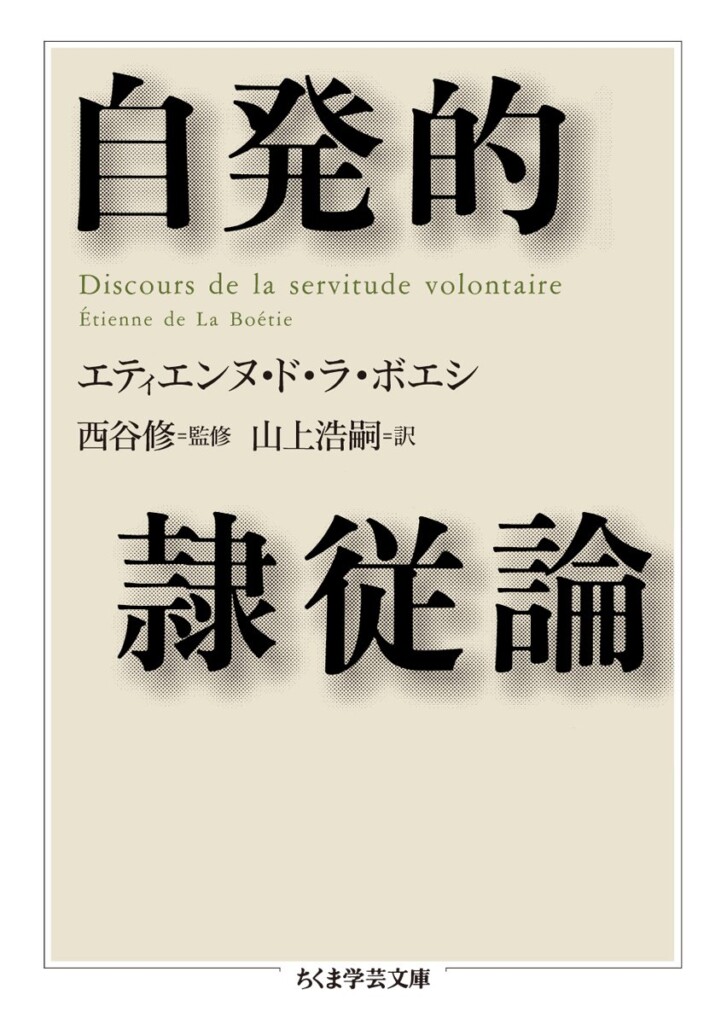
あなた方は、自分の祖父伝来の田畑、家屋が略奪されているのが分からないか。これは、多くの敵によるものではなく、たった一人の圧政者がもたらしているのだ。それをあなた方は、あたかも偉大な人物の様に敬い、その者のために戦争に行き、その者の威信のために自らの尊い命を死に晒し、財産を投げ売って貢いでいることを知らないのか。
民衆を支配しているその敵は、目が二つ、腕は二本、身体は一つ、街の中の最も貧しく弱い者の身体と全く変わらない。
それなのに、その敵が持つ権力は、あなた方が与えているのである。あなた方は果実を種から育てながら、住まいを整えながら、子供を育てながら、それらを、わざわざ奴の餌食として与えているのである。
自由のための不服従
自然と言う良母は我々に地上を住みかとして与え、同じ家に住まわせ、皆の姿を同じに作った。互いが相手の姿を映し、声と言葉と言う贈り物を与え、互いの考えを言明し合うことを通じて意思が通い合い、協力と交流の結び目を強くしてくれた。
ところが同じ姿でも支配するために生まれたもの、支配されるものに分かれ、ある者は大きな分け前を得、ある者はそれを受ける力を得る。大いなる力は、大いなる責任を伴う。持つものは奢らず、持たない者は卑屈にならず、誰のために、どのように活かすかが問われるのである。それは分断ではなく兄弟愛として、自然に生まれたものだった。
このような「生まれつき」の状態から成長すると、社会的、国家的長に隷従するようになるという社会的習慣が身につく。隷従状態の下で発育し、成長する者たちは、もはや、生まれた時の状態に満足し、それが自然の在り方だと考え、国家の束縛から脱出して自由を得ようと考えることはない。さらに、先人たちが力によって強制的に隷従させられると、後世の人間は、悔いもなくその時の権力に隷従する。隷従の習慣は、人間をこのように愚かにしてしまうのである。
隷従を止める方法・非暴力不服従

それではどうすれば、国家的悪徳に君臨する圧政者に隷従することを止めることができるか。
それは、民衆自身が敢えて彼らの抑圧に堪え、我慢している自分自身を知るべきことから始まる。彼らに立ち向かう必要はない。隷従しなければ良いだけである。彼から何かを奪おうと力づくになることもない。奪うのではなく、与えなければ良いだけだ。小さな火に薪をくべると炎は大きくなり、ますます強く燃え盛る。だから、薪をくべなければ良い。
彼らを支えなければ、そのうち、土台を奪われた巨像のように、自分の重みで崩落するだけなのだ。
この思想を提唱したのは19世紀アメリカ東部の哲学者ヘンリー・デビッド・ソローであった。その思想を実践したのはインドのガンジーであり、ロシアのトルストイ、20世紀の黒人地位解放の提唱者キング牧師であった。しかしこの方法は最も困難な道であることが証明されている。
ラ・ボエシ本人も、隷属しないという構想が如何に難しいことかについて言及している。ここでは、彼の先見性に富んだ思想の中からほんの一部を紹介することしかできなかった。
最後に、本書の解説で、西谷修氏は次のように戦後日本人のアメリカへの隷従について印象的な言葉を綴っている。
日本はアメリカの「核の傘」の下に入り、「平和と繁栄」を享受して、核の惨禍の記憶を払いのけながら、「平和利用」という触れ込みの原発を鳴り物入りで導入してゆく。
多くの人々は日本を打ち負かしたアメリカの強大さと華やかな「文明」に魅了され、アメリカに憧れ、アメリカに従い、・・・その風潮は二世代、三世代にわたって引き継がれ今日に至っている。」
ここで、ラ・ボエシを聞いてみよう。
「人は先ず最初に、力によって強制されたり、打ち負かされたりして隷従する。だが、後に表れる人々は、悔いもなく隷従するし、先人たちが矯正されて為したことを、進んで行うようになる」
【参考図書】
『自発的隷従論』(エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ著、監修者西谷修、訳者山上浩嗣、筑摩書房、電子版ちくま学芸文庫2013年11月)