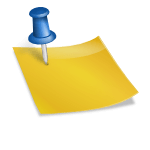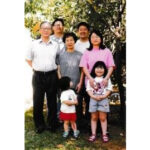そのうち空襲が激しくなったため岩手県盛岡市郊外の小岩井農場(三菱系、東山農事株式会社農場)とその近くの農林省種馬育成所に半分ずつ学級疎開するようになった。私たちのクラスは小岩井組であった。
さて、父は満州中央銀行の理事を1期4年勤めたあと退任し、内地に戻って大蔵公望氏の主宰する国策研究会と言う機関に加わっていた。東京に落ち着いた父は京王線幡ヶ谷駅の近くで渋谷区代々木西原町にあった、元衆議院議員鈴木万次郎氏の屋敷を購入し、建て替えて住むことにした。
敷地は1200坪という松林や大きな池もある広大なものであるので、中心部に新しい家を建て、以前の大きな古い家屋を解体し廃材を利用して周りに4軒の貸家を建てた。新築の家は材木商であった叔父の五十嵐仁氏の指揮で建坪120坪あり、高級な参州瓦と銅版で葺き、大名か大旗本の屋敷のように屋根付きの門を構えた豪邸となったが、1945年5月25日の空襲でその門と庭の燈籠数個だけ残して全焼する運命となった。当時機関銃を作っていた日本タイプライターの工場が直ぐ近くにあったため36発を束ねた焼夷弾セット(モロトフのパンかごと呼ばれていた)が家の真上の上空で開き、消しようもなかったのである。
焼け跡に残ったのはピアノの骨組みと植木バサミなどだけで、おびただしい父の蔵書の灰がいつまでもくすぶっていた。庭に作った防空壕にいた義兄の美しい従妹が直撃を受けてこの夜犠牲になった。
1944年始めから母と次姉、弟は久留馬村の伯父惣一郎宅に疎開しており、姉は日本女子大の家政科を出ていたので村の小学校の代用教員、弟は高崎中学に通っていた。
終戦の少し前、連絡のため東京に帰っていた父と私は赤坂にあった満鉄会館や貸家などにしばらく住んだ後、幡ヶ谷の焼け跡に建築を許された面積一杯の20坪の家を建て、久留馬村から引き上げたものたちと一緒に住むようになった。
私は世田谷区桜ヶ丘の旧陸軍機甲整備学校跡に移った農大に通いながら父と百姓を始めた。
世田谷の梅が丘に以前父が義兄(母の兄坂倉幸利)と共同で買った農地が12反歩あり、その半分(1800坪)に小麦や甘藷を植えて食料を確保しようとしたのである。しかし勉学と農業は両立せず、しばらくして農業を放棄し、畑地を売却することになった。(つづく)