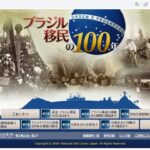「挫折したやつはうちに来い!」のキャッチフレーズで、ポルトガル語教室「ロバのポル語」を運営、YouTube「カポエイライフ」で動画を配信しているポルトガル語講師のなだせいじ、こと久保原信司さん。ほぼ毎年、ブラジルに1カ月ほど滞在しているそうだが、先日ブラジル日報協会の会議室で、オフライン特別授業を初めて行った。
実は、本職は「カポエイラ」を教えることで、しかも「サンパウロ新聞」の記者をしていたこともあるという。
元々は日本の大学院で、アイヌ民族の研究をしていて、ブラジルのインジオ(先住民族)との比較をしてみたい、と思い、ブラジル日本交流協会のプログラムで1995年サンパウロ大学(USP)に留学した。インジオのNGOとインジオの村を訪ねたり、USP社会学部の遠足で、パンデイロ(タンバリンに似たブラジルの打楽器)の演奏を聴き、弾けるようになりたいと思い、パンデイロの演奏を習えるカポエイラの道場を紹介してもらった。
そこで初めて、楽器の演奏だけでなく、カポエイラのすべてを見て、惹きつけられてしまったそうだ。カポエイラとは、ブラジル発祥の伝統的な音楽・ダンス・格闘技が融合したものだ。
カポエイラに惹きつけられたのは日本で少林寺拳法を習っていて、大学では主将も務め、香川県にある総本山に就職しようと思っていたほどで、少林寺拳法とカポエイラの共通点を見出したからだという。少林寺拳法は、技を磨くことや相手を倒すのに熱中するのではなく、精神も鍛えるというのが本当の強さとされていて、カポエイラも「勝ち負け」がない、というところに惹かれたのだそうだ。
このカポエイラを日本に持ち帰って紹介したい、と強く思い、サンパウロ大学留学を終えて日本に帰り、結局大学院の修士論文のテーマも、アイヌとインジオの比較ではなく、カポエイラに変更した。日本に帰ってからも、ポルトガル語を忘れないように、名古屋のブラジル総領事館で働いた。
1997年に「サンパウロ新聞」に就職が決まり、再渡伯、平日の夜と週末はカポエイラ漬けの生活を送った。1999年12月に日本に帰国、愛知県名古屋市で念願のカポエイラ教室を開く。と同時に、ポルトガル語メディア「International Press」で営業を行っていた。
カポエイラはアフリカから奴隷として連れてこられた人たちの子孫が作ったもので、その歴史を紐解くと、国際理解教育につながると考えた。南米やアフリカの情報はほとんど日本に入ってこない。でも、ブレイクダンスやヒップホップなどからカポエイラを知って習いに来る人もいて、そういう人たちにも小難しくなく、自然に南米やアフリカのことを知ってもらえるからだ。

カポエイラを深く極めたいと思ったら、やはりポルトガル語は必須で、カポエイラの歌の意味を知ると知らないとでは、例えば絵を見るときに、ただきれい、と思うのと、その絵のテーマや画家の思いを知って鑑賞するのとでは違うのと同じだという。
カポエイラの教室に来た人たちにポルトガル語を教えたり、愛知県の複数の大学でポルトガル語を教えるようにもなった。「子どもがね、長女18歳、長男15歳、次女13歳と3人いてね、カポエイラのほかにも稼がなくちゃいけないからね」と笑いながら言う。
カポエイラのことを話し始めると、本当に饒舌になり、本業はそちらなのだな、というのがありありとわかる。なだ先生のレッスンは、自身が必要に迫られて苦労して覚えたポルトガル語を、自分がつまずいたところをわかりやすく教えるのが特徴だ。ポルトガル語に「挫折した」人は、ぜひ一度彼のレッスンを受けてみてはいかがだろうか。