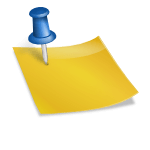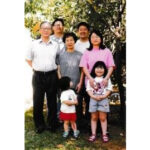学校の方も実験設備が不足のため学外で実技を得ることを奨励していたので私は以前私の家の貸家に住んでいた川島四郎農学博士(元陸軍主計少将)の主宰する代々木にある食糧産業研究所というところに通いサッカリンの合成や化学醤油の製造などの助手をした。その後芝白金の北里研究所(母方の遠縁に当たる北里家の)の秦藤樹博士(梅毒の特効薬サルバルサン発明者秦佐八郎の子)の生化学研究室に移り抗生剤の開発のお手伝いをした。同研究室のマイトマイシンの発見直前のことである。
なお、最近私は緑内障の治療を受けたが、その手術中マイトマイシンが使われたと聞き、秦先生を偲んだ。
やがて、父が政府の復興金融公庫からの融資で資金、油糧公団から原料の供給を得てマーガリン(人造バター)の製造を始めるようになり、新宿区戸塚町に株式会社櫻化学研究所という名前の小さな工場を始めたので、製造法の研究に忙殺されるようになった。
脂肪と水の乳化と急速冷却と練り上げが物理的な作業の要点で、あとは色匂い味付けであった。色は合成色素で簡単に解決したが、味には牛乳の乳酸発酵とグルタミン酸など、匂いつけも合成香料の製造と調合が決め手で、工場の研究室で色々研究した。ジアセチルやアセチル・メチル・カルビノールなどというバターや生クリームの匂いの合成に苦心したが、後ではマーガリンを製造している他社にも売って学費を出せるようになった。
卒業論文は「マーガリン用香料の製造研究」であった。
(3) 終生の職業の選択と修業
香料の分野に強い興味を抱き、その世界に身を投じることに決め、学友の安井廉君(後にマーガリンメーカー日新化工取締役)を会社に入れ、私自身は幡ヶ谷の駅に近い曽田香料株式会社の工場に入社した。
しかし、同社の火事や社長の婿の参議院選挙応援と落選、社業の不振による三井の経営参加などの問題もあり、数か月働いただけで退職、これまた家の近くの大山町にある昭和香料株式会社に移った。高名な香料研究者であった社長の岡澤辰造氏に私服していたからである。
この会社には5年半働き、数々の合成香料(調合用合成品=単品香料ともいう)の製造法を学んだ。曽田に比べ製造装置の規模は小さく殆どがグラスワークであった。バラの匂いのシトロネロール、ゲラニオール、スミレの匂いのイオノン類、桃の匂いのC-14アルデヒド、苺のC-16アルデヒド等々この期間の修業と実際的な経験が後にブラジルの現場で非常に役立つのである。