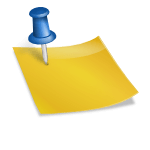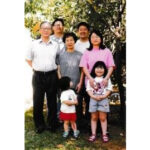1954年の年末、昭和香料を退職した。
毎日新聞の鈴木記者の書いた明るく楽しいアルゼンチンの生活の思い出話や、古き時代のウルグアイを描いてロマンに満ちたハドソンの「遥(はる)かなる国(くに)、遠(とお)い昔(むかし)パープルランド」そして色々な南米関係の解説書・歴史書などを読んで、特にアルゼンチンに興味を持ち、移住して香料を製造したいと考え、父の満鉄時代の友人であり農大の先輩の伏見真次郎氏に受け入れの依頼状を出した。
伏見氏はアルゼンチンのミシオネス州で農園を経営している移住先駆者の一人であった。長期滞在には呼び寄せ書類が必要である。待機中、渡航準備として高田外国語学校に通いスペイン語の勉強に励んだがいくら待っても返事が来ないため、ついに諦めて行き先をブラジルに切り替え、今度はブラジル大使館員が教えていたポルトガル語塾に通った。
なお、伏見氏から受け入れの返事が届いたのは半年後のブラジルへ渡る直前であった。恐らく私を入れる仕事場所の選定に腐心されて手間取ったものだと思う。
この時期、朝鮮戦争は既に始まっていたが日本はまだ貧しく不景気で工員のストライキや学生の政治運動が頻発し、香料の顧客業界ではクラブ化粧品やレートクリーム本舗などの老舗が倒産したり、櫻化学に硬化油を回してくれていた花王石鹸のグループが不渡り手形を出して製造不能に陥ったりの始末で、それら化粧品・石鹸業界に頼り、下請けのような立場の香料業は更に困難な状況で、言わばどん底まで行き着ついた有様であった。
その後になって、運良く朝鮮戦争の特需が起爆剤になって上がり始め、その直ぐ後の神武景気につながって行ったのであるが、そんな日本に比べ当時のブラジル・アルゼンチンなどの南米諸国は正反対で、戦時中は殆ど或いは全く戦いに加わらず、ヨーロッパの連合国に食料を始めとする物資を多量に供給した外貨の決済で急に裕福となり、外国製品の輸入、自動車などはアメリカ、ヨーロッパ諸国のあらゆる種類ものが町を走り、工業化投資も盛んで好景気であった。
弟の勇次は1年半前の1953年慶応義塾大学法学部の政治学科を卒業後の7月にサンパウロにある南米銀行の専務であった宮坂国人氏の呼び寄せで渡伯、同銀行に入って働いていた。ブラジルでの技術者歓迎の状況や、ブラジル工業の大きな可能性についての調査報告を送ってくれていたのである。