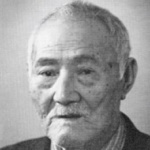しかし既出のリオ移民一〇〇年史によれば、彼は自身の乗船・帰国に際しては、残留する邦人中から出る困窮者のため五〇コントの金を人に託したという。無論、大使館の金であったろうが…。
しかし既出のリオ移民一〇〇年史によれば、彼は自身の乗船・帰国に際しては、残留する邦人中から出る困窮者のため五〇コントの金を人に託したという。無論、大使館の金であったろうが…。
また、交換船が来ることになった時、留置中の地元の邦人の釈放運動を行い、実現させた。日本からの派遣者は乗船した。
その時、石射は移民の浦田年春(石材店主)にも「スパイと呼ばれては、仕事もなかろう。一緒に日本に帰ろう」と声をかけたという。
つまり、することが一貫していない。あるいは、緊張が続く中で、石射は判断を誤ったのかもしれない。そのことを後で自覚したのではあるまいか。これほど重要なことを、その自伝では触れていない。後ろめたさが残っていて、触れることができなかったのではなかろうか。
後ろ姿の卑しさ
この時期の日系社会の心理は、無論、正常ではなかった。
残留した邦人は皆、移民といっても、ごく一部を除いて、帰国を前提に出稼ぎのつもりでいた人々であった。
しかも、この頃は一九二四年から日本政府が推進したブラジル移民奨励策による渡航者が全体の八割以上を占めていた。 彼らは国策移民だったのである。その国策移民を国家が見捨てた、と彼らは思った。
無論、総ての移民を交換船に乗せられるわけはない。誰もが、それは判っていた。
しかし、残留させるならさせるで、相応の配慮…例えば日本政府からの懇切丁寧な説明、邦人保護のための大使や総領事の残留があって、然るべきと思ったのだ。
ところが、そういう配慮は一切なく、石射大使も原総領事も、その他外交官たちも(残留者から観れば)逃げるように交換船で帰国してしまった。しかも、乗船枠の余裕があるというので、サンパウロから駆け付けた人々を追い払って…である。
外交官の最重要任務の一つは任地の在留同胞の保護である。その任務のため、自身の命もかける、そこに外交官の美学がある。
その守るべき同胞を見捨てて、追い払って、自分たちだけ逃げ帰った彼らの後ろ姿の卑しさに日系社会は驚き、呆れ、失望し、怒った。
香山六郎は、その回想録で、
「…これら外交官連は、在伯移植民には、一言のサヨナラも言わず…(略)…我々は平素一面には天皇陛下の赤子だと認識を強いられながら、一面にはイザとなればサヨナラもつげられず棄民扱いをされた…(略)…駐在外交官のかくれるように逃げてゆくような態度は…(略)…彼らの民族的、否人間的教養の浅はかさをしみじみ感じた…(略)…吾々移植民に永住せよなんておすすめなさる外交官連中が…(略)…一番に尻に帆かけ逃げ出す」
と罵っている。(418頁)
文筆家らしからぬ乱れた文章だが、その乱れぶりに、怒りが滲み出ている。
また、当時サンパウロ市内に住んでいた日本陸軍の退役中佐吉川順治は、この外交官たちを、こう鋭く叱っている。
「自決してでも、この国に留まるべきであった」
吉川中佐には、本書の別の章で再登場して貰う。
日本政府の代表である外交官に裏切られた邦人たちにとって、最後に救いを求めたのが天子様であった。その思いがいかに強烈であったかは、架空の詔勅が出たことに現れている。
七章で紹介した日高徳一は、父親から海外の日本人に対する詔勅が出たと聞いたという。その中に、「長く日本精神の美を保持せよ」「艱難辛苦を克服して」という言葉があったそうである。
実際は、そういう詔勅は出ていなかった。
あるいは「我々を残留させるなら、せめて、こういう内容の詔勅が欲しい」と話し合っている内に、それが出た…という風に誤伝されたのかもしれない。
ともかく、邦人たちは、その種のものを飢えるが如く欲していたのである。
もう一つ、邦人たちの間に、幻覚が生まれていた。これは、帰国願望が昂じて…のことであろうが「日本から、迎えの船が来る」という話がまことしやかに伝わり広まったのである。
日本が戦争に勝ったら、自分たち移民を帰国させるための船が来るというのである。これは、日本に帰りたい、帰りたいと思って互いに口にしている間に、来るかもしれない、来る…と変形して行ったのであろう。
無論、あり得ないことだったが、これが戦後まで尾を引き、日系社会に起こる騒乱の一因となる。