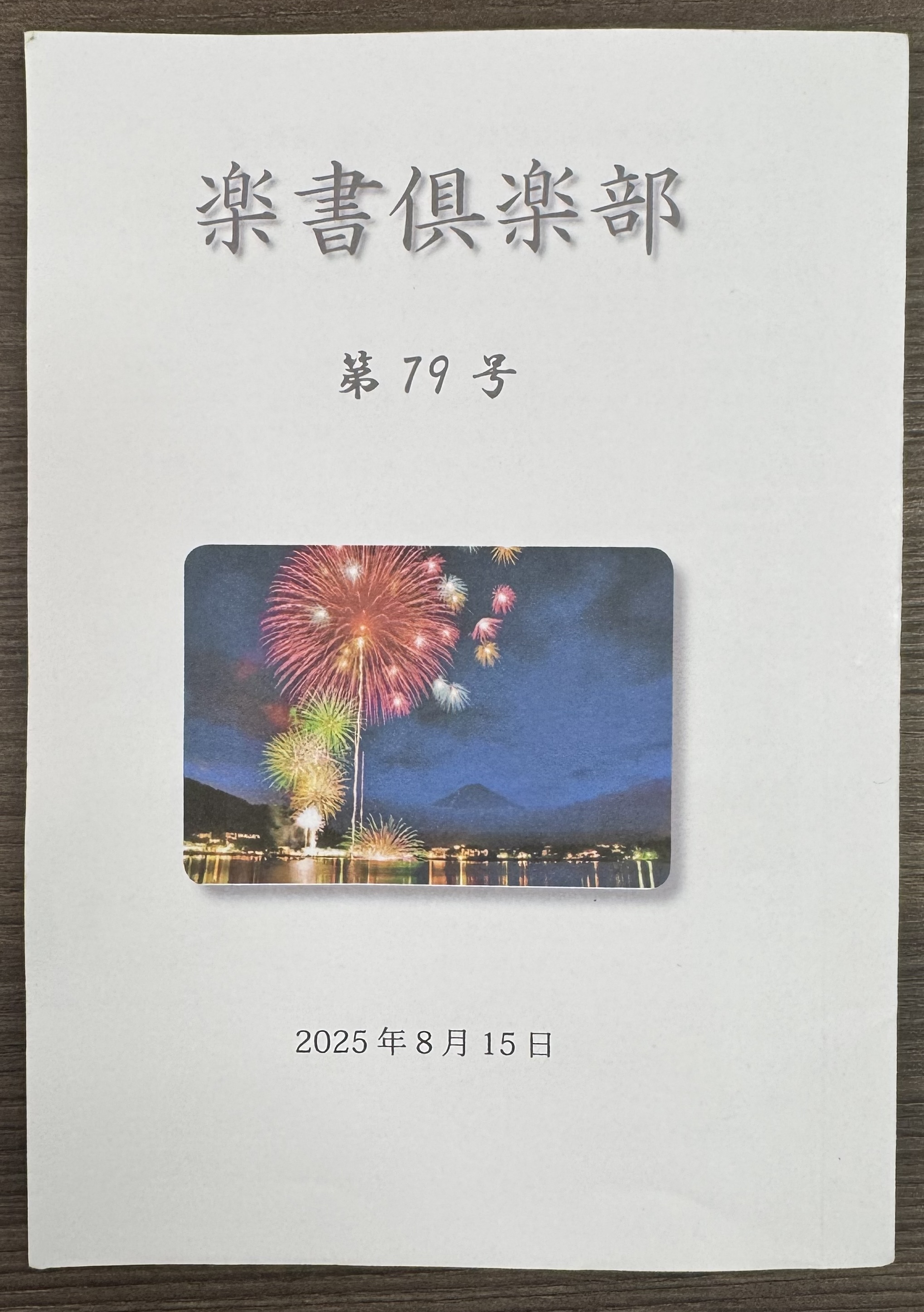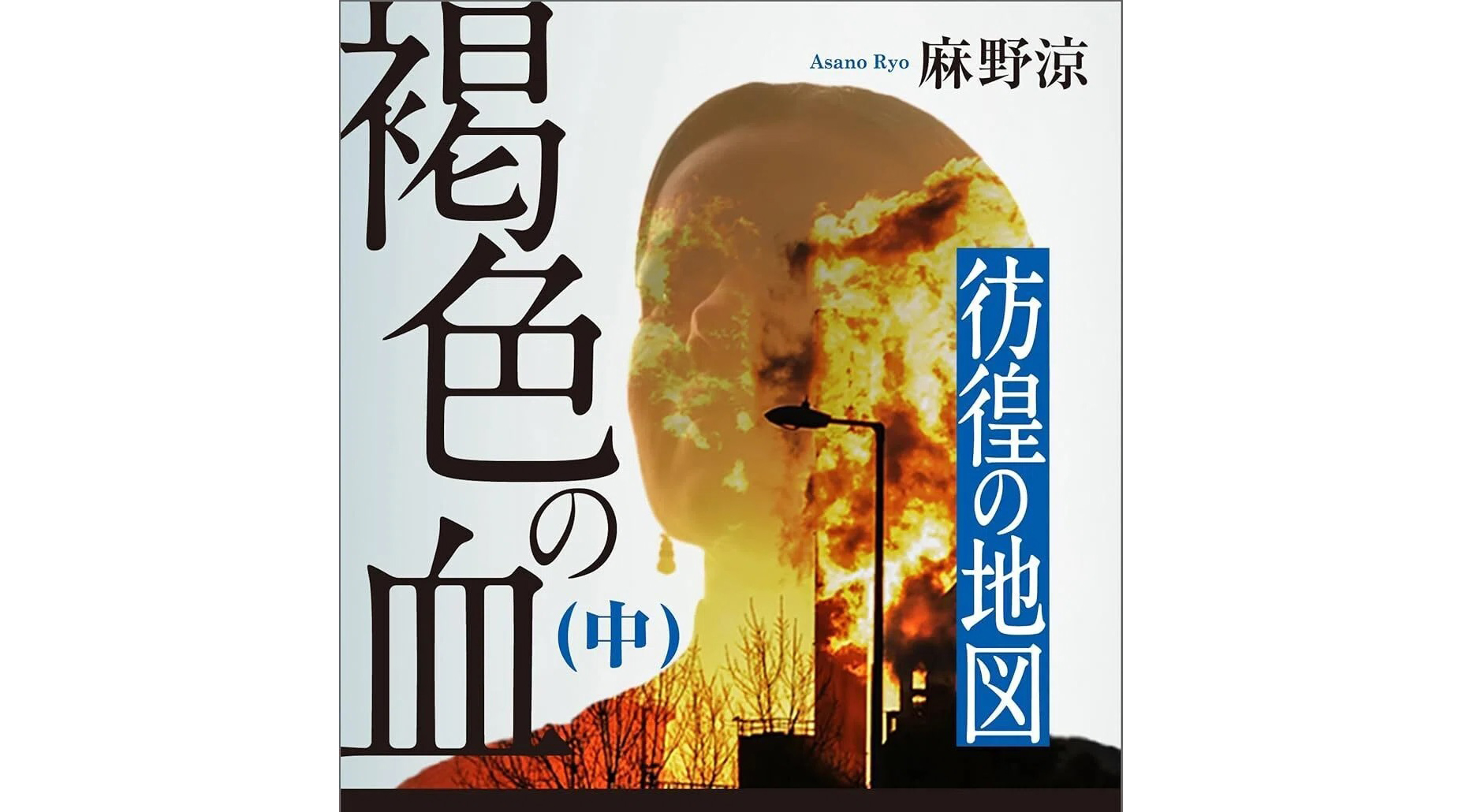麻野涼=『褐色の血』第一部「混濁の愛(上)」=《前編》=日本人の心の臨界点を探る旅

かつて日本文学の黎明期に第1回芥川賞を受けたのは、ブラジル移民を題材にした石川達三の作品『蒼氓』だった。それからおよそ90年を経て、再び移民の現実を正面から描いた長編小説が誕生した。麻野涼による『褐色の血』(幻冬舎刊)だ。全三部作の第一部にあたる「混濁の愛(上)」(www.amazon.co.jp/dp/B0FL1M3WWT)は、1970年代半ばのブラジルを舞台に、差別と愛、移住と家族の葛藤を描き出した重厚な序章だ。
著者の麻野涼は1970年代にブラジル移住して、パウリスタ新聞で記者をしていた。滞在した3年の間に日系3世の妻と出会い、帰国後はジャーナリストとして活躍。高橋幸春の名義で、ドミニカ移民問題を抉った『カリブ海の「楽園」』で潮ノンフィクション賞、家族の視点から勝ち負け抗争を描いた『蒼氓の大地』で講談社ノンフィクション賞を受賞した。のちに麻野涼名義で小説を執筆し始め、『死の臓器』は2015年にWOWOWでテレビドラマ化された。
元ブラジル移民という特異な経歴を持つ麻野涼は常々、資本やサービス・商品が軽々と国境を越えるグローバル化時代の中で、「どこまでが日本人なのか」というアイデンティティの境界線、心の臨界点を手探りする問題意識を持ち続けている。日本人の境界線を辿る精神の旅は、ナショナリズムとグローバリズムの境目に潜んでいる排外主義という地雷を踏み分ける危なっかしい道程でもある。
司馬遼太郎は『この国のかたち1』(23―24頁)の中で、《ナショナリズムは、本来、しずかに眠らせておくべきものである。わざわざこれに火をつけてまわるというのは、よほど高度の(あるいは高度に悪質な)政治的意図から出る操作というべきで、歴史は、何度もこの手でゆさぶられると、一国一民族は壊滅してしまうという多くの例を遺している》と警鐘を鳴らしている。
昨今の日本では外国人労働者の激増によって、「本来、しずかに眠らせておくべき」ナショナリズムが搔き立てられている。SNSによる無責任な情報伝達がそれに拍車をかけ、ネトウヨなどのプチ右翼が存在感を高めている。そのような、身の回りに外国人が激増するという環境変化に直面して、アイデンティティが揺れる日本人という社会問題を、自分の経験に照らして小説として表現できる作家はごく珍しい。その意味で、麻野涼は稀有な存在だ。
本作の中心にいるのは二人の若者、児玉正太郎と小宮清一。ともに日本で差別の痛みを受け止めざるを得なかった彼らは、新天地ブラジルで人生の新たな章を開こうとする。児玉は新聞記者としてサンパウロに渡り、在日韓国人二世の恋人・朴美子との別れを胸に刻む。彼女は「差別される韓国人と差別する日本人が一緒に生きられるはずがない」と告げ、愛を絶望に重ねて拒んだ。児玉はその傷を抱えながら、サンパウロの日系社会に身を投じ、やがて日系三世の女性と家庭を築いていく。(続く、深沢正雪記者)