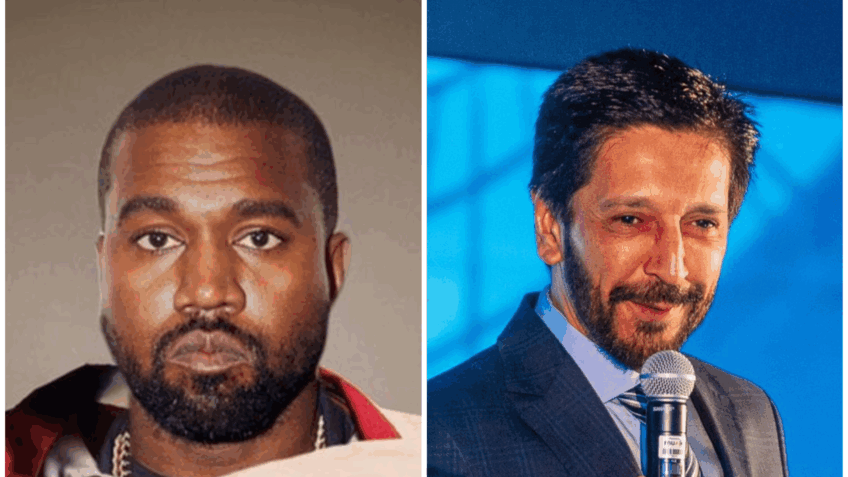日本移民迫害の裏に米国諜報機関=勝ち負けの背景にある地政学的構図=真珠湾攻撃の10日後にブラジル報告《記者コラム》

ルーズベルト大統領に上がったブラジルの報告
日本移民社会の「勝ち負け抗争」はしばしば、コミュニティ内部のナショナリズムの衝突として語られる。しかし、その背景には当時の国際政治、とりわけ米国の対南米戦略が色濃く影を落としていた。単なる「日本人の愛国メンタリティの衝突」では説明しきれない、より大きな圧力が作用していた。
1941年12月18日、真珠湾攻撃の10日後。ルーズベルト米大統領の机上に、CIA前身組織の報告書が届けられた。ブラジル内の親独組織や治安機関の動向を30頁にわたり分析したもので、日本移民調査の存在にも言及している。ブラジル政府・社会の側に広がっていた戦前からの対日不信は、このような国際的情報戦のもとで強化された。
なぜ勝ち負け抗争が起きたかといえば、ブラジル政府や国民による戦前・戦中からの日本移民迫害を抜きには語れない。そのストレスが溜まりに溜まって、じわじわと火力をかけられて爆発寸前の圧力釜のようになっていたところに、敗戦という火花が飛び、一気に爆発したのが勝ち負け抗争だ。つまり、同抗争は「結果」であって「原因」ではない。
「日本移民迫害」という構図は、アジア系人種に慣れていなかったブラジル人からの人種差別という部分もあるが、それ以上に第2次大戦という地政学的構図からの影響が強い。
前述の文書は、米国政府(主にCOI/後のOSS)が収集したブラジル内の政治・治安・親独勢力に関する詳細な報告(CIA-RDP13X00001R000100010004-9)でCIAサイトで公開されている。この文書は、ブラジル政府内部の高官、治安機関、軍部の動向、国内のナチ支持組織の活動、一般市民の反政府的な動きなどを、在伯の情報提供者(スパイ)がワシントンへ送ったものだ。
ドイツの影響が強いブラジル南部状況を報告
この報告によれば、当時のブラジルでは、警察・宣伝機関・軍部の一部に強い親ナチ傾向が存在した。特に、国家警察長官フェリント・ミュラー、宣伝局(DIP)長官ロリヴァル・フォンテス、陸軍大臣ガスパル・ドゥトラらは、国内におけるドイツの影響力維持に協力的であると指摘されている。これらの人物は、イタリア系航空会社LATIのブラジル内運航を保護しており、米国側はこれを重大な安全保障上の問題とみなしていた。
同時に、報告書はインテグラリスタ(ブラジル・ファシスト)運動の再組織化について詳述する。元指導者プラシド・サルガドは亡命先から党員に向けて書簡を送り、ヨーロッパの「新秩序」が成立しつつある今こそ、ブラジルがその秩序に参加できるよう、インテグラリスタの再結集とエスタード・ノーヴォへの協力を呼びかけた。
ドイツ諜報活動の存在も複数の書簡で強調されている。ドイツ軍将校が外交パスポートでブラジル南部に出入りしていたこと、サンパウロ州におけるナチ系集会がドイツ病院で行われ、地元の親独商人や移民社会が関与していたことが指摘されている。
一方、ブラジル政府は表向きには米国への協力に前向きな姿勢を示していたが、実際には対米協力は限定的で、米国側の分析者はこれを「アメリカの警戒心を和らげるための戦術」とみなした。政府内部の親独派が依然として強い影響力を持っていたため、米国側はブラジルの対独姿勢を信用しすぎてはならないと警告している。
文書後半には、地方での民衆の不満・デモも記録されている。映画上映の禁止をきっかけに、ドイツ系移民が多い地域で警察が対応できないほどの抗議が発生し、一部の兵士が命令に従わない事態も起きた。これらは政治的反乱ではなかったが、政府の統治能力に対する不安を生み、軍・警察の配置転換が行われた。
同文書は1941年当時のブラジルが、親独勢力・治安機関・軍・ファシスト組織・移民社会を背景に、枢軸国の強い影響下にあったことを詳細に報告。米国側はこの動向を綿密に監視し、ブラジルがアメリカの「裏庭」に組み込まれるよう外交・情報戦を展開していたことが読み取れる。
この報告書の歴史的な意義
この文書の歴史的な意義は、第2次世界大戦期のブラジルがいかに地政学的に重要で、かつ脆弱な均衡の上にあったかを示す一次史料という点だ。南大西洋の制海権は米国にとって決定的で、北東伯(ナタール・レシフェ)はアフリカ・欧州戦線を結ぶ補給ルートの要衝であった。
当時の航空機の航続距離は短く、北米から大西洋を跨いで一気に欧州に飛ぶ能力がなかった。そのため、もっと大西洋で陸間距離が短い南大西洋は、欧州戦線に米国が軍を送り出す上で、最重要な兵站ルートだった。そのため、米国はブラジルが枢軸寄りになることを脅威と捉え、政治・治安・宣伝・軍内部の親独派の実態を逐一把握しようとしていた。
この文書は、ブラジル内のファシズム運動(インテグラリスタ)やドイツ移民社会の影響力を明確に描き、南米が単なる「後方」ではなく、枢軸国の浸透と民主主義陣営(米国)のせめぎ合う競争空間であったことを示す。ブラジル政府(エスタード・ノーヴォ体制)は権威主義的で、国内には強い反米感情や独自の国家主義が混在していたため、米国はブラジルの政治姿勢がどちらへ傾くかを懸念していた。
本資料は戦時の外交・諜報活動の実像を明らかにする。後のCIAによる冷戦期のラテンアメリカ政策の原型がすでに形成されていたと言える。

ナチス運動に組み込まれたドイツ移民社会
ブラジルのファシズム運動「インテグラリスタ」(AIB)は、1930年代〜第2次大戦期にかけて、ドイツ移民社会と多層的に結びついていた。両者は正式な同盟関係を結んでいたわけではないが、思想的親近性・人的交流・政治的利害の一致という三つの軸で強く接近していた。
第一に思想的親近性だ。インテグラリスタはブラジル版ファシズムで、強烈な反共主義、国家至上主義、指導者崇拝、民族的統一を中心理念とした。これらはナチス思想と容易に共鳴し、特に「反共」「反自由主義」という点で、ドイツ移民社会の親ナチ層と自然な協力関係を生んだ。南伯のドイツ系移民地域では、既に1930年代からナチ党外国支部(NSDAP/AO)が活動し、そこで広まった民族主義的空気がインテグラリスタを受け入れやすくした。
第二に、人的交流と組織的接触だ。ドイツ系学校、協会、体育クラブ、ヴェーハラ(文化協会)などは、すでに高い組織力を持っていたため、インテグラリスタ側はそのネットワークを政治動員に利用しようとした。逆に、ドイツ移民社会にとっても、インテグラリスタはブラジル政府内部へ影響力を持ち込む経路となるため、互いの利益が一致した。
同文書にある通り、親独的警察官僚や軍人がインテグラリスタと接触し、ドイツ領事館やナチ系組織とも関係を保っていたことが米国側情報として報告されている。これは、ドイツ移民社会—インテグラリスタ—政府内部の親独派という「三角関係」を形成していたことを意味する。
第三に、戦時下の政治力学である。ブラジルのエスタード・ノーヴォ体制(1937–45)は、当初ファシズム的要素を帯び、反共を掲げていたため、インテグラリスタや親独派と一定の共通基盤があった。これにより、ドイツ移民社会は政治的保護を得やすく、インテグラリスタを通して間接的な影響力を維持した。特に、南部の都市では、ナチ支持者の集会や文化活動が、インテグラリスタ幹部を含むブラジル人右派と重なり合っていた。
インテグラリスタ運動はブラジル版ファシズムとしての理念によりドイツ移民社会の親ナチ層と結びつき、人的ネットワークと政治的利害の一致を通じて互いを強化する関係を築いた。この結合は、米国がブラジルを枢軸から切り離そうとする際の重大な懸念となり、大戦時の外交・治安政策に影響を与えた。

バルガスは当初「枢軸・連合の両天秤」
1930年代後半〜1941年のバルガス独裁政権は、強権的な国家統制、反共主義、指導者中心主義、宣伝機関の強化など、ヨーロッパのファシズムと共通点が多く、国内にはインテグラリスタ(ブラジル・ファシスト)やドイツ移民社会の親ナチ派が強い影響力を持っていた。そのため、バルガスは外交的には「どちらにつくか」を明確にせず、ドイツ・イタリアとアメリカを競わせて最大利益を得ようとする外交戦略をとっていた。
米国が使った「外交的飴玉その1」は鉄鋼コンビナート(ヴォルタ・レドンダ製鉄所)建設で、これは最も象徴的な誘引策だ。ブラジルは工業化の要である「国営鉄鋼企業」を強く求めていた。米国は1億ドル級の融資と技術支援の提供を申し出て、その見返りに連合国側へ誘導した。
「飴玉その2」は米国によるブラジル産商品の「戦略的買い上げ」だ。米国はブラジル経済を支えるため、コーヒーだけでなく、ゴム・綿花・カーネーション等の農産物を大量買い上げた。特に、コーヒー価格の下落を防ぐ、ブラジル経済の外貨収入を安定化させる、という効果を狙った政策が行われ、ブラジル側では「経済的生命線を握る米国の支援」と理解されていた。この米国政策は、まさに現在も生きている。
「飴玉その3」は軍事供与と基地建設だ。武器供与としてはブラジル空軍の近代化、「北東部基地」(ナタール)への米軍進駐と援助だ。その結果、1942年、ブラジルは枢軸国に宣戦布告。ドイツ潜水艦がブラジル船舶を攻撃したことも契機となり、ついに連合国側として参戦した。米国の経済・軍事的誘導が決定的役割を果たした。

戦時下の日独伊コミュニティの違い
大戦期のブラジルで、移民社会は「潜在的な外交リスク」とみなされた。戦争勃発後は枢軸国移民=敵性国民(潜在的に敵国の延長)として扱われる状況が生まれた。中でも、日独伊の三つのコミュニティは、特に政治的監視の対象となったが、それぞれの影響力には大きな違いがあた。
ブラジル政府の最大の懸念は、ドイツ系移民社会だった。19世紀以来の長い定住歴があり、100万人規模に達し、南部諸州で圧倒的な存在を示していた。高い教育水準・学校・新聞・協会があり独自の自治性の強い社会があった。
そこには1930年代からナチ党外国支部(NSDAP/AO)が積極的に浸透、学校・青年団・体育クラブなどを通じて親ナチ運動が展開していた。ブラジル政府も「国内にナチ〝飛地〟が存在」と懸念するほどだった。だから、ドイツ系は政治的に「最も影響力があり、最も警戒された移民社会」だった。日本移民もブラジル官憲から迫害されたが、ドイツ系への隔離政策は特に厳しく、日系以上に酷い目にあったという。
イタリア系移民社会はブラジル最大規模の移民集団を形成し、サンパウロ州を中心に農業・都市労働者として広範に定着。社会階層は多様で、上層にも下層にも広がっていた。1920〜30年代にムッソリーニ政権が積極的に「在外イタリア人政策」を展開し、文化協会・ダンテ・アリギエリ学校などを通じてファシスト的影響が広がった。しかし、ポルトガルとイタリアは文化的に近いため、社会的な同化が容易に進み、ドイツ系や日系ほど「凝集した民族ブロック」を形成しなかった。
戦時中、連合国側の勝利が見え始めると、イタリア系の雰囲気は急速に非ファシスト化した。政府からの監視はあったが、ドイツ系ほどの疑念は向けられなかった。文化的にはファシズムの影響あったが、政治組織力は弱い移民社会だったという。
これに対して、日本移民社会は急成長したが「異質性が極大」とみなされた。1930年代には大規模な農業移民コミュニティを各地を形成。サンパウロ州の農村に集住し、言語・文化・教育の独自性が強かった。ブラジル社会からは最も「外来性」が強い集団と認識された。
日本移民は国家主義が強く、皇国意識も保持されていたため、「日本政府の影響力が強いのでは」と疑われ、ブラジル政府は真っ先に日本語新聞や日本語学校の閉鎖を試みた。真珠湾攻撃後、最も厳格な監視対象になり、人種的・文化的に最も排除されやすい移民社会となった。
この大きな地政学的な構図の中で、日本移民迫害が行われ、その過大なストレスが勝ち負け抗争を引き起こした。前回紹介した「特定封鎖国民リスト」然り、ブラジル政府の背後には米国政府がおり、その情報収集と指図のもとに迫害も行われていた。サントス強制立退の背後に米国がいてもなんら不思議はない。ぜひ研究者の皆さんに明らかにしてほしい。(深)